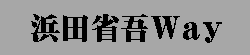
継続性トップ
ファン・サイトの浜田省吾Wayです。
浜田省吾のデビュー30周年時に公開の個人ブログ。【祝・40周年】
80年代半ば以降のバブル経済では、土地や芸術作品などが投機の対象となり、三菱地所のロックフェラーセンター買収やソニーのコロンビア映画買収等の象徴的出来事があった。
当時、東京の不動産価格は青天井と言われ、貸しビルやマンションは、その実質的価値以上の評価額で売買されていた。
不動産オーナーは、物件を利用したいという本来の顧客の要望には応えようとはせず、より高値で売却できる相場師(ブローカー)との取引を熱望した。堅い職業と思われていた銀行も、このブームに便乗して怪しげな相場師に資金の供給を続け、バブル経済過熱に加担した。
不動産は投機目的の相場師の手を経た後では、その価格は適正水準から乖離し、もはや誰もが手を出すことができない金額まで膨れ上がった。こうした現象は、土地転がしやマネーゲームと呼ばれ、海外からウサギ小屋と揶揄される狭いマンションを、ビジネスマンの高嶺の花としてしまった。
その異常さに誰もが気づく頃になると、土地神話は崩壊し、バブル経済は一気にはじけた。バブル経済の後遺症を治すため、銀行は不良債権処理に躍起となり、企業は適正規模への回帰を図るため血の滲むようなリストラを敢行した。バブル崩壊後に、生活に窮したり、人生計画の軌道修正を余儀なくされたりして、辛酸を嘗めた読者の方も多いだろう。
浜田省吾は1990年に発売したアルバム「誰がために鐘は鳴る」に収録された「詩人の鐘」の中で、「銀行と土地ブローカーに 生涯を捧げるような 悪夢のようなこの国」とバブルに溺れる日本経済を糾弾した。
これは無理をして購入したマンションが、バブル崩壊後には評価額が暴落し、生涯をかけて支払うローンだけが残った多くの人達の心情を代弁している。
そこには、マネーゲームを放置した国への怒り、重い負債だけを背負わされた人達への思いが込められている。
「詩人の鐘」の発表から15年後の2005年には、マンションの耐震強度偽装問題が発覚し、翌年の2006年初めにはライブドア粉飾決算問題による東京証券市場の混乱が生じた。
マンションの耐震強度偽装問題は、マンションの安全性よりも建設コストを下げることを優先し、利益を上げるためなら法律を侵し、住民の生命を脅かしても構わないという企業エゴを白日の下に晒した。
ライブドアの粉飾決算や脱税問題は、球団買収や国政選挙に乗り出した時代の寵児ですら、赤字決算を黒字に粉飾して投資家を欺き、自社の利益をひたすら追求する現実を見せ付けた。
これらの出来事は、事業の本質で利益を出すのではなく、違法な原価低減や投機で暴利を得て、そのしわ寄せを弱者に押し付けるという構図であり、15年前のバブル期と何ら変わらない。
バブル経済と現在の耐震強度偽装や粉飾決算・偽計取引問題は、他人を泣かせてでも暴利を貪るという点が共通している。
しかし、そのような政策や事業は長続きするものではない。人々の支持を得られなければ、短期的に利益を上げることには成功しても、その成功を継続し続けることはできない。
実際に、バブル経済は崩壊し、耐震強度偽装をした建築会社は倒産し、粉飾決算で投資家を欺いた会社の経営者は退陣した。
それでは、事業の本質とは一体何かと言えば、それは「顧客満足」に尽きる。どんな事業であっても、顧客の支持が得られなければ、長期間の安定経営は成立しない。顧客の支持を受けるためには、当然ながら事業者が提供するサービスについて、顧客の満足を得る必要がある。
つまり、事業の本質とは顧客満足を得るために、継続的に努力をしていくことだ。これは会社経営全体でも、各自に与えられた部署や担当という現場でも共通してあてはまる。
浜田省吾は、自らの最大のファン・サービスはライブであると位置づけている。この方針は決してブレていない。
ライブ・ツアーを敢行するには、バンドや舞台装置等の裏方を引き連れて全国を移動する必要がある。大勢のスタッフを動員するからには、当然ながら経費も掛かる。実はミュージシャンにとって、ライブの経費は負担であり、利益性は良いとは言えない。
単に利益を追求するなら、ライブは行わず、CDのみを多量にセールスする事を考えた方が効率は良い。ライブは極力行わず、テレビ出演でCDの宣伝を繰り返し、CDセールスを重視するミュージシャンも存在する。
だが、浜田省吾は音楽業界では異色とも言えるスタイルを貫いている。それは、テレビ出演やコマーシャルやドラマとのタイアップはほとんど行わず、CDのセールス・プロモーションは控え目だ。
一方で、採算性が良いとは言えないライブは、精力的に行っている。浜田省吾のライブは「ON THE ROAD」と呼ばれ、そのON THE ROADツアーのチケットは発売即日に完売となってしまう。
ファンの間でも、浜田省吾のライブは年々進化しているとの評価が高い。デビューから30年を経過しても、更にライブの質は向上しているのだ。
この質の高いライブを提供し続けることで、CDアルバムも安定数が売れている。つまり、浜田省吾はファンが喜ぶことを第一に考えて行動し、その上でプロモーターとして、採算性も両立させる手腕を発揮しているのだ。
ファンや顧客を無視した利益追求では、事業は長続きしない。事業を長期安定化させるのは、徹底した顧客満足への取り組みに尽きる。
事業者が提供するサービスに、猛烈なファンがつけば、経営は安定する。その基本を浜田省吾から学ぶべきである。
理想と現実。浜田省吾の曲の中に度々登場するフレーズだ。理想は夢、現実は日常とか暮らしという言葉に置き換えられることもある。
「J.BOY」-“掲げてた理想も今は遠く”“打ち砕け日常ってヤツを”
「Midnight Blue Train」-“描いた夢と叶った夢がまるで違うのにやり直せもしない”
「星の指輪」-“若い頃の計画(ゆめ)なんて もう思い出せない 忙しいだけの仕事に追われているうちに”
このように若き日の理想や夢と、それに立ち塞がる現実について、葛藤する様子が描写されている。
そんな理想について、少年期と大人になってからのとらえ方の違いを、浜田省吾は次のように語っている。
「 (子供の頃は)理想と違ったからといってゲンメツしても、それをつくったのは自分だからね。子供のころは家庭にしても学校にしても自分がイヤだと思うものは、みんな人から与えられたものでしょ。そこから飛び出すことがひとつの目標だし、それを拒否することが、ひとつのストレスのはけ口でもあるしね。ティーンエイジロックと呼ばれるものの詞の、唯一のポイントがそれでしょ。だけど、そこを過ぎた人は、自分のつくったものを捨てて出るか、それを壊してつくり直すしかない。それは、たいへんなことだよね。だれの責任でもないから、人のせいにもできないし。」(ef 1986年11月号より)
つまり、少年期は理想どおりに現実が運ばないとき、それを人のせいにできる。実際、学校にしても企業の新人教育にしても、その枠組みを用意したのは大人の世代だし、それに不満をぶつけるのは少年の特権ともいえよう。
かくいう遠山も、集団行動や規律を嫌う小生意気なガキだった。そのくせ、ひとりじゃ何もできずどこへ行くのかもわからない中途半端な反抗ぶりだった。
授業を抜け出すことはあっても、タバコをふかしたりゲーセンでたむろすることは無かった。数学の授業をサボって、世界史の自習をするような意味不明の行動をしていたような気がする。
このように特に明確な目的も無く、ただ大人が作った軌道に乗るのを拒むのは、ズルい対応だったかもしれない。拒否する以上は、自分で道を切り開かねばならないのだが、そんな苦労を背負う覚悟は無かった。
それが大人になってからの批判の矛先は自分に向かうものだから、始末におえなくなってくる。何か不平不満を口にすると、その原因には少なからず自分の怠慢が含まれている。
すると高校生のように、自分が潔白であることに勝ち誇って、無邪気に社会を批判することに引け目を感じたりしてしまう。
それは動物愛護に目覚めた0Lが、ミンクのファーや皮のブランド・バックを買い込むことを止められない様なあざとさだ。
そこで日々の暮らしに何らかの妥協をして、こんなはずじゃなかったという思いを封印する生活を送ることも多いのではないだろうか。
そんな現実とは、疑問や不安、絶望や退屈などネガティブな感情を打ち消しきれないものだ。
誰しもが抱えるそんな問題について、浜田省吾は解決を請け負うというスタンスはとっていない。
ただ、ライブで良質の音楽を提供し、一時的な高揚感や慰安を感じ取ってもらうように務めているという。
そして、ライブが終わっても参加者が前を向いて頑張っていこうと思えるような気分になれたら、それがミュージシャン自身の救いにもなると語っている。
それでは、現在は30代~40代の働き盛りのビジネスマンたちが、若き高校生だったころ、どんな夢を描いていたのだろうか。
強烈な特定の職業への憧れから、必死の努力をしてその職業に就くことを成功した人もいるだろう。
ただ、多くは漠然と学歴のレールに乗り、深く考えることも無く進学をして、給与や処遇を比較しながら就職先を決めたというパターンでは無いだろうか。
そしてほとんどの場合は、かつて憧れていた職業とは全く違うことをしている。
だからと言って、就職希望の変節が悪いと言いたいわけではない。人は自分の適性について若いうちから把握できてはいない。また社会的環境によって、就業の選択肢が狭くなることもあろう。
だから、特に何がしたいという明確な目標がなくても、まずは何でもやってみるという行動力が大事なこともある。
そして岐路に立った時、その瞬間ごとに後悔の無いチャレンジができているかが大切だ。そんな時に迷いを断ち切るきっかけが、小説であったり音楽であったりするものだが、浜田省吾の曲が重大な決断の背中を押してくれたというケースも多いように思う。
何しろ現代の詩人でもあり哲学者でもある浜田省吾が、時流と対峙しながら練りに練った歌詞をつくっているのだから。そんな優れた曲は時が経過しても支持されていくだろう。
浜田省吾は自らの音楽活動について、ライブとCD制作を二本柱と位置づけている。いわゆる車の両輪ってことで、どちらか片方が欠けても音楽道を突っ走ることはできやしない。
そのライブとCD制作については、次のように語っている。
「 変なたとえですけど、コンサートは産業でいうと“実業”なんです。現場にたくさんの人が集まって成り立つ。利益は少ないけど、確実に仕事をしてみんなが生きている。それに対して、CD制作は投機。金融業に近い。あるとき当たって大儲けする、というね。
でも、バブル経済にしても、そういう方向ばかりになって弾けたわけでしょう。ちゃんと製造業があった上で、金融や不動産投資があるべきだと思うんですよ。だから、コンサートにこだわっている僕は、その一番の根幹をやっている。
ライブに向かう意識も、昔はまず自分が先だったのが、今はまずオーディエンスがいて、次に俺たちがいるっていう感じになってます。これだけ長く自分が音楽をやってこれたのは、やっぱり彼らが支えてくれたからです。」(日経エンタテイメント1999年6月号より)
何という冷静な見方をしているのだろうか。普通、ミュージシャンであればCD制作も立派な創作活動であり、充分に実業と言えるはずだ。
それを敢えて投機と言い切ってしまうあたり、芯の強さを感じる。
恐らくCD制作にはライブほどの人手と経費はかからず、メガヒットとなったときには、その分莫大な利益を生み出す可能性があるから投機という表現をしたのだと思う。
逆にライブは大勢のスタッフが関わることが前提となり、利益を出すには様々な工夫が必要となる。文字通り汗をかいて必死に稼ぐ仕事だ。
世の中の経済活動でも、モノ作りをする製造業がしっかりと機能した上で、投機に励む金融業が成立する。その投機でラクに稼ぐという感覚が染み付いてしまうと、地味で苦労も多い製造業が割に合わない仕事に思えてしまう。
その結果、製造業離れが進んで、モノ作りをしていた人たちが不動産や株式の投資に血眼になった時代があった。
そう、バブル経済と呼ばれた1980年代後半の現象だ。
そのバブル経済が崩壊することを、浜田省吾は独特の感性で予見していたと他の章で述べた。それなら、バブル経済の後始末にジタバタする世間に対し、「そらみたことか」と評論家気取りですましていることもできたはずだ。
しかし、浜田省吾はそんな態度は取らなかった。その導き出した答えは次のようなものだった。
「 特に90年代に入って、こんな不景気ですごく厳しい時代になって、その中をみんな頑張って過ごしているわけじゃないですか。僕自身の音楽人生や作品のことだけを考えるなら、時間をかけてアルバムをつくった方がいいかもしれない。でも、これまで僕を支えてくれた人たちがそれぞれの現場で一生懸命頑張っているのに、自分だけが隔離された別世界にいて、音楽をつくるのは恥ずかしいと思った。」(日経エンタテイメント1999年6月号より)
つまり、苦労も多く利益も少ないライブは止めてしまって、じっくりとCD制作に専念することもできた。でも、それだと必死で不況に耐えているファンの人たちに申し訳ない。だったら、ファンが本当に喜んでくれるライブを続けて楽しんでもらいたい。そう考えて、ON THE ROAD 2001という前代未聞の4年間に及ぶライブツアーを敢行したわけだ。
ライブが製造業という浜田省吾的解釈であるなら、どこまでもモノ作りにこだわっていることになる。まさに頑固一徹の職人気質と言えよう。
そこには「稼げれば良い」というお気楽な考え方は存在しない。ここまでファンのためを考えて行動するミュージシャンだから、そのファンも裏切るはずは無い。ライブはどの会場も満員御礼だ。
話を日本経済に戻すと、バブル後のリストラや企業破産地獄を経験して、製造業は本業回帰を目指した。その血の滲むような努力の甲斐があって、景気は落ち着いてきたと言えよう。
しかし、今またネットトレーダーがもてはやされ、空前の株式ブームが起きている。自宅に引き篭もって株の売買益で稼ぐことや、ネット広告などの不労所得によって生活することが若者の憧れのライフスタイルになっている。
そんな虚業が流行する時代の空気は、30代~40代のビジネスマンの皆さんならデジャビュ(既視感)の錯覚が起きないだろうか?
確か過去にもそんなムードで盛り上がった時期があったはずだ。
そう、1980年代後半のバブル期だ。あの時ほどの浮かれ気分では無いにしろ、今もモノ作りからかけ離れたところで稼ごうとする人々が増えている。それを煽るマスコミ情報も氾濫している。
例えば、「ネット株売買で1億稼ぐ」「アフェリエイト月収を100万円にする」「ダイエットで稼ぐ」こんなキャッチコピーがあちこちで目につかないだろうか。ちょっと考えれば胡散臭さ100%だと気づいても良さそうなものだ。
バブルの後には強烈なシッペ返しが待っている。その事は痛いほど学習したはずだ。その予防法は、浜田省吾が身を持って教えてくれた。
自分にとって何が本業であり、どうすれば顧客は喜んでくれるのか。その原点を見失うことなく事業を継続することに尽きる。欲におぼれて、投機に走ることなかれ。
ショービジネスに関わる人々の心意気を表すスローガンとして「SHOW MUST GO ON」というものがある。
直訳すれば、「ショーは止められない」ということだ。雨が降ろうが、槍が降ろうが、戦争になっても、病気になろうが、破産しようが、親の死に目に会えぬとも、それでもショーを中止することは無いという壮絶な決意表明でもある。
浜田省吾は足かけ5年にもおよぶロングランツアーのON THE ROAD 2001で、2001年のアリーナツアーのテーマを「THE SHOGO MUST GO ON」と決めた。
これは浜田省吾の“ショーゴ”と「SHOW MUST GO ON」をもじったものだ。
このスローガンをプロ意識と理解すれば、一般社会で働く人々も共感できる部分はあるのではないだろうか。
例えば、鉄道マンであれば台風や大雪であっても、何とか列車の運行を継続しようと努力している。その関係会社の社員も含めて、運行を支えようと必死の努力をしている。
だが、そうした努力は乗客は認識していなかったりする。ダイヤが狂えば心ない誹謗を受けることもあるだろう。それでも職業意識に燃えて列車の運行を地道に継続している。
商社マン・銀行マン・スーパー店員に公務員など。誰もがプロ意識に燃えて仕事を継続しているから、日本経済は今日も回っている
実は「THE SHOGO MUST GO ON」というテーマは、戦時下に近い環境でもその真価を発揮した。
2001年9月11日。この日はアメリカで同時多発テロが起き、世界貿易センタービルと米国国防総省(ペンタゴン)が破壊された。この直後からアメリカは過度な警戒態勢を敷くようになり、日本国内でもアメリカ大使館や米軍基地の警備は厳しくなった。
また、旅客機をハイジャックしたテロであったため、航空機を利用した海外旅行等は自粛ムードが漂い、旅行業界は大きな損失を出していた。
そのような時期の10月13日に、浜田省吾は沖縄県の宜野湾で野外ライブを行っている。
沖縄といえば、ご存知の通り米軍基地が密集している地域だ。9・11同時多発テロから1ヶ月しか経っていない時期で、人が集まるライブは危険であるという察しはつく。
それは戦時下のピリピリとしたムードであっただろう。誰もがこの公演は中止した方が良いと忠告をしたそうだ。
それでもライブを敢行した浜田省吾は、次のように語っている。
「 日本全体で考えると、米国の基地を沖縄に押しつけてるわけですよね。戦後の歴史でそうなってしまったんですけど。なのに本土に住んでいる人間が、“あそこが危ないから行かない”というのはあり得ないだろうと。だから“絶対にやらなきゃいけない。特にこの時期にやらなきゃいけない”と思ったんですね。
ステージの上でも言いましたけど、“ジェット機の爆音で音がかき消されるようなことがあったとしても、それが沖縄の現実じゃないか”と思ってました。実際は、そんなことはなくて、のどかな雰囲気だったんですけど。」(日経エンタテイメント 2002年1月号より)
誰もが身の危険を感じて敬遠するような時に、敢えてショーの継続をやり通した心意気はサスガとしか言いようがない。
これが本当の“歌バカ”なのかもしれない。
沖縄のファンも、このライブには特別の印象があっただろう。当然に中止になると思われていたライブを、危険を承知でやってくれた。
米軍の厳戒態勢の影響で観光業はダメージが大きくなり、日常生活も不便な局面もあっただろう。そんな中で、普段と変わらず浜省がライブをやって元気付けてくれた。その行動力に胸を熱くしたファンは多かっただろう。
そこまでやれば、ファンは絶対に離れない。
日常のビジネスは、実は単調な仕事の繰り返しなのかもしれない。その仕事の一つだけを取り出してみれば、大したことはやっていないと思えてしまうものだ。
しかし、それを毎日毎日繰り返し、風邪をひいても、身内に不幸があったとしても継続し、何十年もやり抜けばそれは周囲から絶大な信頼をされるものだ。
何か事業を行う場合に、顧客から無条件の信頼を得ることができれば、それは大成功したと言えるだろう。
その信頼は簡単には得られない。短期的に莫大な収益を上げることができても、事業としての信頼感は醸成されない。
地味であっても、長期間安定して継続している事業こそ、真の評価に値すると言えないだろうか。
その継続性というものが、例え戦時下となろうとも中断することが無いというのは、これ以上は無いアピールだ。
つまり、何があってもやり通すという気迫がお客を安心させる。そこまでビジネスを徹底して継続すれば、お客は逃げない。
私達の日常生活には小さなつまづきから、大きな壁までいろいろな障壁があるものだ。ビジネスでも同様だ。そんないろいろな困難から逃げず、地道に障害物を取り除いて仕事を継続していくことが成功への正攻法と言えよう。
親子の相克というのは、小説や映画では普遍的なテーマとなっている。もちろん、音楽でも同じだろう。
子にとって親は最初の社会との接点であり、成長するにつれて親を超えようとする。その際に生じる心理的葛藤は、文芸のネタには最適だ。
浜田省吾にも当然ながら親子間の葛藤はあり、特に父親との衝突は凄まじいものだったようだ。
浜田省吾の父親は警察官であり、今でいう転勤族だった。そのため、浜田一家は頻繁に引越しを経験した。
父親は子煩悩で、浜田省吾も父を慕っていた。浜田省吾は父親の強い勧めもあって、まじめに勉強をして広島県内でも有数の進学校へ進んだ。
それまでは平穏な家庭環境であったが、浜田省吾が高校へ入学した頃から、父親との関係がギクシャクする出来事が続いた。
まず、浜田省吾はまじめに授業を受けなかったらしい。学園紛争や反戦デモの機運が高まっている時期に、利己的な進学のことしか話題に上らないクラスメートに辟易した。
そんな進学校独特の雰囲気に馴染めず、野球部に入って部活に熱中したり、生徒会活動に没頭したりした。
高校生活で溜まった鬱憤を、反戦デモへの参加や、職員室前でボブ・デュランの「時代は変わる」を独特の歌詞を付けて唄ったりして発散していた。
そうした所業を警察官の父親が聞き及ぶに至り、親子の対立は臨界地点に達した。
「お前を過激派にするために高校へ入れたのじゃない。ワシは恥ずかしくて明日から仕事へ行けん。学校を辞めい。」
こうして父親自慢の出来の良い息子は、その評価を暴落させた。社会的な反戦デモ隊と官憲の対立という関係を、家庭内にも持ち込んだのだから始末に終えない。
大好きだった父の期待に沿えない苛立ちと、矛盾した学校や社会の仕組みにフラストレーションは蓄積される一方だっただろう。
それでも高校を卒業し、浜田省吾は浪人生活を送ることになった。しかし、予備校に通うことはなく、遊びまわっていた。
そんな様子を父親が知り、大喧嘩となって浜田省吾は家出をした。
家を飛び出して転がり込んだ先は、京都に住む友人の下宿だった。その友人は彼女と同棲しており、一緒に暮らしていると何かと不都合が生じた。
男女の気配を感じると、浜田省吾は遠慮をして野宿に近い生活をした。そんな生活を数ヶ月間送ると、風邪をこじらせて深刻な体調不良となった。
そこで意地の張り合いを止めた浜田省吾は広島の実家に帰った。その時、父と母は何も言わず向かい入れ、それ以来浜田省吾は父親と喧嘩をすることは無かったという。
その後はまじめに勉強をして、神奈川大学に進学した。
これは有名なエピソードだが、遠山は大学生のときにその事実を知った。そして、成功する人物っていうのは家出の一つくらいしなくてはいけないのかと単純に思った。
しかし、家出をして半年間も生き抜くエネルギーは、自分には無いよなと自己認識をしたものだ。
現在でも親子の対立は社会にありふれている。しかし、親への反抗が家出や自立という方向に向かうのではなく、引き篭もってニートになるという形に姿を変えてきたようだ。
引き篭もりは、子の成長や自立とは反対の方向に作用する。これでは何の解決にもならない。子が家出をするようなパワーも無く、ひ弱になっているのかもしれない。
経済が成熟した今、社会のあらゆる場面で争いを回避する風潮にある。それが家庭の中にも浸透して、親子間でも本音を言わないという現象が生じていないだろうか。
浜田省吾は不満を口にして行動することで、深刻な親子の対立を招いた。反発心は家出をするほど凄まじく、両親はそれを受け入れた。
だが、これが現在の一般的家庭像であれば、恐らく互いに遠慮して本音をぶつけることなく心にシコリを残す方法を選択するのではないだろうか。
つまり、子の反発心のキバを抜くことが日常的に行われるのだ。去勢された子は反発することもなければ、自立することもできない。
大学に進学した後の浜田省吾は、学園紛争に明け暮れる大学に愛想を尽かし、半年で退学した。その後はミュージシャンとしてデビューして、売れない数年間を経た後でロック・スターの階段を登った。
このように浜田省吾の人生は、決して順風満帆ではなかったのだ。普通であれば社会からドロップ・アウトしてしまうような試練を幾度と無く経験している。
現在、受験失敗・ニート・自己破産・事業失敗・離婚など、さまざまな悩みを抱える人は多いだろう。それが原因で家庭も混乱してしまう局面もあるかもしれない。
しかし、諦めてしまえば道は続かない。今はどんなに低いところにいようと、必ず少しづつ階段を登る決意をすれば、過去の失敗が財産となることもあるだろう。
浜田省吾の歌に励まされるのは、彼自身が苦悩を昇華させてきた経験を有しているからだろう。
Never Giveup
言葉にするのは簡単だが、事業を継続させたいなら、決して諦めないことだ。
「ベストセラーよりロングセラー。」
これは著作物の作者であれば、誰もが憧れるものだろう。ベストセラーとは短期間に凄い売上げを記録することで、ロングセラーとは長期的に継続して売れ続ける現象だ。
一瞬で爆発的なセールス記録を作って、印税収入がガッポガッポ入るベストセラーも捨て難いが、それよりも長い間売れ続けて人々の記憶に定着するロングセラーの方が制作者冥利に尽きるだろう。
浜田省吾の楽曲は、もちろん1992年に200万枚近く売り上げた「悲しみは雪のように」のようなベストセラーも存在するが、その多くはロングセラーと言えるだろう。
アルバムやDVD等の売り上げもロングセラーの傾向はあるだろうが、カラオケで歌われる曲は古いものが多い。
「J.BOY」や「もう一つの土曜日」は1986年、「MONEY」は1984年にリリースされた曲だ。
30代から40代のビジネスマンが集うカラオケでは、誰かがこれらの曲を必ず歌うのではないだろうか。
このように多くのファンに愛され、口コミによる評価で売れ続ける曲はロングセラーの称号を得ても良いだろう。
その一方で、口コミでの支持とは対極の商業音楽も存在する。
何よりも売り手側の論理に基づく、えげつない程のマーケティング主導の音楽だ。別に音楽だけに限らないのだが、商品の品質やサービスレベルが低次元な状態なのに、広告だけは巨費を投じてガンガンに行うパターンだ。
あまりにも売り込み臭が強すぎると、いかがわしさを感じてしまう。
そのような迷惑な情報タレ流しは、今日の日本に溢れている。テレビで、週刊誌で、インターネットで。
「ブレイク間違いないのイチオシ新人」
「1ヶ月で100万円稼げる新規ビジネス」
「寝ているだけで痩せられる最終ダイエット術」
遠山はホームページによる営業活動だけで生業をしているわけだが、眉唾な情報や胡散臭い特ダネを発信しているホームページを見ると辟易する。特に一方的に送られてくる迷惑メールには、怒りを覚えてしまう。
そんなホームページで商売をするには、SEO(Search Engine Optimization)という技術の話題が避けて通れなくなってきている。
一般にホームページで商品を購買したり情報調査をしようとした場合、まずはYAHOOやGoogleという巨大検索エンジンを利用するのがセオリーと言えよう。
これはネット初心者でも知っている常識だ。
検索エンジンのフォーム欄に、調査したいキーワードを入力するだけで、有力な手がかりが掲載されたホームページがズラズラと並ぶのだから、実にお手軽だ。調査をするのに費用が取られるわけでもない。
商品を販売したい側は、その検索エンジンの表示結果に対して、自分のホームページがより目立つ位置に並ぶようにしたい事情がある。
実際に表示結果がより上位にある程、ホームページが閲覧して貰える確率は高くなる。表示結果が2ページ以降になった場合は、ほとんど人目に触れなくなってしまう。
商業立地に例えるなら、検索エンジンの1ページ目に表示されるホームページは、銀座や渋谷の繁華街、または国道沿いの一等地に店舗を構えているのと同様の効果が見込める。
しかし、表示結果が2ページ目以降の場合は、途端に人通りは途絶える。10ページ目以降となっては、もはや砂漠や月面に立地するに等しい。
このような事情はネットショップのオーナーは先刻承知しているので、検索エンジンの上位に食い込ませようと涙ぐましい努力が続けられているのだ。
SEOとは、特定キーワードに関して、検索エンジンの上位に表示させるための技術ということになるが、ここでもマーケティングのための過剰競争が繰り返されている。
大多数の情報を検索する側にとっては、自分が知りたい情報をより素早く把握したいのが本音だ。
目的の情報がわかりやすく解説され、そこで見つけた商品に魅力を感じるなら、検索ユーザーも満足するだろう。
しかし、検索をかけた結果、表示されたホームページは宣伝ばかりで有益な情報が何も無かったら、二度とそのホームページに訪問しない。
販売する側は、とにかく検索エンジンでの表示順位を上げることに腐心して、その対策にばかり精を出す。それが効を奏すると、情報量が不足していても上位に表示されることはある。
すると、そのホームページを踏んでしまった訪問客は、外れをつかんだ感覚に陥る。
検索エンジンは、現在のところは多くのホームページから紹介のリンクがされているホームページが、より価値の高いページだと解釈するシステムになっている。
この特性を逆手にとって、自分のホームページとは何の関係も脈絡もないホームページとリンクを結ぶ行為が一般化している。いわゆる相互リンクだ。
この相互リンクを乱発するサイトが、表示順位を上げるという神話が成立しており、このリンクをする作業のみに没頭する業者も存在している。
このように、“売りたい”“広告をしたい”という思惑を全面に出すことがマーケティングと勘違いすると、ユーザーの感情や要望を漏らしてしまう。すると、検索エンジンの上位表示には成功したが、売上は伸びないという現象に悩むことになる。
ロングセラーを志向するなら、拙速な大量広告は慎むべきだ。顧客から確実に評価して貰えるサービス体制を確立し、情報提供量も充分に用意するなど、足許を固めることが何より大切だろう。
ミュージシャンのファンであれば、そのミュージシャンのライブに参加して、ナマの音楽に触れてみたいのが人情だ。
しかし、当のミュージシャンにとって、ライブにかかる経費は頭痛のタネのようだ。というのも、ライブには照明や舞台美術、音響など多くのスタッフが必要で、会場の確保やチケットのセールスにも経費や人手はかかる。
これが全国にツアーに出るとなると、スタッフを丸抱えで移動するわけだから、そのコストは膨大となる。経営で一番コスト高となるのは人件費だが、ライブは多くのスタッフを必要とするため、どうしても経費は高くついてしまうらしい。
ファンはそんな事情にはお構いナシに、お目当てのミュージシャンの全国ツアーを渇望するのだが、その期待にこたえるのは相当にきついのが実情のようだ。
そんな予備知識を得て浜田省吾のライブを観察すると、いろいろと考えさせられる。
なぜかと言えば、浜田省吾のライブには、見るからに費用がかかっていることが明白だからだ。
まず舞台装置が大掛かりで、大型モニターには全国各地の風景が映し出されている。いわゆるご当地映像をふんだんに使う。
2001年の“ON THE ROAD 2001”ツア-からは、アリーナ席の中央部を潰してセンター・ステージを設けている。これはアリーナ席の後部であっても、ライブの臨場感が味わえるようにする配慮だと思うが、その狙いは見事に成功している。ライブ後半部のセンター・ステージでは、1万人規模のアリーナの観客が、小さなライブハウスで盛り上がるような雰囲気となる。
浜田省吾がセンター・ステージの真下にいるファンに対して「今日は夫婦で来たの?」等と語りかければ、本当にそこが100人規模のライブハウスであるような錯覚に陥る。
ファンにとっては嬉しい限りのサービスぶりだが、このセンター・ステージを設けることで座席を潰しているので、貴重な売上を削っていることになる。
更には、ツアーの企画自体にも驚かされる。
1998年から1999年にかけての“ON THE ROAD 2001”ツア-前半部では、主に全国の小ホールを回っている。座席数が2,000にも満たないような会場を回るので、収支はカツカツであったろう。
極めつけは、奄美大島でのライブだ。離島まで機材を船便で運び、スタッフは航空機の定期便をほぼ貸切状態で移動している。その様子はDVDの「ON THE ROAD 2001」に収録されていて映像で確認できるが、傍目に見てもこれは赤字だろうという印象だ。
また、同ツアーでは野外コンサートも行ったが、そのコンセプトは「雨天順延」だった。実際に昭和記念公園では雨に祟られ、翌日に延期をしてライブを実施した。これも経費はかかっている。
このように、浜田省吾のライブは尋常ではないファンへの配慮と、採算度外視ではないかと思わせるほどの思い切りの良さを感じさせる。
それでも、ライブ・ツアーについては赤字では無いようだ。浜田省吾は初期の頃はホリプロダクションに所属していたが、ライブをレコードのセールスのためのツールとしか位置づけず、ライブの採算性を軽視する方針に納得がいかなかったようだ。
それで1983年に現在のROAD&SKYという事務所を設立し、ライブ中心に音楽活動を継続するようにしたと語っている。そのためには、当然ながらライブで利益を出さなくてはならない。
ファンには窺い知れない部分だが、ファンに満足を提供しつつ、ライブで収益を得られるように賢明な経営努力がされているはずだ。
恐らく個々のライブ会場では赤字となった所もあるかもしれない。しかし、ツアー全体では収益を上げているはずだ。
このような収益を出す仕組みは、経済活動でも共通する部分がある。例えば、会社の決算で言えば、単独の企業では赤字であっても、グループ企業全体の連結決算では黒字になるケースもあろう。
もう少し小さな事例では、小売業のある売り場で、単品では人気商品を赤字販売しても、それが集客剤の役割を果たし、売り場全体では売上が伸びる。よって粗利益はミックスされて、黒字となるというケースもある。
つまり、時として赤字になるような冒険をしても、それが顧客に大きな感動を与えれば、後からその出血分を補って余りあるほどの収益をもたらす可能性があるのだ。
ただ、ビジネスマンが注意をしなくてはいけないのは、赤字の先行投資の見極めだ。いつかは利益が出ると予測して、延々と赤字事業を継続した結果、取り返しの付かない事態に陥っては元も子も無い。
先行投資については、一定期間の評価をして、採算に合う見込みが無ければ打ち切る覚悟も必要だ。
情熱的な冒険と、冷静なそろばん勘定と、その両方を天秤にかけながら事業を続けたいものだ。
1976年4月21日に、浜田省吾はアルバム「生まれたところを遠く離れて」でソロ・デビューをした。
その時代背景としては、高度経済成長後のオイルショックを経て、社会は激動の中で安定の道を模索していた。中核派と革マル派の抗争激化などの事件もあったが、学生運動は確実にその終焉を迎えつつあった。
当時、浜田省吾は学園闘争で荒廃した神奈川大学を中退し、ミュージシャンとしてソロ・デビューする道を選んだ。(前年の1975年にはAIDOというグループのドラマーとして、アルバム・デビューはしていた。AIDOには、浜田省吾のツアーには欠かせないギタリストの町支寛二や、現在はROAD&SKYの社長を務める高橋信彦も所属していた。)
しかし、経済的に支援してくれるスポンサーがいた訳でもなく、現在のようにミュージシャンが確立された職業とは言えない状況だった。
当然ながら、音楽活動を継続する資金は乏しく、生活も苦しかったようだ。今では信じ難いことだが、浜田省吾もアルバイトをしながら生活費を稼いでいた。
デビュー・アルバムに収録された「路地裏の少年」には、「アルバイト 電車で 横浜まで 帰る頃は 午前0時」という歌詞があるが、これは当時の実体験に基づくものだそうだ。偉大なロック・スターも、デビュー初期は生活苦を味わっていたわけだ。
成功が約束されていたわけでもなく、生活の目途も立たない、そのような状況で、浜田省吾はデビュー・アルバムに全てを賭けていた。「これが最初で最期のアルバムになるかもしれない」。このような背水の陣を敷く覚悟で、制作に没頭したと述懐している。
結果として、デビュー・アルバムは売れなかったが、「路地裏の少年」を気に入ってくれた音楽関係者が複数いて、その後の浜田省吾を精神面で支える存在になっていったそうだ。
このように社会的成功を収めた人物でも、事業を起こした当時(起業時)には、大きな不安を抱えている。順風満帆なスタート・ダッシュを出来るケースの方が少ないのであろう。
ここで事業の継続がいかに厳しいものであるかを示す数値を2つ紹介しよう。
まずは2002年の起業統計調査によると、1年間の新設事業所数は26万件で開業率は4.2%。これに対して、廃業事業者数は39万3千件で廃業率は何と6.4%となる。
つまり、今の日本経済においては、新規開業による登場よりも、廃業による退場の方が多いのだ。
また、少し古い資料になるが、1998年の中小企業創造的活動実態調査によれば、開業後の1年未満で廃業する事業所は30%に達し、更に5年未満では75%が廃業するというショッキングなデータがある。
一説によれば、開業後10年経過した場合の企業生存率は5%以下と言われている。
このように起業は簡単であっても、その事業を長期間継続していくことは、本当に難しいことなのだ。
これはミュージシャンという雲の上の職業では無くても、ごく身近なありふれた仕事でさえも、事業をしていくことの厳しさは変わりが無い。
そういう遠山も、2003年4月に遠山行政書士事務所を開業した。
実は行政書士という仕事について精通していたわけではない。この時点では、単に行政書士の資格を有しているという程度に過ぎなかった。
開業資金も営業人脈も業務ノウハウも、全て皆無だった。いわゆる金ナシ・人脈ナシ・ノウハウナシの“三重苦の困ったちゃん”だった。
こんな“困ったちゃん”が、独立起業しても食っていけるわけがない。そのくらいの常識は遠山も持っていた。
そこで、家族を飢え死にさせないために選択したのが、週末起業だった。つまり、当時は会社勤務のビジネスマンをしながら、いつかは独立を夢見て行政書士業を副業として始めたのだ。
日中は会社勤務をする傍らで、夜間と土日を行政書士の業務に充てるという思惑だった。
そのために、行政書士の仕事を誘引するためのホームページを作り、訪問者が問い合わせをしてくれる事を期待した。
もちろん、このような甘い計算通りに物事は運ばない。開業して半年は、1件の依頼もなかった。
自分の思いとしては、早く行政書士業を軌道に乗せたかったが、あまりの無反応に頭を抱えてしまった。こういう時の心境は、精神的にキツいものだ。
それでも、ホームページ閲覧者から激励の言葉を頂いたり、ホームページによる集客で実績を上げている同業者に刺激を受けたりしながら、方向性としては間違っていないという感覚を得ていた。
その後、ネット上の様々なエキスパートの助言を得ながらホームページの改良を続け、会社員としての月収よりも行政書士業の収入が上回るようになり、2004年6月に晴れて独立することができた。
起業や事業の継続には、適切なマーケティング判断が不可欠だが、起業者の信念と周囲の理解も必要だ。
起業直後は誰でも苦しいものだ。その苦境を突破する原動力は、やはり起業者の信念の強さと、それを支える理解者にあると思う。