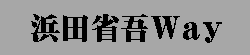
マーケティングトップ
ファン・サイトの浜田省吾Wayです。
浜田省吾のデビュー30周年時に公開の個人ブログ。【祝・40周年】
2006年夏に、浜田省吾は2枚のベストアルバムをリリースし、秋口からはホールツアーを開始している。
ツアーの様子は公式ブログでも紹介されており、その精力的活動に狂喜するファンも多い。
しかし、相変わらずテレビを中心とするマスコミに登場することは無く、チケット争奪の激戦をクリアしなければ、浜田省吾が歌い語る姿を目にすることはない。(DVD鑑賞できるではないか、というツッコミは遠慮して頂こう。)
浜田省吾が築いたセールス記録として印象に強いのは、1992年発売のシングル「悲しみは雪のように」(170万枚)と2000年発売のアルバム「TheHistoryOfShogoHamada“Since1975”」(150万枚)だ。
これらはメガヒット作品と言えるだろう。
当サイトの他ページでも取り上げているが、浜田省吾は音楽がセールス記録だけで語られる現象を危惧している。
音楽プロモーションがテレビと連動することでシステム化されて、ごく一部のメガヒット曲とその他の全く売れない曲に二極化する現象についても、警鐘を鳴らすコメントを多く発している。
このような圧倒的なマスコミの作用によって、ヒット曲のルールが定められ、音楽の多様性が損なわれることに憂いを表明する音楽関係者も多かった。
しかし、このマスコミによる画一的メガヒット曲垂れ流し現象も終焉を迎えそうだ。
そのキーワードは、現在の流行語といっても良いロングテールだ。
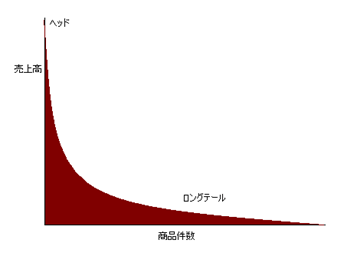
ロングテールとは、ワイアード編集長のクリス・アンダーソンが、その著書「ロングテール」で紹介した経済理論といえる。
音楽のタイトル数を横軸にして、個別タイトルの売上を縦軸にして売上順に並べると、上図のようなグラフが出来上がる。
このグラフの形が、首を伸ばした尻尾の長い恐竜のように見える。
その尻尾の長さを比喩してロングテールと呼んでいる。
クリス・アンダーソンの著書から事例を引用すると、アメリカの音楽業界では2000年を境にしてメガヒット曲が激減したそうだ。
例えば、2000年のトップセールス5のアルバム(ブリトニーやエミネム)の合計売上数は3800万枚だが、2005年のトップセールス5の合計ではその半分の1970万枚しか売れなかった。
同様に日本の音楽業界でも同じような現象は起こっている。
かつての浜崎あゆみや宇多田ヒカルは、アルバム・リリースの度に100万枚はクリアしていたものだが、近年ではそこまでの勢いは無い。
他にも100万枚を超えるミリオンセラーは生まれ難くなっている。
かつては恐竜の頭(ヘッド)の部分の売上に依存していた音楽業界だったが、このヘッドの高さが頭打ちになっているのだ。
その代わりに、尻尾(テール)の部分が横方向にどんどんと延びている。
これは音楽の提供がレコードやCDという有体物から、iPODや携帯電話、パソコン(MD)へのダウンロードという無形の形にシフトしていることがあげられる。
つまり、2000年付近までは楽曲を購入するにはCDショップの店舗に出掛けるしかなかった。店舗にはCDの陳列が限られるため、どうしても最新のヒット曲しか並ばない。よって、過去の名曲や浜田省吾のアルバムは目立たない位置にひっそりと置かれるだけだった。
しかし、携帯端末へのダウンロードや、アマゾンでCDを注文すれば、簡単に膨大な曲を入手できるようになった。曲のリストは無尽蔵で、しかも容易な検索手段も用意されている。
これはインターネットによる技術革新の賜物だ。
このように過去の曲も含めた膨大な検索手段を手にしたリスナーは、もはやテレビだけを情報収集の手段とはしていない。
そうしてテレビはメガヒットを作り出す神通力を失い、リスナーは携帯端末に自分の嗜好にあった曲ばかりを蓄積していく。
(ちなみに私の蓄積は圧倒的に浜田省吾が多いわけだが。)
その結果、より多くのタイトルが広範囲のリスナーに聴かれるようになり、いわゆる尻尾の長いロングテール現象が生じている。
浜田省吾やSONYミュージックも、そうした時流は把握して、曲のネット配信には積極的だ。特に浜田省吾のような30年ものキャリアを持つベテランは、豊富な名曲リストがあり、このようなロングテール現象によって掘り起こされる需要も増えていくだろう。
このロングテール現象は音楽業界に限った話ではなく、書籍や文房具をはじめあらゆる商品やサービスについても起きている話だ。
単なる現象ではなく、革命であるというとらえ方もある。確かにインターネット普及以前には、古い曲や無名のアーティストの作品を一般人が見つける手段は無かった。
その不可能を可能にしたのだから、これは革命なのかもしれない。(実際にクリス・アンダーソンは産業革命に匹敵する程の革命だと表現している。)
マスコミや大手商社に牛耳られた流通が、消費者の手に開放された。
確かにこれは革命かもしれない。
最近の浜田省吾のライブでは、MC(演奏休止中に演奏者がトークをする)の時に恒例行事となっている儀式がある。
それは、浜田省吾自身が「オレがライブをやっていく内は、ずっと継続していく」と宣言しているものだ。
一体、何だろうか?
答えは「年齢チェック」である。浜田省吾も、ライブに参加するファンの年齢構成が気になるらしい。
観客に向かって、「10代の人、手を上げてー」と尋ねる様子は、微笑ましくもある。
実際の統計は無く、遠山の感覚的計測では、その年齢層別は以下のとおりだ。
10代 5%
20代 10%
30代 30%
40代 35%
50代 15%
60代 5%
ファンのメイン・ボリュームは30代から40代の年齢層ということだろう。しかしながら、10代から60代まで幅広いファンを集める魅力はさすがと言うべきだ。
このような幅広い世代に対して、遠山が参加したライブでは次のように声をかけていた。
どうだろう?
浜田省吾の言葉の一つ一つは、様々な年齢層のファンのことを考えて発せられていることが理解できるのではないだろうか。
これはファンに対する実に細やかな配慮だと思う。親子ほども離れた年齢層のファンの心を、的確に捉えるのは彼のキャリアのなせる技だろう。
ちなみに、1992年時点ではファンクラブ会員の平均年齢は26.2歳だった。(1992年会報「ALL ABOUT SHOGO HAMADA」より)。
全くの余談であるが、遠山は当時23歳でこの年に結婚をした。その頃のライブ参加者は、当然ながら皆若かった。
しかし、2005年のライブに参加した時には、ファンの中心層は前述のように30~40代となっており、親子連れも増えていた。何か同窓会に参加するような感慨深さがあった。
年を重ねていくのは、浜田省吾のファンばかりではなく、実は日本の人口動態にも大きな変化が起きている。
いわゆる少子高齢化社会の予兆である。
すごく単純な話だが、ある夫婦が子供を二人産めば、長期的に人口は維持される。一人しか産まなければ、夫婦が死亡した場合は人口は一人分減ることになる。
これを数値化したのが合計特殊出生率という指標だが、これが2.05以上であれば人口は維持される。しかし、2004年6月時点で合計特殊出生率は1.29となっている。間違いなく若年層は貴重となり、人口は減少していくことは明らかだ。
一方で戦後のベビーブーム世代(いわゆる団塊の世代)は、2007年から2010年の間に60歳に達し、多量の定年退職者が発生する。この期間の退職金総額は80兆円にも達すると言われ、その使途が大きなビジネス的関心を呼んでいる。
つまり、子供や若年層は減少し、定年退職者は激増するというのが、日本経済の目前の課題になっている。家計に例えれば、働き手がいなくなり、扶養家族ばかりが増えるという状況だ。
更に製造業を中心とした中規模以上の企業は、日本国内の賃金負担に耐えられず、工場をどんどん海外に移転している。今は中国やベトナムへの転出がブームだ。
国内に残った企業は、賃金コストを抑えるためにパート・アルバイトや派遣社員の雇用を増やし、逆に正社員を削減している。2002年の総務省調査によれば、全国のパート・アルバイト比率は30.5%にも達するという。
少子高齢化で働き手が少なくなることを嘆きながら、貴重な働き手の就労の場所は減少し、必死で見つけた仕事がアルバイトというのが、これからのありがちな問題となる。
そんな時代を生き抜いていくビジネスマン世代は、働き方とか生き方の発想を変えていかなくてはいけない時にきているのではないだろうか。
極論すれば、多数の日本人の頭の中は、未だに高度経済成長期の幻想をひきずっていると言える。
それは、大企業に勤めて、大量生産・大量販売に関わって良い収入を得て、郊外に一戸建てを買うというライフプランだ。それが悪いとは言わないが、実現し難い夢になっていくのは間違いが無い。
何故なら、大量生産モデルは海外へ移転し、日本国内で生き残る産業は、極めてニッチな需要に対応するものになっていくことが予測できるからだ。
顧客のわがままとも言える細かい注文に応えることが出来る事業しか、日本国内では生き残れないだろう。それは、大企業では苦手な(効率の悪い)手法であり、若き起業家達がニッチな市場を開拓していくスピリッツに期待したい。
音楽も工業製品も、同一規格品を大量に売りさばく時代は終わったのだ。各年代や地域ごとの事情に応じて、柔軟なサービスを提供できる機動力こそが必要だ。
浜田省吾もファンの年代や地域別の特性の把握には熱心だ。その真正直な姿勢を見習いたい。
浜田省吾はライブ会場の規模の違いに応じて、ライブの内容や趣向を変えている。大別すると1,000人規模のホール会場、10,000人規模のスポーツ・アリーナ会場、数万人規模の野外公園会場という位置付けだ。
アリーナクラス以上では、ライブの際の視覚的工夫が重要となる。なぜなら、会場は広く後部の座席からはステージ上のミュージシャンは数cm程度の大きさにしか見えない。座席位置の違いで、ライブの臨場感が変わってしまうという不公平が生じる。
そこで、浜田省吾はアリーナ会場では大型スクリーンを導入するようにスタッフへ求めた。大型スクリーンでライブ・パフォーマンスの様子を投影すれば、会場の隅の座席であってもファンは盛り上がることができる。
野外ライブでは、このような大型スクリーンを活用するのはスタンダードな流れとなっているが、室内アリーナではまだ希少だ。その理由としては、やはり大型スクリーンのレンタル費用の問題がある。
そこは費用対効果の検討と、運営スタッフの懸命の努力があったのだろう。
浜田省吾のアリーナ会場でのこだわりはもう一つある。それは前面のメインステージの他に、センターステージを設置することだ。
センターステージとは、アリーナ席の中央部にプロレスのリングのような特設ステージを設けて、ライブの後半部はその場所で演奏を行うスタイルだ。ステージを2つも作るのだから、経費は余計に増す。
また、センターステージを作ることで中央部の座席を潰すことになるので、その分の入場料収入は減る。
メインステージでは大型スクリーンを活用して映像をフルに流し、更にセンターステージまで追加するわけだから、その経費コントロールには頭が痛かっただろう。
そのようなコスト的デメリットを抱えてまで、どうしてセンターステージにこだわるのか?
その答えは浜田省吾が求めるライブのクオリティにある。
浜田省吾はライブの醍醐味は生の演奏と観客との親密性にあると考えているようだ。ステージ上のミュージシャンと観客の一体感が味わえるのは、1,000人規模のホール会場が限界だ。
遠山も過去のON THE ROADツアーにおいて、ホール会場とアリーナ会場
の両方を体験したが、ホール会場の親近感と比べて、やはりアリーナ会場ではどこかによそよそしさを感じたものだ。
ホール会場では自分が叫んだ歓声が浜田省吾に届いていることが実感できるが、アリーナ会場ではそうはいかない。周囲の観客も同様に感じているためか、どうも行儀良く曲を聞き入る形になってしまう。
浜田省吾はライブ会場の違いによる温度差についても、何とか改善したいという気持ちがあったのだと思う。
そこで、アリーナの中央部にセンターステージを設けることで、座席の不公平感を緩和し、ライブ後半部はアリーナをホール会場の雰囲気に変えるマジックを披露したのだ。
このマジックは大好評で、メインステージでの演奏とは異なった盛り上がり方を実現した。
また、会場へのこだわりとしては、ドームやスタジアムではライブをしないというポリシーもあるようだ。
これは過去に横浜スタジアムでライブを行った際に、アリーナでも野外でもない施設で演奏をする難しさを感じ取ったからと述懐している。
つまり、浜田省吾は会場の規模や施設を層別して、それぞれの適切なサービスの仕方を作り上げているのだ。一定のサービスレベルに達しない施設では、ライブをしないという主義も徹底している。
このように場所や客層に応じたサービスの層別や絞込みは、ビジネスの場面でも必須といえよう。
よく「お客様には平等に接する」という原則論を標榜する職場があるが、この鉄則も運用を誤るとサービスの画一化と酷評されてしまう。
例えば、家具の接客でも単品のテーブルだけを探しにくるお客と、婚礼家具一式を探しにくるお客とでは、販売員に求められる商品知識や接客レベルは大きく異なるだろう。
それなのに、単品の購買客と同じ程度の応酬話法しかできなければ、大型商談を逃すことになってしまう。
商機を確実にGETするためには、顧客層の違いを理解して、それぞれの客層の心理にジャストフィットする商材の提案や提供ができなくてはならない。
少し話題は変わるが、今は何でも低価格志向で、販売店はローコストオペレーションこそが万能だという哲学が浸透しつつある。
確かに消費者にとって、良いものがよりやすく買えればありがたいことだ。
しかし、「安ければ必ず売れる」ものではないという現状認識も必要だろう。外資系のスーパーで新学期用品としてランドセルを破格の値段で売り出しても、これはほとんど売れなかったという。
アングロサクソンの合理思考だと、安価で品質は通常のランドセルを売り出せば、過剰スペックで高い日本製のランドセルを駆逐できるというシュミレーションが成立する。
だが、実際には高級ランドセルばかりが売れて、それなりのランドセルは在庫の山を築くことになった。
これは日本人の父母や祖父母の「子供には良いものを贈りたい」という心情を理解しないマーケティングの失敗といえよう。
このようにサービスというものは均質であることが良いとばかりは言えない。浜田省吾がライブ会場の規模に合わせてコンサートの内容を工夫するように、ビジネスの現場でも顧客の要望に応じたサービスレベルの差別化は必要だ。
現在の音楽業界では、一部の大ヒット曲が生まれる一方で、圧倒的多数のミュージシャンの曲は注目されることもなく忘れ去られている。
大ヒット曲はドラマやCMとのタイアップにより作り出されていることは、他の章で何度も述べたとおりだ。
こうした傾向を浜田省吾は次のように分析している。
「リスナーがすごい保守化してきて、それは世の中全体的に言えることだけど、ものすごいビッグ・セールスのものとそうでないものの落差が大きい。売れるものと売れないものが段階的に散らばってるんじゃなくて、二極化してるでしょう。それは世の中の流れ同様、保守化してるんだろうとは思う。
ロック・ミュージックが若かった頃は、ミュージシャンもリスナーも、とても冒険してたよね。新しいサウンドに対して貪欲だったし、新しいサウンドをミュージシャンの方はつくろうとしてたし、リスナーは探そうとしてた。でも今はもう、たぶんそういうものってないんじゃないかな。やっぱりヒットしているものを聞くと、リスナーの欲しがるものを提供してるっていうつくりですよね。歌の内容もメロディもサウンドも。それがいいか悪いかは別にして、けっきょくビジネスに徹した音楽作りになってると思う。
僕なんかは、正直言うと少し反骨気分ってのがあるから“冗談じゃないよ”と思うところがあるんだけど。」(「ROAD&SKY ファンクラブ会報57号」より)
つまりヒット曲は極めて限定され、音楽のジャンルや売れ方に多様性が無いとも言えるだろう。
このように圧倒的に強いもの、注目を浴びるものに大衆の関心が集中するのは、日本人の国民性かもしれない。
野球で言うなら、かつての読売巨人軍。政治の分野では、幾度と無く窮地に立とうとも必ず盛り返す自民党。自動車は世界のトヨタ。今も昔も圧倒的強者に対して信頼をよせて、安心感を得ると言う図式は不変だ。
これは他人の評価(世論)が気になり、多数派に所属することが大好きで、何かと集団行動をしたがるという典型的な日本人の行動パターンだ。
終身雇用の終焉や地域社会の崩壊が話題となっても、このメジャーな存在が大好きという日本人の性質はDNAにまで染込んでいるのかもしれない。
通常の市場原理がダイナミックに働くなら、安価で良質な商品が揃えば、後は適切な広告さえ行えば、その商品は多量に売れるはずである。
しかし、日本市場は一筋縄ではいかない。他人の評価を第一とするDNAが作用するため、アングロサクソンには理解できない購買行動が起きるのである。
その一例として、かつて“国民機”と呼ばれたパソコンを取り上げよう。
それは、NECが生産していたPC-9801(通称キューハチ)シリーズと呼ばれるマシンの伝説だ。
1990年代初めの頃は、日本でパソコンといえばNECのキューハチのことを指していた。そのシェアは圧倒的で、他社の追従を許さないものだった。それゆえに、キューハチは“国民機”と称号を欲しいままにしていた。
当時のパソコンのCPUは非力で、海外製のパソコンでは漢字等の日本語表示が困難だった。そこでNECは日本語処理を専門に行う漢字ROMという機能を付加し、高速な文字入力を可能とした。
その時点ではキューハチにアドバンテージがあり、パソコンに精通した人は知人にキューハチを勧めるようになり、NECのパソコンのシェアは9割を超えていた。
ブランドに依存する日本人は、キューハチ以外のパソコンには全く関心を示さなかった。(もちろん、その頃からの熱烈なMacファンも存在したが少数派だった。)
しかし、1995年にWindows95が登場する頃になると状況は激変した。
この時期にはパソコンのCPUは飛躍的な性能向上を遂げ、漢字ROMに頼らなくてもWindowsで日本語処理は実用レベルに達するようになった。つまり、漢字ROMを搭載していても、その機能は使わない盲腸のような存在となってしまった。
すると、国際規格(AT互換機)は海外の安価な部品が調達可能となるため、価格面での優位性が明確となった。
実際に欧米ではAT互換機のWindowsマシンが飛ぶように売れ、キューハチは割高だという認識が浸透し始めた。
性能でも価格でも優位性を示せなくなったキューハチは、すぐに売れなくなると思われた。
だが、実際にはWindows95の登場以後も、順調にキューハチは売れ続けた。もちろんNECの価格対応や広告戦略が見事だったこともあるが、これは日本市場独特の現象ともいえよう。(その数年後、NECは緩やかに方針転換を行い、キューハチからAT互換機に切り替えることで見事な生き残りを果たしている。)
そこには、日本人が集団として盲信したブランドは、少々時代遅れになっても、その神通力を失わないという特徴が読取れる。
それほど日本市場は世論やオーソリティーの言動に盲従する傾向がある。
よって、市場に圧倒的勝者が存在する場合は、特に日本市場では同一分野での競合は勝ち目が無い。そのような状況ではサービスの差別化を図り、違う土俵で勝負をかけるべきであろう。その差別化への動機は、浜田省吾の言う“反骨心”であっても構わない。
それが購買行動の二極化に適応していく術だと言えよう。
浜田省吾をテレビで見かける機会は、本当に少ない。歌番組には出演しないし、ドラマやCMのタイアップで曲が流れることも無い。
しかし、1998年から2001年にかけて敢行したON THE ROAD 2001ツアーでは、全国127ヶ所で196の公演を行い60万人を動員した。2000年に発売したベストアルバム「The
History of Shogo Hamada"Since 1975"」は150万枚を売上げ、最近のアルバムもコンスタントに20~30万枚のセールスを記録している。
つまり、売れないからテレビで見かけないのではなく、テレビやラジオといったマス・メディアを、セールスの手段として活用していないのだ。
ミリオン・セールスを記録するようなヒット曲は、ほとんどの場合がドラマやCMのタイアップ曲というのが日本の音楽界の現状だ。こうしたタイアップやテレビの活用無しにアルバムを売ってヒット・チャート上位に入ったり、ライブで1万人収容のアリーナを満杯にするのは驚異的だ。
ここで単純な疑問が生じる。
歌番組やCM等で全く耳にしない曲なのに、どうして売れるのか。更にはライブのチケットは当然のごとく発売即日にSOLD OUTとなるわけだが、これも不思議だ。
一体、浜田省吾のアルバムを買ったり、ライブに参加する人は、どこで浜田省吾の存在を知ったのだろうか?
ライブ会場に行くと、そこに集うファンの年齢層は30代から40代が中心だが、10代や20代も見かける。(もちろん、50代以上のファンもいる。)
10代や20代の年齢層は、比較的最近に浜田省吾を知ったはずだ。しかも、テレビ以外の接点から。
恐らく、親や年の離れた兄弟が浜田省吾ファンであったり、会社の忘年会で上司がカラオケで歌う「J.BOY」や「MONEY」を聞いて興味を持ったとか、そういうきっかけでアルバムを聴くようになったのではないだろうか。
つまり、もの凄く身近な人から影響を受けて浜田省吾の曲を知り、競争率の高いチケットを取るために何度も電話をする苦労を経て、ライブに辿りついたわけだ。
このように親兄弟や友人、恋人からお気に入りの音楽を勧められ、それがお気に入りとなって、気が付けばロングセラーのヒット曲となっていくという様子は、まさに口コミの力であり、最も自然な音楽の波及の姿ではないだろうか。
浜田省吾のファンは、親しい人にアルバムを聴かせたり、ライブの感動を話したりということをマメにしているように思う。
そこには感動を人に伝えたいという単純な動機の他に、テレビでは絶対に知りえない浜田省吾の音楽の良さを、自分が伝播しなくてはという使命感もあるように思う。
「俺が浜省の歌を広めなければ、誰がやるんだ。」
このくらいの心意気のファンも多いだろう。ファンにそこまで支持されるようになれば、口コミ・マーケティングは大成功と言える。
まるでマッキントッシュの熱烈なユーザーが、Macの良さを延々と語りだしてエバンジェリスト(福音伝道者)と称されるように。
遠山の場合は、浜田省吾教のエバンジェリストでありたいと思っているわけだが。
ON THE ROAD 2001ツアーの頃からは、インターネットも普及し、ライブの様子をネット上に逐一報告しあうファンが増えた。
最近では、ブログやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のmixi(※注1)で、ライブの感想を公開するファンが急増している。
余談となるが、遠山がこの本を書くきっかけとなったのが、mixiに公開したライブ参加の感想だった。その日記を見てくれた企画者から、ビジネスや経済学的視点から浜田省吾について書いてみないかとお誘いを頂いたのだ。
(※注1)
ブログとは、簡単な手順で日記形式のホームページを公開するツールで、この普及によってホームページを公開する個人が急増している。
ソーシャル・ネットワーキング・サービスとは、ブログを会員制にしたようなツールで、同好の士によるコミュニティが盛り上がっている。
このように、ファンが勝手に新しいファンを呼んで来るようになれば、放っておいても商品は売れる。この段階に至れば、派手なプロモーションや費用のかかる宣伝・広告は控え目にしても良いわけだ。
通常、消費者が購買行動に至るまでには、様々な心理的障壁が存在する。例えば、ふと耳にした曲を良いと思っても、そのCDを即購入するわけではない。CDショップまで出掛けるのが億劫だったり、ネット予約すら面倒と感じるものである。
ましてや、ライブとなれば繋がらない電話を何回もかけて、予定を調整して会場まで出掛けなくてはならない。
そんなハードルを乗り越えても、「欲しい」と思わせる何かがなければ、結局販売機会を喪失してしまうのだ。
しかし、親しい知人からの口コミという後押しがあった場合、大抵の人は「それなら買ってみようか。アイツが言うなら間違い無いだろうし」と思うわけだ。
この場合は購買行動に結びつきやすい。
一般のビジネスであっても、いろいろと宣伝活動はしているのに、あと一歩のところで購買(契約)まで至らないという現象に悩むことは多いと思う。
売り手側が必死に宣伝すればするほど、皮肉なことにお客は離れていくこともある。これはお客側から見れば、見ず知らずの営業マンが強引に商品を押し付けようとしているという印象を抱いてしまうからだ。
そんな時には、商品やサービスの品質の良さを追求し、既存顧客がリピーターとなり、更には新しい顧客を連れてきてくれるという循環を作り出す努力をすべきだろう。
そのためには、サービスレベルを維持し続け、口コミの評判を上げるに尽きる。一朝一夕に信用は醸成されるものでは無いが、これが出来れば事業は安泰となるはずだ。
ライブの帝王である浜田省吾にとっても、野外ライブは特別なイベントだ。通常のライブ場合は「みんなの街へ行く」という言い方をするが、野外の場合は「遊びに来て欲しい」と語る。
それだけ野外ライブにはファンを接待するような気分が働くらしい。
そんな特別な野外ライブだが、近年では1999年夏に開催している。その時も8年ぶりとなる野外ライブであり、とにかく貴重な機会だった。
この1999年の野外ライブを企画するにあたり、浜田省吾はライブ会場に関していくつかの要望を挙げたという。
それは、まず公園が全面芝生であること。そして、面積のゆとりがあること。(5万人が収容可能な会場に対して、チケットは2~3万枚しか発行しなかった。)
更にはトイレ・売店・駐車場が充分に用意できること。
これらの条件を満たす会場は意外と見つからず、スタッフは懸命に全国の公園をリサーチしたそうだ。
そして、最終的には北海道のキロロリゾート、広島の備北丘陵公園、東京の昭和記念公園が選ばれた。
全面芝や面積的なゆとりについては、恋人や家族と一緒に来て、ゆったりと座ったり寝転がったりできるようにしたいとの思いだったそうだ。
トイレについては、とにかく数を充実して、トイレ待ちの間に演奏が数曲終わってしまうような事態にならないような配慮だ。売店はアルコールを買ったり、子供が退屈しないように。駐車場に関しては、家族連れが余裕を持って行動できるようにとの狙いだ。
これらは屋外でイベントをする際には常識だと思えるが、このように行き届いたライブは少ないのが実情だ。
何よりも、野外ライブは経費も莫大となるため、会場のキャパシティの限界までチケットを発行するのが常識化している。そのため、会場はスシ詰めとなり、トイレで30分待ちとなったり、迷子や行方不明の遭難者が溢れることも珍しくない。
にも関わらず、ファンがゆとりをもって参加できる条件整備を第一に考えるのはサスガだ。
ミュージシャン自身がこのような細かい配慮をするのは、本当に素晴らしい。だが、浜田省吾のこだわりは、もっとスゴイところにあった。
それは野外ライブについては「雨天順延」というコンセプトにしたことだ。
野外イベントで雨天順延というのは、ある意味当たり前のことかもしれない。しかし、順延というからには予備日を用意する必要がある。野外ライブには大型スクリーンや照明、動力装置そして大勢のスタッフの人件費など、とんでもないコストがかかる。
それを予備日の分まで確保すると、単純計算で経費は2倍となってしまう。
恐らく、最初に「雨天順延」というコンセプトを聞いたステージ責任者は、顔面蒼白になったに違いない。ひょっとしたら、卒倒してしまったかもしれない。とにかく、運営者にとってはそのくらい過酷な条件なのだ。
とにかくビジネスに徹して利益を追求するなら、会場はスシ詰めにして「雨天決行」にするべきなのだ。経費を1日分に抑えて、チケットを多量に売りさばけば、儲かって仕方が無いはずだ。
そうした野外ライブのあり方について、浜田省吾は次のように語っている。
「 音楽ビジネスという面から考えれば、雨天でもコンサートは決行すべきなんでしょうね。でも、それは、目先のビジネスで、その場で損をしないだけなんですよ。野外コンサートについての業界の常識に対して、アンチ・テーゼを示したかったんです。そして、口で言うだけでなく、実際にそれを実行し、こうしたやりかたでも成功を収めることができるということを証明したかった。ぼくは、これは小さな種にすぎないかもしれないけれど、必ず実を結ぶとおもっています。」(アサヒグラフ 1999年9月24日号より)
つまり、雨天決行のような目先のビジネスでは、観客に酷な思いをさせることになってしまう。土砂降りの中で風邪をこじらせて肺炎にでもなれば、そのファンにとってはマイナスの意味で伝説のライブになってしまうだろう。
すると、その観客は二度と野外ライブには行こうとは思わなくなる。そのようなファン無視のライブはできないというのが浜田省吾の配慮なわけだ。
それでも、ライブで赤字を出すわけにはいかない。このようなファンに優しい野外ライブを行いつつも利益は出す。その実績によって、他のミュージシャンもファン優先の野外ライブのモデル例として考えるようになる。
浜田省吾は、そこまでの大局的視点で行動したそうだ。そこにはライブの先駆者としての誇りと自覚が垣間見える。
世の中には経済効率ばかり追求して、顧客の立場を見失う事例はいろいろとある。例えば、2005年のJR福知山線の列車事故は、過密ダイヤで運転士を追い込むあまり起きてしまった可能性が取り沙汰されている。
他社との競争や効率に焦るあまり、最も大切な安全性が損なわれてしまった。
目先の利益や効率ばかり追っていると、人は近眼的行動しか取れなくなっていく。その結果、事故でも起こして顧客からソッポを向かれては元も子もない。
自分が関わる事業にとって、本質的な顧客サービスとは何か。その問いかけを忘れてはいけないだろう。
現在の日本経済市場は成熟して、なかなか新規参入のチャンスは無いように思える。ごく一部のIT関連企業が急成長をしているが、ライブドアの偽計取引や粉飾決算事件、光通信株の大暴落をなどの現象を見るにつけ、どことなく胡散臭く頼り気がない。
マスコミは高感度の高い女優を使って大企業のCMを垂れ流し、消費者はそうして刷り込まれたブランド・イメージを信奉して、ヒット商品に群がる。
結果として、大企業が提供するメガ・ヒット商品は誕生するが、新規起業者がそのようなサクセス・ストーリーにあやかる可能性はゼロに等しい。
音楽業界でもテレビを中心としたマスメディアの影響力は大きく、そこに利権が発生する。とにかくテレビに関わる人々の意向に従わないと、ミュージシャンが楽曲をリスナーに知ってもらうことができないのだ。
そんな現在の音楽業界事情を、浜田省吾は次のように語っている。
「 シングル(CD)を売るというシステムがどういうものであるかっていうのは-ユーザーの人は知る必要もないことなのかもしれないけど、いかに露出していくかと。そして、その中で最も力を持ってるものはダントツにテレビであると。テレビの中で最もたくさん露出するものはドラマの主題歌であったりCMであったりするわけですけど、当然そこからたくさんのヒット曲が出てそれがたくさんのお金を生んでるがために、ガッチリとしたシステムがもうでき上がってるんですよね。具体的にじゃあこの楽曲の何%、この楽曲が入ってるアルバムの何曲分の著作権をどういうふうに分配しろ、しなければ使わない-もうそういうところなんですよ。だから、ものすごくいい作品だからシングル盤として世の中に露出して、それがメガヒットになっていくというような時代ではもうないんですよね。」(BRIDGE 2001年10月号より)
何という世知辛さだろうか。ファンはCMやドラマでも、もっと浜田省吾の曲を聴きたいと願っても、それには多額の宣伝費用をテレビ関連の各所に上納しなくてはならず、巨大プロダクションに所属しているわけでもない浜田省吾にとっては、その負担を背負えないという状況なのだ。
世の中はカネと利権でよどんでいると嘆きたくもなるではないか。
これはテレビという既存マスコミを通した場合の話だ。そのテレビが創り出すメガ・ヒットには上位集中という特徴がある。それは売れる曲は爆発的に売れるのだが、そんなメガ・ヒット曲数は年間ではそれほど多くない。
一方、ほどほどに売れる曲というのは減少して、圧倒的多数の売れない曲の骸が荒野に転がっている惨状だ。
何か少し前の戦力集中を図った読売巨人軍とプロ野球の関係のようではないか。
実はこのような圧倒的な上位層とうだつの上がらない下位層に二極分化するのは珍しい現象ではない。
ビジネスの現場でQCサークル活動なんかに取り組まれる方ならご存知だろうが、諸々の売上をパレート図とかABC-Z分析という手法で解析すると、成熟した市場は少数の勝ち組とその他大勢の負け組みに分化してしまう。
飲食店で物を売るにも、人気メニューは集中していて、売れない商品は全く売れないものだ。
だからと言って、売れない商品が粗悪品かといえば、そんなことは無い。単に陽の目を見ないだけだ。
そんな売れない組のやるせなさに、かすかな光を与えるのがインターネットだ。インターネットの可能性を雄弁に示す事例として、アマゾンの書籍販売がある。
書籍も音楽業界と同様で、ベストセラーとその他大勢という売上構成が出来上がっている。そのため、取次を経由した一般書店では、ベストセラー本しか置かれないという現象が起きている。
マイナーな書籍であれば、ほとんど店頭で見かけることはなく、注文しなければ入手はできない。当然ながら、そんな本は売れない。
しかし、アマゾンはインターネット上で無店舗販売をしているため、在庫リスクを考える必要がない。そのため、マイナーな本でも取扱をする。
すると消費者は、店頭では見かけない本を検索で見つける喜びを知り、これを積極的に活用するようになった。結果として、アマゾンでは売上の三分の一を非ベストセラーで占めるという快挙を成し遂げた。
ここに成熟市場でも挑戦者が切り込んでいける道筋が示されたと言えよう。
浜田省吾も意識しているかどうかは不明だが、わりとインターネットの活用には積極的だ。ROAD&SKYやSONYミュージックの公式ホームページでは、ビデオクリップ視聴やファンに向けたメッセージを提供している。
携帯電話向けのコンテンツとして、着うた配信にも積極的だ。更にはsuicaによる日本初の電子ポスター予約や、ConnectedDを活用したCD購入者に対するファン・サービスも実施している。
2005年には新曲「I AM A FARTHER」の発売にちなんでYAHOOとタイアップしてブログを公開したりもした。
インターネットは現段階では既存マスコミの影響力が小さく、検索エンジンとの親和性が良ければ、不特定多数のエンドユーザーに直接働きかけることが可能となる。
テレビを利用しないで、そんな芸当ができるのは、インターネットくらいだろう。これを活用しない手は無い。
そんなわけで、テレビに振り向いて貰えない起業家達は、こぞってインターネットを利用する。僕自身もそんな一人だ。(浜田省吾はテレビに振り向いて貰えないのではなく、自らの意思でテレビ出演を拒否しているのだから、事情はことなることはお断りしておく。)
成熟市場の閉塞感を切り崩すツールとしてインターネットを活用すれば、まだまだ面白いことはできそうだ。
かつて浜田省吾は日本の音楽業界では非主流の存在だった。いわゆるニューミュージックというジャンルの音楽は、大量のCMやプロモーションを前提として、広告や宣伝活動の物量作戦によってセールスをするのが常識化していると言えよう。
ドラマ・アニメ・映画・CMとタイアップして作り込みをされた曲が、ヒット曲となるのが一般的現象となっている。
また、こうしたタイアップにはテレビというメディアの存在が不可分であり、それだけにミュージシャンは歌番組への出演には積極的となる。
つまり、テレビ抜きには日本の音楽セールスは始まらないというわけだ。
そのテレビに出ないということは、従来の音楽マーケティング活動では自殺行為に等しいとも言えよう。
無論、浜田省吾も初期の頃はテレビやラジオというメディアへの出演や、テレビCMとのタイアップをして、(当時は)EP・LPレコードの販売促進活動にチャレンジをしていた。
遠山はリアルタイムで観た記憶は無いが、「ヤング オー オー」に出演したり、日清のカップラーメンのCMに「風を感じて」が使用されたらしい。
また、浜田省吾は「デビューから5枚目のアルバムまでは廃盤にして欲しい」と冗談で語っている。その主な理由として、初期の頃は音楽の方向性が定まらず、周囲のアドバイスに従って“売るための”音楽であるポップス系を作っていたと述べている。混迷が深まって他人に作詞をしてもらったりもした。
しかし、思うように売れずに、「それなら、(本心に従って)もっとハード・ロックをやりたい」と思うようになったという。
その時点で大きな思い切りがあったのだろう。6枚目のアルバム「Home Bound」(1980年発売)では「終わりなき疾走」を始めとするロック基調の曲が増え、この年に初めて年間のライブ数が100を超えた。
現在の浜田省吾のモデル・パターンは、この時期に形成されたと言ってよいだろう。そして、この戦略は当たり浜田省吾は“ロック・スター”“ライブの帝王”の称号を得るようになっていった。
ちょと見方を変えれば、テレビではポップス系の曲がもてはやされていて、音楽業界の主戦場はポップスの過熱で消耗戦に突入していたとも分析ができる。
その主戦場を回避し、ハード・ロックをしかもライブ中心でPRするという戦略に切り替えたとも言えないだろうか。
つまり、経済的にも精神的にも消耗・疲弊が強いられるテレビ=ポップスを敬遠し、日本では未開拓だったライブ=ロックという分野に特化していったということだ。
このような競合を避け、専門分野に特化(セグメント化)していく手法を、経済理論では“ランチェスター戦略”という。
ランチェスター戦略とは、第一次世界大戦時にイギリスのエンジニアであったF.W.ランチャスターが考案した戦争の法則で、第二次世界大戦後は企業の経済戦略理論として応用され現在に至っている。
ランチェスター理論の要点について、挑戦者側から見た場合は以下の通りである。
「大局での競合(消耗戦)の回避」
「差別化(セグメント化)した局所で戦う」
「局所に経営資源を一点集中し圧倒的勝利をする(カテゴリー・キラー)」
大局での競合を回避するというのは、資本力や販売力で劣る立場にある挑戦者は、既にディファクト・スタンダート(事実上の標準)を確立している勝者が存在する市場には参入しないということだ。
トヨタやGMと真っ向勝負をして、大衆車の製造メーカーを起業すると言う人はいないだろう。もし、いたとしても銀行は1円も融資してくれまい。
しかし、大衆車ではなくニッチな分野の極めて趣味的な車を作るなら、ごく僅かな希望はあるかもしれない。
差別化した局所というのは、巨大な販売網を持った会社でも、苦手な分野は存在するものだ。その大手が扱わない市場に狙いをつけることだ。
イトーヨーカドーやイオンの隣地で物販の店舗を構えるのは厳しいが、これら巨大スーパーでは売り場面積の少ない商品に目をつけ、そのジャンルに特化した店作りをすれば勝算は生まれる。
例えば、隣接する巨大スーパーが100坪の衣料品の売り場面積を有していたなら、50坪の紳士服専門店を作る。店舗面積が20坪しかなければ、更に「大きいサイズ」に特化する。このような工夫が差別化といえよう。
局所に経営資源を一点集中とは、差別化した事業を片手間でやっていてはいけないということだ。片手間の仕事では、消費者の要求するクオリティーは満たせない。
差別化すると決めた事業(市場)に対して、経営資源や人材を全力投球することだ。そうしないと、新興市場に目をつけた大手が後から参入してきた時に太刀打ちできなくなってしまう。
かつて世界のパソコンメーカーといえば、それはIBMのことを指した。しかし、汎用コンピュータ(パソコン)に特化したコンパックの台頭を許し、その後は通販やインターネット直売に特化したDELLが販売台数を凌駕している。
そして、当のIBMはパソコン事業では利益を出せなくなり、その事業を中国企業に売却した。これも、DELLが販売店を通さない通販という事業に全力投球したからだ。DELLが既存販売網の圧力に屈してダイレクト販売を止めていたら、現在のシェアは無かっただろう。
浜田省吾もロックとライブという差別化を図り、その分野での先駆者となった。そして、商業的にも成功を収め、既存メディアからも一目置かれる存在=カリスマに昇華したといえよう。
新しく事業を始める場合は、ほとんど誰もが挑戦者という立場に置かれる。その際には、既存市場との差別化や一点集中という戦略が有効となるのだ。
モノ余りの時代では、どんな事業でもマーケティングが重要となる。物資の乏しい地域であれば、少々の粗悪品であっても、安価に大量供給できれば飛ぶように売れる。
しかし、成熟した経済環境下では、そんな商品やサービスは受け入れられない。
いかに現代のマーケティングが難しいかという好例に、1996年に大ブームとなった「たまごっち」がある。携帯玩具の先駆けとも言える商品で、子供だけでなくOLも夢中になってバーチャルなヒヨコを無機質な液晶の中で飼育していた。
これが発売から大ヒットなって、店頭では山のようなバック・オーダーを抱えた。製造元のバンダイも、そこまで売れることを予測していなかった。
そこで慌てて「たまごっち」の大増産をしたのだが、潤沢に商品が店頭に並ぶ頃にはブームは去ってしまった。バンダイは不良在庫を抱えることになってしまったのだ。
つまり、二重にマーケティングの判断を誤ったことになる。当時の担当者には同情するばかりである。(2005年から小学生にたまごっちのリバイバル・ブームが起きている事も補足しておこう。)
このように、マーケティングの予測や判断は、非常にシビアで難しいものと言えよう。そこには、いつも様々な資料やデータを検討した上でも、迷いや不安がつきまとう。
その点、浜田省吾は最大のファン・サービスはライブであると位置づけ、過去この方針は決してブレたことがない。
なにしろライブ・ツアーを敢行するには、バンドや舞台装置等の裏方を引き連れて全国を移動する必要があるのだ。大勢のスタッフを動員するからには、当然ながら経費も膨大。そのためミュージシャンにとって、ライブの経費は負担であり、利益性は決して良いとは言えたもんじゃない。
というか、単に利益を追求するなら、ライブは行わず、CDのみを多量にセールスすることを考えた方が効率はいい。言うまでもないが、ライブは極力行わず、テレビ出演でCDの宣伝を繰り返し、CDセールスを重視するミュージシャンも少なくない。
あえて名前は出さないが、そうやって多くのミュージャンは人気を獲得し、ファン層を開拓し、安定したところで、ツアーに出る。
ところが、浜田省吾はそんな音楽業界では異色とも思えるスタイルを貫いている。
ライブ優先だ。
しかもテレビ出演やコマーシャルやドラマとのタイアップはほとんど行わず、プロモーションもむしろ控え目。
売る気がないと思えるほどである。
にもかかわらず、採算性が低いライブを精力的に展開し、チケットは即日完売。しかもファンの間では、そのライブは年々進化していると評価も高い。つまり、驚くことにソロデビューから30年を経過しても、更にライブの質は向上しているのだ。
残念ながら、これはライブ経験者にしか分からないが、そのブレない姿勢は圧倒的なメッセージになっている。
結果として、この質の高いライブを提供し続けることで、CDアルバムも安定的にセールスを計上。つまり、浜田省吾はファンが喜ぶことを第一に考えて行動し、その上でプロモーターとして、採算性も両立させる手腕を発揮しているのである。
ちょっと考えれば、テレビ出演やコマーシャルやドラマとのタイアップも、重要なファン・サービスであり、それを期待する需要も大きいのではないか。そういう疑問もあると思う。
これに関して、浜田省吾は「青空のゆくえ」(ロッキングオン出版・渋谷陽一著)で次のように言っている。
「これは凄くいい音楽か?っていうよりも、これはブレイクするか?これは凄く売れるか?っていうところで音楽の話をしてる。(中略)例えば音楽がテレビの付属品のようになってしまったこととか、そこからしかメガヒットが生まれなくなってしまったこととか、もちろんそのビジネスの仕方ね、タイアップの仕方とか(中略)あまり僕には健全に映らないんですよね。」
これには音楽に対する浜田省吾のこだわりが垣間見える。
つまり、音楽の提供が自らの職業的使命だと認識し、何の制約も受けずに楽曲を作りたい。そのためには、制限の多いテレビとのタイアップは避け、ダイレクトにファンに楽曲の良さを感じて貰いたいと考えているのだろう。
だから、浜田省吾の歌を聴く事を楽しみにしているファンの目前で、力の限りアピールできるライブを重視しているように思う。
結果として、この姿勢はファンに支持され、熱烈なライブへのリピーターを生み出している。
マーケティングとは、とても繊細で予測が難しいものであることは前述した。多くのビジネスマンは、それを知っているからこそ、時としてマーケットに迎合したりする。
それは、顧客像を過剰に意識して、生産者のポリシーを曲げたりするという弊害となることもあるだろう。
生産側の意向と顧客需要のすり合わせが、マーケティング活動とも言えるが、企画者が自己のポリシーを押し通す勇気も必要と言えよう。
浜田省吾がソロデビューをした1976年の時点では、日本ではロックやR&Bというジャンルの音楽は産声をあげたばかりだった。そのため、この分野でのセールス手法は確立されておらず、何もかもが手探りだった。
前例やマニュアルの類が無いというのは、ホントに辛いものだ。突然にジャングルへ放り出され、「今日からここで生きてゆけ」と宣告されるに等しい。
浜田省吾自身も、好きな音楽をやっていける嬉しさはあっただろうが、不安の方が大きかったかもしれない。その心境を次のように語っている。
「 我々の時代は、ロックシーンというものがまだなかったですから、10年後を全く想像できなかったんですよ。自分はどうなっているんだか分からない。でも、とりあえず好きなことだし、これで食えているからハッピーだねという気持ちと、世の中はオイルショックで不況で就職口もあまりないし、これで成功しなかったらどうしようみたいなのと、両方あったと思いますね。ただ、何もなかったからこそ、自分で選んだ道だからという納得もありましたね。俺が選んだ道なんだという。そこは今の子たち(現在の若手ミュージシャン)と(置かれている環境が)違うかもしれない。今はシステムがしっかりと出来ていて、これとこれを組み合わせるとどうなるかとか、タイアップはしっかりとって、プロモーションはこの番組に出て、みたいなことをすでにアマチュアのミュージシャンも知っていますよね。それが良いことか悪いことかは分からないですね。」(J-POP MAGAZINE 2005年9月号より)
やはり、浜田省吾といえども、成功しなかったらどうやって食っていこうかという不安を抱いていたようだ。
1980年代以降は音楽市場が膨れ上がり、ミリオンセラーも狙えるビック・ビジネスとなった。しかし、それ以前はロックで生計が成り立つものかどうかというレベルの疑問もあったのだろう。
そんな状況の中で、現在では考えられないことだが、浜田省吾もCMソングを作ったりテレビの歌番組に出演したりと、必死のプロモーションをしていたわけだ。
しかし、ポップミュージックのセオリー通りにプロモーションをしても、結果として売れなかった。そこで、ある種の開き直りもあって、自分が大好きなバリバリのロックを作り、それをひたすらライブで披露するという形で活路を見出すことになっていった。
そこから過去と現在の対比として、フロンティア精神とシステムの確立という特徴が分析できるだろう。
過去においては、ほとんどの場合で前例はなく、何もかも自分達で切り開いていかなくてはならなかった。いわゆる開拓者精神(フロンティア・スピリッツ)だ。
とにかくルールと呼べるものすら未整備で、全てが自己責任だ。失敗することの方が多いだろう。
そのようなリスクは大きいが、逆に自由な気ままさもあったはずだ。何もかもが自分の裁量次第とも言える。そういう面では、失敗した場合も納得はできた。
一方、現在は何もかもが整備されて、いろいろな販売手法は確立している。目標やチェックポイントは明確で、マニュアル通りに行動をすれば大きく間違うことは無い。
マーケティング活動においても、事前に売上の予測はできてしまう。コンビニの弁当売上予測等は神業かと思ってしまう。とにかく作業に無駄をなくし、効率の向上が何よりも美徳とされる。このように販売システムは確立された。
だが、この効率を極限まで追求すると、何もかもがマニュアル化された画一的なサービスしか提供されなくなる。マンネリってやつだ。そこには個人の思い入れや新しいアイディアが排除されてしまい、不満を抱えて仕事を続けるケースも生じる。
浜田省吾も名曲J.BOYで「打ち砕け日常(マンネリ)ってやつを」と絶叫しているのだが・・・。
また、ある商品のマーケティング手法が確立されてくると、昔は全工程を少人数で行っていた作業が分業化する。
すると、細分化された作業を任された人は、その分野のスペシャリストとなる。このスペシャリストが自分の作業範囲内でしか物事を考えなくなると、そこには深刻な組織的弊害が生まれる。いわゆるセクショナリズム、お役所仕事だ。
いくら販売システムが優れていようとも、その内部でお役所仕事が蔓延すると、そのシステムは悪性の癌に侵されたような状態となってしまう。
このようなマンネリを打ち砕くため、浜田省吾はライブ・ツアーにこだわる。
「 シンガー&ソングライターというのは、自分が作った歌を自ら歌うわけで・・・。ステージで歌わなければその歌はオールディーズになって行くしかないんですよね。自分の作った歌をコンサートで、自分で歌うことで今の歌になるんですよ。そして、聴いてくれた人がそれを良い歌だと思ってくれれば、それは生き残った歌であり、生き残って行く歌なんですよね。」(J-POP MAGAZINE 2005年9月号より)
つまり、ソングライター(作り手)としても、シンガー(表現者)としても、現役であることにこだわっていると言えよう。単に曲作りをしていくだけではなく、それをエンドユーザーであるファンの前で演奏しようと務めている。
そこには分業化が進んだ音楽業界の中にあっても、できるだけファンの顔を見ようとする真摯な姿勢が感じ取れないだろうか。
翻って自分の仕事を考えたとき、調査・開発から製造を経て販売に至るまで、全工程を把握してエンドユーザーの要望を知ろうとしているかが問われる。
分業された作業だけに埋没していると、仕事への意欲も減退するものだ。
既に確立されたシステムに乗っかっていたとしても、エンドユーザーの喜ぶ顔をイメージし、全工程を把握する気概は持つべきだろう。
浜田省吾のライブでは、休憩時間にもサービス心が旺盛だ。ライブの中間で10分程度の休憩があるのだが、この時間に観客が退屈しないようにステージ上のスクリーンにはオリジナル映像を流してくれる。
その映像はショートストーリーになっていて、浜田省吾が主演するというレアものだ。これを見逃すのはもったいないと思い、ついついトイレに行きそびれたファンも多いだろう。
ON THE ROAD 2001ツアーでは、「ミッドナイト・キャブ」と「マリア」というタイトルのショートストーリーを披露した。
「ミッドナイト・キャブ」は浜田省吾が扮するニューヨークのタクシー運転手に、様々な乗客がその人生模様を語りかける。無邪気な不良少年たちの武勇伝、娼婦風の女性が恋人に客の暴行を嘆く、東洋人(日本人?)が株の暴落に断末魔の悲鳴をあげる、寡黙な老紳士が大切な人の死を語る。このように乗客の人生観を、寡黙な運転手の浜田省吾がただ頷いて聞いている場面が印象的だった。
「マリア」は大農場でメキシコ人労働者が農作業をする様子が映されていたが、その中に浜田省吾が混ざって農夫役をしているのを見つけると、会場から笑いが起こった。やはり農作業中でもサングラスは外さないのだ。
そんな農作業後の歓談の際に、浜田農夫と地元の美少女のマリアが世界観や職業観を型ってしみじみと聞かせる。
この「ミッドナイト・キャブ」も「マリア」もテーマは「働く」ということだそうだ。そういえば浜田省吾の曲には「ビジネス」や「仕事」について触れる歌詞が多い。ロックにしろR&Bにしろ、流行歌のテーマはほとんどが「恋愛」というのが主流だが、そういう面でも異色といえるだろう。
もちろん、浜田省吾もラブソングはたくさん作っているし、その評価も高い。でも、人間は四六時中恋愛だけを考えて生きているわけではない。働き盛りのビジネスマンが音楽CDを買わない現象というのは、案外恋愛漬けの流行歌に食傷気味になっている事情もあるのではないか。もう学生ではないんだし、愛だ恋だと浮かれている気分じゃないっていうのも本音だろう。
遠山自身の感性が人と違っているところがあるのかもしれないが、はるか昔の高校生の頃からラブソングしか入っていないアルバムに違和感を持っていた。いいラブソングは確かに好きだが、歌の全てが恋愛一色だと「あんたの頭の中は恋愛しかないのか?」と毒づいていたものだ。何か無理に恋愛を強制する“恋愛押し売りソング”が氾濫しているようで、流行歌を聴きたいとは思えなくなっていった。
そんな偏屈な少年時代を過ごしていたが、大学に入学した年に浜田省吾のアルバム「J.BOY」を聴いて衝撃が走った。
何とアルバムの1曲目から「A NEWSTYLE WAR」なんていう反戦歌が入っている。「J.BOY」では過労死が社会問題になる中で、仕事におぼれるビジネスマンの心境を吐露している。その他にも父親の人生観やアルバイトで苦学する歌など、生活に密着して共感を得る曲が多かった。
ラブソングも「19のままさ」や「遠くへ」などは、将来の不安を抱えて吹けば飛ぶような存在の自分の境遇に一致した。
その時以来、浜田省吾が「通りのウィンドーに飾ってあったギターを見たとき」並みの稲妻が体を駆け抜けて、彼がリリースする曲は必ずチェックするようになった。
そんな浜田省吾が「仕事」について語った記事がある。
「 仕事っていうのは、ただ、お金をもらって生活するためだけのものだったら、どこか寂しい気がするんですね。人は社会的な生き物ですから、仕事をすることによって、社会の中のつながりとか誰か人のためになっているとか、そういう存在価値みたいなものを見出せたらすごく幸せだと思うんです。」(日経エンタテイメント 1999年12月号より)
納得である。現代社会は物の生産や流通が高度化して、仕事の内容が分業化・細分化されている。
例えば、工場の中で精密回路のハンダ付けの作業を任された場合、それ以外の仕事が見えないわけだから、自分のやっていることが社会のどこで役に立っているか認識できない。
そこで「お客様のために貢献しろ」とか「仕事に誇りを持て」と言われても、それは虚しいスローガンとして耳の左から右へ抜けていくだけだろう。
逆に消費の場面でも同様だ。今晩の夕食の刺身について、その生産や流通過程に携わる人々の苦労にどれだけ意識はいくのだろうか。
魚が切り身になるまでは、養殖業者の手で何ヶ月も世話をされた魚が水揚げされ、鮮度が落ちないうちにトラックで運ばれ、加工センターで切り身にされる。その後、店頭に並ぶわけだ。その間では熾烈な価格交渉があって、そこでストレスを抱える人もいるはずだ。
笑い話で、小学生に魚の絵を描かせると、切り身が泳いでいる絵を描いたという話がある。それほどまでに現代人は、かつては自らの手で行っていた工程の一部しか見ることができず近眼になっている。
そんな断片的な日常を繰り返していると、自分が社会の中でどのような役割を担っているかを感じ取るのが難しくなる。
浜田省吾も語るように、社会とのつながりを認識しないことには、人間は孤独や疎外感から開放されることはない。面倒に思える作業になるかもしれないが、自分のやっている仕事が何の役に立っているのかを調べ、その全工程や全体像を把握する努力を行い、それを家族と語って確認することが幸せにつながるのかもしれない。
ビジネスの現場では、何かと二者択一とか三者択一の選択を迫られる場面が多い。そんなときに、デジタル的にスパッと即決できることもあれば、双方の折衷案を模索することもあるだろう。
そんなギリギリまで方向性に悩む案件に対しては、浜田省吾はどのようなアプローチをしているのだろうか。
「 長く音楽をやってる人間の難しいところでもあるんですけど、ずっと僕の音楽を聴いてくれているファンと、ポップスを旬のものとして聴いている幅広いリスナーとの接点をどう持てるかかのバランスですよね。例えば、今だと宇多田ヒカルさんとかラルク・アン・シエルとかGLAY、椎名林檎さんとか-ポップスのリスナーって、そういう人たちの曲を聴いている人だと思ってますから。
もし僕が今、真っ白な新人としてデビューするとしたらどうするかということと、今までやってきたことにのっかって、これまでのリスナーだけを想定してつくること。僕は、そのどちらかに偏るのは嫌なんです。」(日経エンタテイメント 2000年5月号より)
やはり自らの音楽活動に関する重要な方向性に関しては、バランス感覚を大事にしたいということだろう。古くからのファンの要望にも応えたいし、流行を追うリスナーの感性にも合う曲もつくりたい。その両方のバランスをとりながら、アルバム制作やライブの選曲に工夫をしているはずだ。
このバランス感覚はビジネスのあらゆる局面でも求められるのではないだろうか。
例えば、究極的なテーマとしてサービスの質の向上とコスト削減の問題がある。このサービスとコストの関係は対立することも多い。
サービス向上とコスト削減、その片方のみを追求すると事業は傾いてしまう。
ありがちな話だが、脱サラをして喫茶店やペンションを経営したいという人も多いだろう。そして、いざ夢がかなって開業することになり、気合が入りすぎることになる。
とにかくお客様第一だからということで、出血サービスをしてしまう。減価償却も何も考えずに、夢の城に資金を投じて料金は良心価格に設定。その結果、赤字を垂れ流すことになり、「儲からない」と嘆くようになる。これでは経営とは言えない。
逆に、ローコストの過剰追求も悲劇を呼ぶ。品質や安全性を犠牲にしてまでコスト削減を極めた結果、マンションの耐震強度偽装問題を引き起こし破産した会社もある。この問題では、単に事業者が破産しただけでなく、多数のマンション住民を絶望の淵に追い込んでしまった。その責任は大きい。
やはり、物事には限度があるということだろう。サービス向上もコスト削減も、その片方だけを見て突き進むとロクなことにならない。
かといって、サービスも価格も中途半端な状態では、シビアな日本の消費者には見向きもされない。サービスはイマイチ、それで価格はどうかと言えばこれもイマイチ。そんな事業者の気の迷いが伝わるようなモノは売れるはずがない。
そこで顧客に支持されるには、高いレベルでサービスと価格のバランスをとることが求められる。サービスの質はできるだけ高く、コストは常識の範囲内で可能な限り抑える。それはとても苦労する作業だが、その過程を経て顧客の満足度は高くなる。
そんなバランス感覚を大事にする浜田省吾だが、今までに蓄積してきた楽曲とファンからの評価だけでは満足していないようだ。
常に新しいモノや時代の流行にも無関心ではない。
2000年4月に新曲「・・・to be “kissin you”」を発表した際には、ファンの間でもその斬新さが話題となった。
この曲のプロモーションビデオはアメリカで撮影され、ミュージシャンは現地で探したそうだ。その現地のベーシストは「日本の音楽はアメリカに比べて10年遅れていると思ってたけど、これはカッコいいじゃん。やらせてよ」と言ったという。(日経エンタテイメント 2000年5月号より)
本音で物を言い、自分が良いとは思えない音楽に関与するのは拒む職人肌のミュージシャンからも、曲の斬新性や独創性を認められている。
これは従来までの成功パターンに安住しない、創作に対して貪欲な姿勢を示している。
遠山が取り組んでいる商業ホームページの分野も、変化が激しい激戦区だ。何か目新しいホームページができると、その1ヵ月後には競合ジャンルのホームページがガンガンと出現する。
あまりに同一ジャンルのホームページが増殖していくので、数ヶ月でそのホームページが持っていた斬新性は損なわれるありさまだ。
何か新しいサービスを開発したとしても、それが目新しく思える賞味期間は短い。そんな過激な競合が起きる現場では、絶えず改良や新ネタの披露が求められる。新しいネタを探してあれこれ考える期間は、本当に苦しいものだ。
この改良や改善という発想は、何も音楽業界やIT業界だけに限った話ではない。製造業からサービス業まで、全ての業種で求められている。
過去の実績に満足してしまえば、事業の成長はそこで終わってしまう。そういった実績を大事にしながら、更に新しい工夫を積み重ねていくバランス感覚を持つことが必要だ。
浜田省吾は、2006年4月現在で53歳だ。ソロデビューから30周年だから、その位の年齢になるのは仕方が無い。
(でも、ステージ上では20歳は若く見えるから羨ましい。)
世間一般では50歳を超えた熟年世代は、ITやインターネットは苦手という先入観がある。
しかし、浜田省吾はITやネットの活用には積極的だ。
ROAD&SKYやSONYミュージックの公式ホームページでは、ビデオクリップ視聴やファンに向けたメッセージを提供している。
携帯電話向けのコンテンツとして、着うた配信にも積極的だ。更にはsuicaによる日本初の電子ポスター予約(※注1)や、ConnectedD(※注2)を活用したCD購入者に対するファン・サービスも実施している。
ディープなところでは、2002年の日韓共催ワールドカップ限定版「J・BOY」をネット配信した実績もある。
(※注1)
suicaとは、JR東日本が首都圏で発売している定期券・プリペイドカード。非接触式のICカードのため、改札通過の際にsuicaを財布から取り出す必要が無い。
suica電子ポスターとは、「東京駅」「上野駅」「品川駅」に設置された駅ポスターに、suicaをかざすことでCD予約ができるサービスのこと。
(※注2)
ConnectedD(コネクテッド)とは、特定の音楽CDを所有した購買者が、会員限定のホームページのコンテンツにアクセスしたり、壁紙やスクリーンセーバーをダウンロードできるサービスのこと。
コネクテッドの付加により、ファンは特典を受けられ、CD制作者はCDの販売促進を図ることができる。
従来型のマーケティング手法で成功を収めた人は、ITやネットの活用を軽視しがちだが、浜田省吾に関しては新しい情報ツールを先取りしていると言えよう。
浜田省吾がドラマやコマーシャルとのタイアップには消極的で、テレビには一歩距離を置いて付き合って来たことは、他の章でも述べた。
なぜなら、これらのタイアップには先にイメージが決められており、あまりに制約が多いため自由な曲作りができないのだ。
これはテレビという巨大メディアについては、スポンサーや広告会社の意向など、多くの調整を必要とするため、気軽には利用できないという事情がある。
もちろん、テレビを利用した場合の広告費が高くつくという要素も見逃せない。
また、テレビの特性として、無差別多量に情報提供はできるが、人々の記憶に残るのは一瞬である。長期的にテレビで広告を継続するには、莫大な費用がかかってしまう。
また、多量にテレビで広告活動をしても、全ての視聴者が関心を示す訳ではない。
これに対して、新しい情報メディアであるインターネットについては、ある面ではテレビと逆の特性を持っている。
つまり、例えばホームページで広告を行った場合、ホームページへの訪問者数はテレビ視聴者数と比較すればごく僅かだ。しかし、ホームページへの訪問者は、ほとんどがそのホームページの内容に関心がある層だと言える。浜田省吾も、この点には注目しているのでは無いだろうか。
ホームページを運営する費用も、現在のところはそれほど高額にはならない。よって、ランニング・コストが低いため、長期間の継続的な情報提供も可能だ。コアなファンは、いつまでもホームページを訪問してくれる。
極論すれば、テレビはムダ撃ちも多い広告の絨毯爆撃であり、インターネットは最新のピンポイント爆撃であると言えよう。
現在はテレビ視聴者人口の方が圧倒的に多いのだが、今後ネット人口の増加に伴い、広告手法は劇的に変化する可能性を予見させる。
私的話題で恐縮だが、遠山は岐阜県の人口が4,000人に満たない山間部で生活をしている。現在の職業は行政書士だが、これもマイナーな仕事だ。その業務内容を知る人も多くは無いだろう。
過疎地域で、しかもマイナーな仕事をしていて、生活は成り立つのだろうか。知人や同業者からも同様の質問をよく受ける。
実は遠山がこのような環境でも生計が立てられるのは、インターネットの恩恵によるところが大きい。
遠山はインターネットを利用した広告のみで営業活動を行い、日本全国から契約書作成等の依頼を受けている。片田舎の個人事務所だが、東京や大阪等の巨大都市圏を始め、南北の離島からも依頼は入る。
経済力も何の力も無い一個人ですら、ネットの有効利用を図るだけで、集客は可能となるのだ。
広告や営業にかかる経費を抑えて、ダイレクトに成果を上げたいという思惑は、どんな事業でも共通すると思う。
そこで、ダイレクト・マーケティングの最新ツールであるインターネットを利用しないのはもったいない。インターネットは単なる情報検索だけの手段ではなく、あなたのビジネスや価値観を全国にPRするツールでもあるのだから。