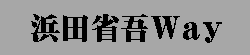
社会との折り合いトップ
ファン・サイトの浜田省吾Wayです。
浜田省吾のデビュー30周年時に公開の個人ブログ。【祝・40周年】
浜田省吾は現在ROAD&SKY(ロード・アンド・スカイ)という事務所に所属している。デビュー時にはホリプロダクションに所属していたが、1983年4月1日に独立してROAD&SKYを設立した。(社長は愛奴時代のベーシストだった高橋信彦が務めている)。
このROAD&SKYを設立して独立するきっかけとなったのは、ライブに関するホリプロとの認識の違いにあったようだ。ホリプロは音楽業界のセオリーに従って、レコードのセールスを第一と考え、ライブについてはレコードを売るための販促活動の一手段と考えていたようだ。
浜田省吾自身は、それまでのライブ活動に手応えを感じていて、ライブを自らの音楽活動の中心にしたいと思ったのであろう。そこに互いの認識のズレが生じ、浜田省吾は独立する必要性を感じたようだ。
だからといって、ホリプロと浜田省吾の間に軋轢が生じたわけではない。ファンクラブ会報「ROAD&SKY 61号」の中で、「ホリプロの堀社長には、独立を理解してもらって今でも感謝している」と語っている。
金銭や人間関係で揉めれば、所属事務所とミュージシャンの間で法廷闘争も含めた泥仕合になる事例もあるが、浜田省吾の場合はそのようなトラブルとは無縁だった。それは浜田省吾の音楽に対する姿勢が明確で、ホリプロもその信念に納得できるところがあったからだと想像できる。
晴れて新事務所を作って独立することになった浜田省吾は、事務所名をジャクソン・ブラウンのアルバム「LATE FOR THE SKY」の5曲目に収録された「ROAD&SKY」から引用した。
このROAD&SKYという名前に込める思いについて、浜田省吾は次のように語っている。
「ROADという言葉は、ON THE ROAD、つまり永遠に続くツアー。」
「SKYは無限に広がる音づくり。つまりレコード制作。」
ライブ・ツアーと音楽製作をイメージして、それを事務所名にするのは浜田省吾らしい。スタッフやファンに対して、ライブと音楽製作を通じて活動していくというメッセージが明確にされている。
理念や目的がハッキリしていれば、周囲も安心するものだ。カリスマやリーダーと呼ばれる人達は、活動の理念を熱く語らねばならない。その義務に対して、浜田省吾は答えを用意していたのだ。
しかし、独立直後のROAD&SKYには難問が立ち塞がっていた。それは1983年8月に、福岡県の海の中道公園で大規模な野外コンサートを企画したことだ。
ライブで生きていくことを宣言した浜田省吾とROAD&SKYにとって、これは失敗が許されないイベントだった。集客が思うようにいかなければ、大赤字となり事務所がいきなり潰れるリスクもあった。
傍観者の立場で眺めれば、何も独立直後の資金の厳しいときに、事務所の命運を賭けるような冒険をしなくてもと思ってしまうところだ。
それだけ浜田省吾はライブにこだわり、大規模な野外コンサートを成功させることで道を切り開きたかったのだろう。
結果として、この海の中道公園の野外ライブは18,000人を集客し、大成功となった。この年の浜田省吾は、138回の公演を行い約258,000人を動員している。その7%近い集客を海の中道で達成したわけだ。このときの感動は忘れられないと、様々なインタビューで答えている。
このようなイベントを成功させるためには、スタッフの協力は不可欠だ。資金や日程に余裕は無く、関係者がどれだけ本気で尽力できるかにかかっている。
無謀ともいえる企画を押し通すには、周囲やスタッフの理解無しには進まない。
どんな職場でもそうだが、無茶な計画や業務命令は従業員のモチベーションを低下させる。例えば、月末締め日の直前になって、「今月の予算は200%上方修正する」と言われたらどうだろうか?
ほとんどの人は、その時点で「終わってるな」と冷笑するだけだろう。実際に上方修正された新目標に対して努力するわけは無い。
同じように、一歩間違えれば浜田省吾のライブ優先の活動は頓挫するリスクはあったと思う。それを回避して、ライブの帝王の座を獲得することになったのは、スタッフの努力であり、リーダー(またはカリスマ)としての浜田省吾の力量であろう。
人は無謀な目標や計画にはついて来ないが、理念に共感できるところがあれば動くものだ。単に上位下達で目標を押し付けるのではなく、理想を語り、その実現への道筋を予感させるリーダーがいる組織は結束が強固となる。そんな組織は常勝集団となるだろう。
ただ、浜田省吾も何の見込みも無く無謀な大規模野外ライブを企画したわけでは無いだろう。前年までのライブの手応えを感じていて、この流れなら冒険はプラスに作用するという読みはあったはずだ。
何の根拠も無い(マーケティング調査に基づかない)冒険であったなら、周囲を説得できずに企画実施すらできなかったであろう。
あらゆる組織のリーダーは、現実の成績をベースとして把握しながら、将来を向いた理念を語らなくてはならない。そして、その理念に共感するスタッフに恵まれたなら、リーダーは組織内のカリスマとなり、事業の成功は約束されるだろう。
浜田省吾といえば、数多くのラブ・ソングもリリースしているが、メッセージ性の強い歌を作るシンガーという印象も強いと思う。実際に、戦争や平和をテーマにした曲は多い。
そうしたメッセージ性のルーツを、過去の学生運動にあるのではと邪推するファンもいるが、浜田省吾自身はそれを否定している。
確かに学園紛争が盛んな頃の神奈川大学に籍を置いていたことは事実だが、ストによって講義が行われなかったり、学生の派閥抗争によって荒廃する大学に嫌気が差し、1年半で退学している。
浜田省吾は平和に対する思い入れの原体験として、広島生まれであることを挙げている。それは小学生の時に原爆資料館を見学したときの衝撃であったり、被災者救助に駆けつけて二次被爆をした浜田の父親の体験談を聞いて、戦争は嫌だと強く思うようになったことであったりする。
そうした思いが底流にあり、反戦や平和をアピールする歌詞を多く書いている。そうした曲からは、その鋭い洞察力に圧倒されるばかりだ。
1986年に発売されたアルバム「J.BOY」に収録された「NEW STYLE WAR」では、「地下から地下へ運ばれたBOMB(爆弾) 国家に養われたテロリスト」と風刺をしている。
また、同時期のインタビューでは、「日本は平和だし、世界も今は、ほら、ソ連とアメリカも一時の緊張感ってなくなってきてるでしょう?だけど、これからの戦場っていうのは国境で区切られている戦場ではなくてね、いきなり東京の丸ノ内のビルが爆破される戦場かもしれないし、病原菌や自然破壊やそういったことが新しい戦場になるわけで、ある意味では今まで以上に平和な時代ではないんじゃないかなって。」(「青空のゆくえ」ロッキングオン)と答えている。
ちなみに、猛毒サリンを使ったオウム真理教の無差別テロである地下鉄サリン事件は1995年。アメリカの世界貿易センタービルやペンタゴンに対する同時多発テロ(9.11事件)は2001年に発生している。
このような陰湿で無残なテロの可能性を、浜田省吾は1986年の段階で予見していたともいえよう。
このような普遍性・予見性を持つ歌を作り出す才能には、本当に驚愕してしまう。
この「NEW STYLE WAR」では、このような新しい紛争の原因は「飽食の北を支えている 飢えた南の痩せた土地 払うべき代償は高く」と分析している。
つまり、豊かさや富の偏在が、一方で圧倒的な貧困層を生み出し、その矛盾がテロを誘発するという解釈ができる。
翻って、現在の日本では格差社会の是非が問われている。
ヒルズ族に代表される億万長者と、生涯を企業勤めで終える一般のビジネスマンとの間には、実に大きな経済格差が生まれている。まして、就労の意欲すら持てないニートに至っては、比較にすらならない。
もちろん、日本は資本主義社会だから、たくさん働いて多く稼いだ者が笑うのは当然だ。そのことに異を唱える人はいないだろう。
しかし、それは自由競争の原理が正常に機能することが前提となる。平等の条件の下で競争を行って、その結果より多くの努力をして汗を掻いた者が報われる経済システムであれば、誰も文句は言わない。
だが、競争のスタートラインが平等ではなく、既に経済力を持つものが優遇されるならば、建前の競争など意味はなさない。
例えば、官公庁のコンピューター・システムの入札でも、仕様書を厳密に指定すれば、実質的に対応できる業者は限定されてしまう。その仕様書策定の過程が不透明であれば、競争は機能しない。
巧妙な細工で、富を持たざるものを排除することは可能なのだ。
現在、ニートが急増しているのも、競争による上昇志向をイメージし難く、社会の閉塞状況を敏感に感じ取っているからではないだろうか。
日本は少子高齢化社会を迎えるのに、働き手である世代にニートが増えているのは、日本経済にとってマイナスである。本来なら貴重な若手の労働力として期待したいのに、その層を親や国家が扶養しなくてはいけないのでは、本末転倒だろう。
これは個別の企業や職場においても同様であろう。勤労意欲に乏しい若者を一方的に責めるのではなく、どのようにして彼らの意欲を引き出すのかが問われている。
そのためには、前提条件の整備が必要だ。つまり、平和・平等をモットーとして、公正な競争を図り、努力した者が報われることを明らかにすることだ。
そんな単純なスタート・ラインの整備ができない職場も多いのではないだろうか?
うつ病(鬱病)はストレスに起因する精神の病気で、生きる活力が落ち込み、その結果として体のあちこちが不調となる症状が表れる。
現代日本では、5人に1人は一生のうちに一度はうつ病を経験すると言われるほど、精神的に参ってしまう人は増えている。
これほどうつ病の患者が増えているということは、花粉症と同様に文明病・国民病として認知されるべきかもしれない。
どうやら“ロックスター”浜田省吾もその洗礼を受けてしまったようである。
彼が精神に変調を来たしたのは、1992年の夏だ。
この年、「悲しみは雪のように」が大ヒットし、シングルチャートの売上1位を8週間連続で確保した。いわゆる浜田省吾の社会的評価が絶頂に達した時期でもあった。
これは実に皮肉な現象といえよう。世間で一番認められたときに、その張本人がうつ病で表舞台に出られる状態では無かったのだ。
つまり、うつ病というのは社会的成功者であっても容赦なく陥る可能性がある。
この時期を振り返った浜田省吾の言葉を引用しよう。
「 その92年の夏、僕はちょっと精神的なバランスを崩してしまいまして。2週間ぐらい全く家から一歩も出ないで、居間の窓に-まあ窓から空が見えるんですけど、ずーっとボーッと2週間何もせず。」
「ええ。非常にヤバイ状態だったんですよ。かつてない、いちばんヤバイ状態で。その時のイメージ-その時は楽曲なんて作れる状態じゃないですから、それから少しずつ少しずつ立ち直って。(中略)僕自身の心の危うさっていうんですか。で、精神の危うさっていうのは、こうやってみんなを見てても、誰を見ててもみんないい奴で、問題も抱えてたりするんだけど陽気な部分もあったりして、でも何かひとつがポロッと壊れた瞬間に、誰もが大きく精神のバランスを崩す可能性を持ってるのが、自分自身の体験からよく分かったんですよ。」(BRIDGE 2001年10月号より)
どうやら浜田省吾自身も、自分がうつ病になるとは思ってもみなかったようだ。心身ともに健康なときに、自分がバランスを崩したことを想像できるわけはない。
それだけに、誰もがそのような精神状態に陥ったり、または家族や知人にうつ病になる人がいた場合、その対処法を理解しておいて損は無いだろう。
遠山も仕事で離婚協議書を作成する機会は多いが、多くの場合、依頼者はうつ病の診断をされている。他にも傷害事件の後遺症として、うつ病が治らないケースもある。
何かトラブルを抱えると、人は心身の均衡をとれなくなり、睡眠障害などの体調不良に見舞われる。体重が激減したり、逆に過食で急速に肥満になったりもする。
そんな局面には、何をするべきだろうか。
まず、うつ病の症状を把握しておく必要があるだろう。その症状は精神面と肉体面の両方に表れる。
精神的症状としては、集中力が散漫になったり、常に悲観的な考え方をするようになる。人と会ったり話をするのが極端に嫌になり、何もする気が起きなくなる。そして、ただひたすらボーッとすることが多くなる。
肉体的症状としては、食欲不振、便秘、肩こり、不眠、頭痛、動悸、異常な寝汗、性欲低下、月経不順などが顕著だ。
こうしたうつ病の症状も、重度の人は外出困難となり就業は不可能だが、軽度の場合は上記のようなトラブルがありつつも何とか仕事をこなしているケースもある。
だが、そんな苦しい状態が数年も続くこともあり、できれば早期に治療をした方が良いだろう。
うつ病になった人は、自分の精神が変調していることを理解できなかったり、認めようとしない場合も多いようだ。
周囲の人がうつ病の傾向に気づいたら、治療を勧めてあげる必要があるだろう。
その具体的治療法としては、通院をする意欲が起こるまで先ずは休養をとることだ。その上で精神科に通い抗うつ薬の処方をしてもらう。その後、医師やカウンセラーの指示に従って精神療法を受ける。
もちろん、うつ病となるきっかけが明確になっている場合は、その問題を解決することも大切だ。しかし、問題に対峙するエネルギーが残っていない場合は、まずは治療を優先しなくてはならない。
うつ病は治すことが可能な病気であるという認識を広めることも重要だ。精神的に追い込まれた患者は、自分の怠け心のせいだと思い込んで、更に自分を責める傾向にある。
うつ病の症状が明確になった場合は、まずは休養を取り、1年単位で通院して治療をすることも視野に入れた方が良い。軽症であれば、休業は最低限に抑えて、治療は通院で済むことも多い。
風邪をひけば内科に通うように、精神が病んだら専門医にかかるべきだ。その方が治癒も早くなる。
浜田省吾も最も忙しい時期に休養を取り、うつ病の治療に取り組んだ。そして、徐々に曲作りに復帰して素晴らしい作品をリリースし、ライブもバリバリにこなせるようになった。
もし、うつ病を抱えてしまったときには、急がば回れのことわざとおり、休息をすることが何よりも大事なようだ。
国際的な交流が進んで、現在では日本にいながら音楽や料理などバラエティに富んだものが楽しめる。
テレビ番組もいろいろな国の習慣を紹介したり、異文化に飛び込む日本人の姿を放映している。もちろん、インターネットを使って直接外国の様子を調べることも可能だ。
そんな中で、各国の良いものはすぐに輸入され、日本人の音感や味覚にあったカスタマイズが行われ、そしてJAPN仕様となって流行していく。
こうしてブレイクしたものは、不思議なもので昔から日本にあったかのような存在感を示し定着していく。
文化の融合とはそんなもので、それぞれの出自を明確に意識する必要なんて無いのかもしれない。
だが、浜田省吾はプロフェッシャルゆえに音楽のルーツにはこだわっているようだ。彼の制作するロックやR&B、バラードといった種類の音楽は、元はアメリカから輸入されたものだ。
その音楽や文化の浸透について、浜田省吾は次のように語っている。
「 例えばアメリカ人なら音楽的にいき詰ったり、アイデンティティにいき詰っても、カントリー&ウェスタンとか開拓精神といった原点に帰って行けるでしょ。オレはどうかと言えば、帰る場所がきっとあるハズなんだろうけど、伝統的な和楽とは感覚的にかけ離れ過ぎてて、そこには帰って行けない。それは一体何なのだろう。ひょっとしたらオレは戦後の子供だということをしっかり認識しないで、オブラートに包まれて育ってきたんじゃないかって思った。どういうことかと言うと、日本はかつて人類史上例の無い原爆ってやり方で占領された。つまり強姦され、その結果生まれてきた子供じゃないかってことなんです。」(FM fan 1988年3月7日号より)
ちょっと過激な表現だが、音楽にしても文化全般にしても、戦後の日本はアメリカから積極的に吸収しようとして、結果として古来からの伝統文化は軽んじることになったという事実は認識できる。
それで、今更伝統文化に立ち返って琴や尺八をやろうとは思えない。能や歌舞伎が見直されているとといっても、ハリウッド映画に匹敵するような観客動員数を見込むことはできない。
そう考えると、戦後と戦中以前では日本という国の文化はガラリと変わってしまったことになる。本来なら音楽も含めた文化や歴史というのは、気の遠くなるような年月を経て継承されていくものだ。
しかし、日本の場合は伝統文化が急速に弱体化し、アメリカから輸入された文化がコンピュータウィルスのように瞬時に爆発的に普及した。
そのようなアメリカン・ライフスタイルに憧れた人々が、物欲を刺激されてそれを手に入れようと懸命に働いた。その結果、高度経済成長を実現し経済大国と言われた礎を作った。
テレビで流れる音楽も、ポップミュージックが主流となり、和楽は影を潜めた。
このように戦後はアメリカを向いて突っ走って来たわけだが、走り疲れてふとふりかえると、そこには昭和初期の故郷の面影は消滅していた。
故郷を探して明治の町並みを見ても、そこは居心地が悪い。結局、東京的な暮らしや文化から離れることはできない。
実はこのような戦後の文化変容の体験は、日本は近代にも体験している。
そう、明治維新だ。
明治維新は外圧による影響が大きかった。黒船来襲ってやつだ。欧米列強に開国を迫られ、サムライはちょんまげを落とした。
もちろん、第二次大戦のようなアメリカによる占領という事態までには至らず、幕府を倒して新政府を樹立するというのは、基本的には日本人の手で行われた。この点は戦後のアメリカ盲従との相違点だ。
だが、急速に近代化を急ぐことになり、欧米の文化輸入は最高のハイカラとして崇拝された。
現代日本のイタリアやフランスのブランド信仰などは、この頃に形成されたのかもしれない。
そして、大正デモクラシーやいくつもの戦争を経て、1945年にアメリカに占領されることとなった。
戦争中に鬼畜米英と刷り込みをされていても、明治の代で変わり身の早さを経験していた日本人は、手のひらの返し方は体得していた。
それはもう、驚くほどのスピードでフォードやクライスラーを研究し、世界のトヨタやホンダを生み出した。
音楽の分野では、初期の頃はビートルズやエルビス・プレスリーを丸ごと受け入れて崇拝したが、歌詞が何を言っているかわかんねえやということになる。
そこで、洋楽のリズムにのせて日本語で日本人の心情を唄うヒーローたちが出現した。浜田省吾はその代表格で、既に日本人のリズム感として市民権を得たロックで「J.BOY」と叫んで喝采を得るようになった。「J.BOY」とは、もちろんJAPANESE BOYのことだ。
みんなが大好きなアメリカ文化は取り入れつつ、全てをマネしているわけではない。かといって、復古主義で演歌を唄うわけでもない。
現在の日本人が抱いている気分を、忠実に歌詞へ反映してくれる。それが浜田省吾ではないのだろうか。
アメリカとの距離感を丁度良く保って、日本人の精神性も大事にする。この現実を受け入れて独自の道を模索する姿が、あらゆる分野で求められているのではないだろうか。
ビジネスマンは一日の大半を仕事に費やしている。仕事というのは職場での労働だけを指すだけではなく、家庭での家事労働も含まれる。
だから、いわゆる専業主婦(主夫)も仕事に割く時間は大きい。人生の中で、仕事をしている時間が最も割合的に多くなる人がほとんどだろう。
ちなみに、遠山は睡眠時間が長いタイプだが、できれば仕事よりも睡眠時間を長く出来ないだろうかと密かに願っている。無論、それは叶わぬ夢だが。
その人生の中で最も多くのエネルギーを投入し、多大な時間をかけているのが仕事なわけだ。
すると、仕事が充実して楽しくて仕方が無い人というのが、最も人生を上手に生きている人だと言えないだろうか。仕事が楽しければ、一日の大半の時間が快適に過ごせるということだから。
そこで、浜田省吾は「仕事」についてどのように考えているかを探ってみよう。
「 仕事っていうのは、ただ、お金をもらって生活するためだけのものだったら、どこか寂しい気がするんですね。人は社会的な生き物ですから、仕事をすることによって、社会の中のつながりとか誰か人のためになっているとか、そういう存在価値みたいなものを見出せたらすごく幸せだと思うんです。
主婦っていうのも、やっぱり仕事だと思うんですよ。家族をケアしながら子供を育てていくことも社会とつながってることだし。その中で社会に対する存在価値を見いだせなくなっているとしたら、不幸なことだという気がします。」(日経エンタテイメント 1999年12月号より)
納得である。現代社会は物の生産や流通が高度化して、仕事の内容が分業化・細分化されている。
過去においては、仕事の企画段階から原料仕入れ、加工製造、運搬、販売に至る過程を少人数でトータルに実施されていた。
それが社会の経済システムが高度化するにつれて、各作業が分担されるようになり、それぞれの作業現場でのスペシャリストが誕生した。企画立案のプロ、バイヤーとして凄腕を発揮する営業マン、神業とも言える加工技術を発揮する熟練工。それぞれが極めて狭い範囲でのプロフェッショナルぶりを発揮する。
例えば、工場の中で精密回路のハンダ付けの作業を任された場合、ただひたすらにハンダと格闘する。黙々と作業をこなすうちに、その作業速度は神の領域に達し、プリント基板の極小の不良についても一瞬で見抜く超能力を会得するようになる。
一方で、それ以外の仕事が見えないわけだから、同じ会社にいても他の人の作業内容は不明だったりする。ハンダとプリント基板についてはプロになっても、自分のやっていることが社会のどこで役に立っているか、その根本的なことを知らないということもあるだろう。
上司も、この部品がどんな製品に使われるのか教えてくれないことも珍しくない。
そんな状況で、朝礼時に「お客様のために貢献しろ」とか「仕事に誇りを持て」と言われても、それは虚しいスローガンとして耳の左から右へ抜けていくだけだろう。
何しろ、自分がどんなお客様に対して、何を作っているのかわからないのだから。
逆に消費の場面でも同様だ。今晩の夕食の刺身について、その生産や流通過程に携わる人々の苦労にどれだけ意識はいくのだろうか。
魚が切り身になるまでは、養殖業者の手で何ヶ月も世話をされた魚が水揚げされ、鮮度が落ちないうちにトラックで運ばれ、加工センターで切り身にされる。その後、店頭に並ぶわけだ。その間では熾烈な価格交渉があって、そこでストレスを抱える人もいるはずだ。
スーパーのバイヤーは納入業者の価格を買い叩き、納入業者は漁師を叩く。尊大な大口顧客が小規模な納入業者に無理を言うという連鎖が延々と続いていく。
笑い話で、小学生に魚の絵を描かせると、切り身が泳いでいる絵を描いたという話がある。夕食の刺身が、水族館で見たことのある生きた魚のパーツであるということが認識できないのだ。無論、お母さんが魚をさばいているところを見たことは無い。魚は切り身で買ってくるものだと学習している。
それほどまでに現代人は、かつては自らの手で行っていた工程の一部しか見ることができず近眼になっている。
そんな断片的な日常を繰り返していると、自分が社会の中でどのような役割を担っているかを感じ取るのが難しくなる。
浜田省吾も語るように、社会とのつながりを認識しないことには、人間は孤独や疎外感から開放されることはない。面倒に思える作業になるかもしれないが、自分のやっている仕事が何の役に立っているのかを調べ、その全工程や全体像を把握する努力を行い、それを家族と語って確認することが幸せにつながるのかもしれない。
自分がやっている仕事がどんな役に立っているのか、それをイキイキと語る様子が子供たちにもまぶしく映るだろう。
人間にとって何が幸福かってことは永遠のテーマになるだろう。とにかく衣食住は足りて、生活が満たされることを優先する人もいれば、精神修養を第一に掲げる人もいるだろう。
人それぞれで大切なものも違う。遠山の場合は、とりあえず好きな時に渓流釣りができて、パソコンは四六時中ネットにつないでいれば、かなり満足してしまう。
もちろん、家族や友人も大事だし、仕事も順調にこなしたい。
大事にしたいのは、恋愛だったり、友情だったり、ビジネス的成功だったり、趣味を極めることだったりもする。
このあたりは、人によって千差万別だろう。
幸福の条件として、それが物欲であればわかりやすい。
「純白のメルセデウス プール付きのマンション 最高の女とベットでドン・ペリニヨン」
これはある有名な歌手が作った歌詞だが、このように欲しいものを列挙すれば、どれだけ手中に収めるかで満足度を図ることもできる。
でも、ここに挙げられたモノを手に入れるには、かなり頑張らないとキツそうだが。
それほど物にはこだわらない人もいるだろう。とにかく三食に不自由なく暮らせれば、それで充分だという向きもあろう。
でも、独りだと寂しいから友達や恋人は欲しいと思ったりする。
浜田省吾も、デビューしたての頃は世俗的な成功を夢見ていたそうだ。アメリカで流行したロックで一山当てて、豪邸でも建てようかという野心はあったという。
だが、実際に長者番付に掲載されるくらい稼ぐようになると、今度はゆとりがほしくなったそうだ。
そりゃそうだろう。全国を移動しながら年間に150回近いライブ数をこなし、合間にアルバム制作をするという過密スケジュールだったら、儲かるだろうがプライベートな時間は限られてしまう。
企業戦士でも同様だが、超多忙になると自分のことに構っている時間は無くなってしまう。“オレはバリバリに働いて充実しているんだ”と強がってみせても、休日も無く帰宅したら疲れて寝るだけの生活に嫌気が差すこともあるだろう。
そんな追い立てられるような仕事漬けの毎日を送っていると、本を読んだり映画を観たり、家族や友人・恋人とゆっくり過ごす時間が欲しいと思うようになるものだ。
でも、時間にゆとりがあってもサイフにゆとりが無いのはカンベン願いたい。
すると、ビジネスで成功していても、無尽蔵な時間を持て余していても、どちらにしても不満は生じるということになる。これは困った。人とはいかに小難しい生き物なのか。
そんな人間の幸福についての考察を、浜田省吾は次のように述べている。
「 基本的には幸福になるための要素は三つあると思う。
それはものすごくシンプルなことで、一つは“健康”であること。それから、“平和”であること。それは世の中が平和であることもそうだし、自分の心が穏やかであることも含めて。もう一つは“孤独”でないこと。この三つがそろえば幸福なんだと思うんです。
そりゃあ、やりがいのある仕事だとか趣味とかほかにもいろいろ細かいことはあるかもしれないけど、基本的にはひとりぼっちじゃなくて健康で平和だったら、それは幸福なんだと思う。その三つを自分のために揃えて、幸福になりたいと思うのなら、それを勝ち取ってやるという努力が必要なんですよね。」(JUNON 1990年9月号より)
これは実に的確な指摘だ。健康でなければ何も始まらないし、平和でなければ恐怖に怯えなくてはならない。孤独は人を追い詰める。
しかも、この三つの要素を得ていくためには、努力が必要だとも言っている。
つまり、健康を維持するためには、食生活や運動量に気を配らなくてはいけない。平和を享受するためには、その存在を脅かす動きに警戒を怠ることはできない。絶えず、社会情勢に関心を持つことが必要だろう。
孤独を脱するためには、進んで人とコミュニケーションを図らねばならない。
このように、幸福を形成する三要素は、受身では待ち人のところに来てくれないのだ。自分から積極的に取り込んでいく努力が不可欠といえよう。
また、人は初期の段階では自分だけの幸福で満足できる。これら三要素がスロット台のようにゾロ目で揃ったら、とりあえず満足するだろう。
だが、その満足感は永続しない。
次の段階として、“孤独ではないこと”と関連するのだが、自分が社会とつながることで役立ちたい。人に認められたいという意識が働くようになる。
そのようにして、幸福への欲求のレベルは上がっていく。
単に物欲に振り回されているうちは、足もとの幸福には気づかない。当たり前だと思っていたことに関心を持ち、身の回りのものを大事にして、人とは進んで接する。
それを意識的に繰り返せば、自ずと幸福を実感できるものなのかもしれない。
男女の恋愛が結実すると、それは結婚につながり、やがて親子や家族という関係が発生する。もちろん例外もあるだろうが、一般的にはそういう過程を辿るだろう。
つまり、恋愛感情は家族愛に昇華していくものだ。
その家族愛では、親子というのも重要なキーワードとなる。親子の愛情というと、普通は母親と子供の関係を連想するだろう。
子供にとって母親というのは、無条件に受け入れてくれる特別な存在なのだ。実際に遠山の家庭においても、子供が慕うのは母親であり、父親は半歩離れたところにポジショニングされている実感はある。子供が年頃になった暁に、洗濯物を箸でつままれるような状態にはならないよう気をつけたいものだ。
また、遠山自身の育った環境が父親とは死別による母子家庭だったため、父親の存在感がどういうものなのかリアルにはわからなかった。物心ついたときには母親しか存在せず、よその家庭で茶の間に父親が鎮座しているのを目にすると、何か敬遠する心境が働いた。 そのため、自分の感覚では親イコール母親であったので、父親象のイメージが貧困であることをお断りしておく。どうも、「父親なんていなくても子は育つ」という感覚が染み付いていることは否めない。
だからといって責任転嫁するつもりは無いが、自分が父親になったときには、妙な違和感があった。どう対応すべきかわからないというか、所在無さみたいなものを感じた。それは、初めて我が子と対面した父親なら誰でも感じることかもしれないが。
それでも10年も父親業をしていると、それなりにやるべきことは心得てくる。そんな今になって、亡き父親の胸中や母親の苦労に思いがいくようになった。
そんな遠山の抱く個人的な父親像は別にしても、世間一般の認識においても現代の父親は家庭で疎外されているのかもしれない。
父親は仕事だゴルフだ釣りだといって家にいないから、どうしても子供は母親についてしまう。仕事で疲弊しきっていることは確かなので、たまの休日は寝転んでいると子供にはグウタラしているようにしか映らない。その子供が思春期になれば「子供が口をきいてくれない」と嘆く父親は多い。
実に頼り気の無い父親像になってしまうが、意外にも浜田省吾は父親との関係を歌にしているものが多い。
1984年に発表された「DADDY‘s TOWN」では、「GOOD-bye Little Daddy’s Town 何もかも閉ざされたMy Hometown」と父親の住む街に毒づいて、家と街を飛び出すことを宣言する心境を曲にしている。
そこには父親が少年の抑圧の対象として描かれている。
1988年の「DARKNESS IN THE HEART」では、「思い出す病室で痩せていく父の姿を 痛みから解かれて去って行った独りきり 車の窓に映っているおれの顔 彼に似ている」と癌との闘病生活の末に亡くなった父親を回顧している。
それは父親に対する伝え切れなかった思いと、その血をひく自分がどう生きるかという自問がある。
そして2005年の「I AM A FATHER」では、「傷ついてる暇なんか無い 前だけ見て進む」「嘆いてる暇なんか無い 命がけで守る」と父親としての決意表明をしている。
浜田省吾自身には子供はいない。それでも、父親世代の心情を代弁して、かつては少年だったが自分が今では父親になったことの自覚を軽快なロックにしている。
このように少年時代は威圧的な壁として存在していた父親が、実は社会の荒波からの防波堤として身を捧げてくれていたことに気づき、今度は自分が子供のために堤防となっていくことを一連の歌にしている。
浜田省吾の30年の音楽活動の流れの中で、父親というキーワードの視点が対立の対象から和解、そして踏襲へとシフトしている気がする。
少年期の父親ならびに社会への反抗というテーマでは、佐野元春が「ガラスのジェネレーション」で唄った「つまらない大人にはなりたくない」というフレーズも有名だ。
1960年代から70年代にかけては、Don’t Trust Over Thirty(30歳以上の大人の言うことを信用するな)というスローガンも流行したらしい。
これは大人社会に対する不信感から、反抗という自己表現をする若者らしい特性を表している。
そんな反抗期を経て、かつては嫌悪の対象であった大人になってしまった現在の父親世代は、もうハラをくくるしかない。
傷ついて感傷的になったり、不遇を嘆いている暇など無く、現実的な問題が次々と目の前に出現するのだ。これはもう、命がけで前に進んでいくしかない。その生き様を子供に対して背中で語るしかないだろう。かつては自分たちの父親がそうしてくれたように。
でも、自分が子供の頃の父親には問答無用の理不尽さがあったと思うなら、そこは改めて子供には向かい合いたいものだ。
今の父親は育児や子育てに積極的に関わろうとしても、残業や休日出勤などビジネスマンの苦役はキツく、なかなか時間が確保できないという問題はある。
また、子供を巻き込んだ凶悪犯罪は増え、世の中が世知辛くなってきている。そのような困難はあるが、だからといって子育てを放棄するわけにはいかない。
そのような父親世代の決意の曲として、I AM A FATHERは歌い継がれている可能性を秘めている。これは時代を反映し、家族のあるべき姿を予見する曲と言っていいだろう。
浜田省吾はよく「単純なラブソングが好きだ」と語っている。また、実際に数多くのラブソングをつくっており、ファンはその世界に陶酔する。カラオケでも定番となっているバラードも多い。
「もう一つの土曜日」や「愛しい人へ」のような苦労の末のプロポーズや結婚への決意表明を歌った曲もあれば、「片思い」や「陽のあたる場所」のような成就することの無い後暗い情感あふれる曲もある。
どちらかといえば、うまくいかない恋愛を唄った曲の比率の方が高いだろう。それ故に「浜省の曲って暗いよね」っていう評価もつきまとうが、それも歌詞の素晴らしさの勲章と言えよう。
こうしたバラードは、見事なストーリー性を構築しており、その歌詞で60分枠の恋愛ドラマが一本できるほどだ。それほど歌詞の情景描写は見事で、聴き入るほどにそんなドラマの1シーンが瞼に浮かんでくるようだ。
そのような男女間の恋愛については、普通は結婚までが一つのクライマックスとなるだろう。(結婚してからも婚外恋愛で盛り上がってしまうイケナイ恋愛体質の人もいるでしょうが・・・)
恋愛の一応のゴール(通過点という説が主流だが)である結婚までには、くっついたり離れたり、時には横恋慕があったりと様々なドラマがある。
結婚してからも家族のドラマはあるわけだが、それは別の章で述べることにする。
その結婚式という社会的儀礼を通過すると、自由恋愛の頃とは違った責任が発生する。恋愛や結婚について話すのに、“責任”とか持ち出すのは興醒めだが、逃れようの無い事実なのだ。
その責任とは、同居や協力扶助の義務であったり、夫婦貞操の義務であったりする。ちなみにこれは民法第752条や同法第770条にキッチリと定められている。
正確に言うと、その“責任”は結婚の時点ではなく、結婚を誓い合った時点(いわゆる婚約)から発生するという見解が主流になっている。
つまり、婚約以前の自由恋愛の状態であれば、一方的に別れても損害賠償の責任は生じない。平たく言うと、慰謝料を支払う必要は無いってことだ。
しかし、いったん婚約なり結婚をすると、これは契約が成立したってことになり、一方的に破棄をする場合は損害賠償責任が発生する。こんなケースでは、身勝手に別れると言った方は、ガッポリと慰謝料を持っていかれることになる。その別れる原因が浮気ということなら、もう逃げようがない。
すると、自由恋愛のうちは失敗したり傷つくのも自己責任ということになる。浜田省吾も「彼女はブルー」の中で「愛ははかなく 契約なんてないのよ」と唄っている。
結婚という契約が成立すれば、法律が守ってくれる場合もある。でも、婚約前の自由恋愛は、どれほど失恋のショックを受けようとも、その苦しみは自分ひとりで背負わなくてはならない。それが近代の原則であり、自己責任ということだ。
今は婚約破棄や離婚について苦しむ人は増えている。それは辛い出来事であるし、その人の人生においては大きな悲劇だ。統計的な離婚率の上昇を見て嘆く人も多い。
しかし、明治以前であれば、婚約を拒んだり離婚をする自由はなかった。不本意な結婚生活であっても、それを断ち切る自由がなかったわけだ。当時でも、離婚の自由が認められ、経済的にも問題が無ければ、恐らく離婚率は格段に上がっていただろう。
そういう意味では、婚約破棄や離婚の自由が広まったと言えよう。何も我慢して嫌になった相手と同居を続ける必要は無いということだ。
交際相手も自由に選べ、婚姻生活が我慢の限界を超えるようなら、離婚するのも自由なのだ。
だからといって、別れるのを前提とするような非生産的な疲れる交際の仕方はオススメできない。男女恋愛をするなら、本気で相手を愛し抜く気概を持つべきだと思う。
ビジネスでも、失敗を前提として企画を打つことはありえないだろう。失敗を「想定の範囲内」等と取り繕ってみても虚しいだけだ。
同じように、恋愛でも長続きしないと思いながら付き合うのは、やはり虚しいだろう。交際をするからには、結婚を意識できる相手と付き合った方が健全だ。真剣に付き合ってみたものの、結果としてうまくいかない場合もある。そんな時は、かなり落ち込んでしまうのは仕方ない。
しかし、いつまでも沈んでいても始まらない。ひとしきり辛さを噛み締めたら、その後は立ち上がらないといけない。
恋愛の破局時には半狂乱になる人も多い。その心情は理解できる。ただ、それは相手に対する依存心が強すぎるということだ。
恋愛をするのは自立した男女だ。その自立が怪しいと、相手に精神的にドップリと依存してしまう。恋愛がうまくいっているうちは、それでも何とか回るものだが、別れることになったときには取り乱してしまうことになる。
人生には挫折とか失敗はつきものだ。受験や就職に失敗することもあれば、事業に失敗することもある。恋愛や婚姻生活の挫折も、そのような失敗の一つと言える。その挫折のたびに半狂乱となっていては、やはり強くなっていくことはできない。
浜田省吾は成就しない恋の歌を数多くつくっている。それは、転んでも起き上がることの大切さを説き、辛い気持ちの人の背中を押してくれる優しさもある。そんなラブソングを人生の応援歌と思って、活力に変えていきたいものだ。
芸能人にとって、プライバシーの確保は頭の痛い問題だろう。その苦悩は一般人からは窺い知れない。
中にはゴシップを売名行為に利用するしたたかな著名人もいたりするが、本音は静かにしておいて欲しいところだろう。
私生活と芸能ネタが密接に絡むお笑い芸人でも、プライバシーの侵害は有名税として受け入れるにも辛いものだ。
浜田省吾の場合は、ミュージシャンとしてプロ意識が高いだけに、ステージや広報以外で個人的話題に触れられるのを敬遠しているように思う。
注目されるのは音楽やステージの上であって、プライバシーを切り売りしたくないという意志を感じさせる言動も多い。
例えば、ファンクラブの会報でも以下のような受け答えをしている。(1991年 ALL ABOUT SHOGO HAMADAより)
Q:兄弟・姉妹関係をはっきりと明記して下さい。
A:ひみつ!
Q:“生まれたところを遠く離れて”に省吾と一緒に写っているのは奥さまですか?
A:そうです。が、プライベートはそっとしてあげて下さい。誰でもプライバシーはあるのだから・・・
Q:ファンの人にしてほしくないことってありますか?
A:自宅に来ること。車の後を追いかけてくること(本当にイヤなんだ)
このように家族や個人的事情に触れることは話題にはしたがらない。曲の歌詞では浜田省吾自身の精神的内面を描写するものも多いだけに、ファンは自己解釈の上では彼の内なる世界に容易に入ることができる。
しかし、プライバシー開示に関して頑なな拒否反応をする浜田省吾を見て、初めて彼にも触れられたくない話題があるのだと理解する。
トレードマークとなっているサングラスにしても、ファンの前や雑誌に登場する場合は、絶対にそれを外さない。これはサングラスによって素顔公開を拒んでいるのだ。
普通の芸能人は、プライベートで行動するときは素顔を隠すためにサングラスで変装をする。それとは逆に、浜田省吾の場合はビジネスの時はサングラスをして、オフは素顔になる。テレビに同調しない姿勢にしても、このサングラスの活用法にしても、通常とは逆の行動をするところに浜田省吾らしさを感じる。
また、浜田省吾は「音楽制作をしているときは仕事という意識は無く、雑誌取材やカメラ撮影を受ける時は仕事だと感じる」と語ったこともある。
スタジオで創作や演奏をしているときはサングラスではなく、マスコミ取材には全てサングラスをしている。ここには「サングラス=仕事」という図式も成立しそうだ。
つまり、浜田省吾は仕事に入る時はサングラスをして、オフになれば外す。サングラスをすることで、仕事モードにスイッチが入るというわかりやすいメリハリだ。それはビジネスマンがネクタイを締めるのと似たような感覚なのかもしれない。
大抵のビジネスマンも、仕事とプライベートのケジメをつけるようにしていると思う。中には仕事と結婚をして、公私の境がボーダレスになっている人もいるかもしれないが。
遠山も自宅開業の個人事務所のため、そのあたりの境目があいまいになる時はある。仕事が一段落して、昼寝をしているときに電話で起こされると、さすがにまずいという意識は働く。
昔の栄養ドリンクのCMではないが、「24時間闘えますか」とはいかないものである。人は働く時は気合を入れて頑張り、仕事が終われば羽を伸ばすというシフトチェンジをして生活が成り立つ。
よく「家庭に仕事を持ち込むな」という酒席での会話を耳にする。これはいくら仕事が忙しくても、そのストレスを妻や子供に向けてはならない。それが家庭円満の秘訣だという人生訓だろう。
逆に「仕事にプライベートを持ち込むな」という上司の叱責を受けたことのあるビジネスマン諸氏も多いだろう。何を隠そう、遠山も企業勤めの新人の頃は、そんな教育的指導を受けてきた。
これは小さな意味では「仕事を早々に切り上げてデートに行こうなんて考えるな」という程度の話だ。大きな意味では「個人的な縁故を利用して私利私欲を満たそうとするな」という戒めだ。もちろん、遠山が小言を貰っていたのは前者の方だ。
そんな公私混同を避けるためにも、仕事モードに入る時はスーツを着るとか、作業着に着替える、社章を付けるといった儀式は有効なのかもしれない。すると、制服には批判もあるが一定の精神的役割は果たしていると言えよう。
それから、芸能人のプライバシー侵害問題にはピンと来ない人も多いだろう。だが、インターネットの巨大掲示板である2ちゃんねる等に、自分の職場での失敗や部署名等を晒されたことをイメージするとどうだろうか?
更に悪ノリをされて、自宅住所まで書き込まれた時には、誰でも堪忍袋の緒が切れるだろう。「テメー!訴えてやる。」という心境になるはずだ。
恐らく浜田省吾もそんな憤りに身をワナワナと震わせた出来事はあっただろう。自分が不快だと思う誹謗中傷や個人情報の暴露は、厳に慎むべきだ。
今日では、ネットを利用して誰もが公然と侮辱を受けるリスクは高まっている。そんな社会だからこそ、個人の良識が問われるといえよう。
現代社会にはストレスが蔓延している。ビジネスマンにとっては、今も昔も仕事によるストレスが最も悩ましいところだろう。
具体的には、上司や部下との人間関係であったり、残業や休日出勤、早朝からの通勤や転勤もあろう。給料が安いというのはかわいい方で、何も決まらぬ生産性のない会議や無意味なアリバイ工作のための成果報告書の作成なんかもイライラ感を募らせてくれる。
そんなストレスを発散するためには、ゴルフや野球等のスポーツで汗を流したり、食欲やアルコールに走ることもあるだろう。クレジットカードで衝動買いをしてしまうのもアリかもしれない。
仲間内で騒ぐときは、カラオケでガンガンやって憂さ晴らしというのもベタな解消法だ。
それで、カラオケで浜省を選曲するなら、そんな気分のときは「J.BOY」や「MONEY」あたりになるだろうか。
「J.BOY」では「仕事終わりのベルにとらわれの心と体取り返す夕暮れ時」とか「そしておれは心の空白埋めようと山のような仕事抱え込んで凌いでる」という歌詞あたりで力が入ってしまう。
「MONEY」では、「俺は何も信じない 俺は誰も許さない 俺は何も夢見ない 何もかもみんな爆破したい」と絶叫すると、最高に気分が良くなる。
また、浜田省吾のライブに参加すると、「Oh Yah!!」と絶叫した後に彼がこう語る。
「Oh Yah!!と叫んだところで何が変わるわけでもない。何も問題は解決しない。でも何故か気分は良くなるだろう。だから一緒に叫ぼう。」
こういう軽快なトークに乗せられ、会場の中はかつてのドリフの「8時だよ!全員集合」並みに何度も「Oh Yah!!」が連呼される。(「8時だよ!全員集合」の掛け声は「オッース!」だったが。)
カラオケやライブに行っても、浜田省吾が言うように問題がそれで解決するわけではない。ただ、その場で気が晴れるだけである。
それでも、日々鬱積するストレスが多少でも和らぐことは確かだ。
このストレスというのは物事の受け取り方で変化するもので、あるプロジェクトを任された場合に、それを負担に感じるのか、それとも奮い立つのかで180度異なった精神状態となりうる。
だから、最初は憂鬱に感じていた仕事も、同僚とカラオケに行くことによって、楽しく思えるような劇的変化をすることもある。もっとも、カラオケの18番を奪い合いあって血の雨が降り、益々職場の人間関係が悪化する可能性もあるわけだが。
職場というのは集団行動の場だから、一定のルールに拘束されるのは仕方が無い。わがままは通らないので、仕事の目的を達成する範囲で行動の自由は制約を受ける。そこは社会人として受け入れなくてはいけない。
しかし、理不尽な事件や納得いかない処遇というのも、残念ながら起こりうる。そんな場面に遭遇すると、ストレスの臨界点に達してしまうこともある。
その状況が長期化すれば、精神的に不安定となり体調まで崩してしまうことも多い。ひどい場合は、鬱病になったり過労死につながったりもする。
そこまで嫌になってしまった職場なら、辞めてしまえばいい。それができるなら、ストレスなんて溜まらない。
その仕事や職場が嫌で嫌で辞めたいと思っても、辞めることができないときにストレスが極大化する。
つまり、嫌な仕事を我慢しながら続けざるを得ない状態が最大のストレスともいえよう。
話は変わって、バブル後のリストラ旋風が吹き荒れた時期を経験し、もはや終身雇用は幻想だということを誰もが肌で感じ取っている。
公務員ですら合併や合理化で人員削減が進んでいる。都市銀行が破綻し、大手証券会社も破産するのも目撃した。無条件で安泰な勤務先なんて存在はしない。
そんな終身雇用が期待できない職場で、心底から嫌だと思う会社に依存する理由は何であろうか?
それは、次の働く場所が見つからないということが大きな原因といえよう。
では、嫌だと思っている職場でも、「辞めようと思えばいつでも辞められる」という心構えができていればどうであろうか?
恐らく、精神的ストレスは格段に軽減するに違いない。命令口調の上司にも、口ごたえの一つもできる余裕が生まれるだろう。
そのためには、「辞めようと思えばいつでも辞められる」と思えるだけの裏付けが必要となる。
つまり、自分には技術があり、その技術があれば次の職場はそれほど苦労しなくても見つかるだろうという根拠が必要だ。
しかし、技術なんて簡単には身につくものではない。もっとも手っ取り早いのは、今の職場の仕事に精通し、同業であればどこに行っても通用するというスキルを積んでおくことだ。会社が資格取得を奨励しているなら、自分のために積極的に取っておくべきだろう。
そのためには、一定の修業年数が必要だ。石の上にも三年とは、よく言ったものだ。
現在の職場では特に何の技術も身につかないという状況であれば、余暇時間を利用して自分で努力をするしかない。
そうして自分の技術に自信が持てるようになれば、気がつく頃には会社は恐くなくなっているから不思議なものだ。
ストレスに打ち克つには、適度に息抜きをしながら、職場のスペシャリストとして自立していくことだ。
浜田省吾のファン層は、ティーンエイジャーから熟年世代まで幅広い。浜田省吾自身は1952年生まれだから、2006年4月現在では53歳だ。
当然ながら同世代のファンも数多く存在し、その上の年齢層にも支持されている。
浜田省吾より年上のファンといえば、年代的には戦後のベビーブーム世代であり、いわゆる団塊の世代である。
この団塊の世代が2007年から2010年の間に60歳に達し、その人数は300万人とも言われる。60歳といえば、多くの企業や公務員の定年退職の年齢だ。
短期間に大量の退職者が発生するので、その補充は新卒だけでは埋めきれず、人事担当者を悩ませることになる。
これを労働市場の2007年問題と呼ぶ。
バブル崩壊以降の雇用抑制が続いたので、どの職場も余剰人員はなく、ギリギリの状態で回っているのが実情だろう。
そんな中で同時多発的に定年退職者が発生するのだから、現場は悲鳴をあげることになってしまう。
しかも、折からの少子化進行で新卒の人数は減少傾向だ。補充は簡単ではない。
また、製造業の現場では、団塊の世代は貴重な熟練工となっている。日本の精密加工を支えてきた熟練技術は、単に若年層を補充するだけでは継承されない。
このような2007年問題に対して、産業界は定年退職後も雇用延長を図ることで対処しようとしている。
しかし、経営再建の名の下に、リストラや賃金カットに耐えてきた団塊の世代の中には、定年後の継続勤務に関しては複雑な感情もあるだろう。
それでも、団塊の世代に対する社会的要請は高いと言える。
では、晴れて定年を迎える団塊の世代のビジネスマンには、リタイア後にはどのような選択肢があるのだろうか?
最も羨ましいのは、退職金を得て充分な貯蓄をし、経済的な不安が無い状態で趣味に生きる生活だろうか。これは本当にあやかりたいものだ。
ちなみに、2007年からの3年間で動く退職金の総額は、80兆円にも達するという試算もある。
他にはボランティアや地域貢献に励む人々もいるだろう。地域の世話役等で、新たな才能を発揮する場面もあるかもしれない。
仕事を継続する場合も、勤務していた会社の定年延長に応じてもよし、気分を変えて他の会社で働くのもいいだろう。
かつてのリストラとは逆の風が中高年に吹くかもしれない。
こうして考えてみると、団塊の世代のリタイア後の人生は、明るく熱いものになるかもしれない。
かつての定年退職後の侘しいイメージは、払拭される可能性もある。
しかし、問題が無いわけではない。
熟年世代にも重荷はのしかかっている。住宅ローンが定年までに払い終えられない人も多いだろう。同様に遅くに子供ができた人は、高等教育の学費支払いに頭を抱えなくてはならない。ひょっとしたら、子供がニートになっていて、その自立を促すために家庭内でひと悶着あるかもしれない。
それから、親が存命であれば介護の問題も抱えているだろう。
必死の思いで長い間働いて老後の資金を貯めても、それを狙う詐欺師も存在する。巧妙な口車に乗せられて、数十年の集大成とも言うべき貯蓄を、ほんの数ヶ月で掠め取られるリスクもある。具体的な手口については、別の章で詳細する。
そこには古きよき時代の日本の美徳は通用しない。
それでも、戦国の世で人生50年と言われた頃を考えれば、今の熟年世代は熱く生き生きとしているのではないだろうか。
団塊の世代が高度経済成長期を演出し、バブルとその崩壊を経て、豊かなリタイアを迎えたのだから、まだまだ何かをやってくれるという期待はかかる。
何しろ80兆円もの資産を手にするのだから、周囲もその動向が気になって仕方がない。
また、熟年世代に属する浜田省吾は、今でも現役のロックスターであることは間違いない。そのライブに熱狂する10代の少年少女も存在する。
これはとんでもない偉業だと思う。浜田省吾がデビューをした1976年頃に、ロックというジャンルの音楽で生計を立て、その30年後もライブでティーンエイジャーを夢中にさせるなんていうことを、誰が想像できただろうか。
もちろん熱狂的なファンは、熟年層にも多い。
余談だが、遠山の微かな記憶では、初めて浜田省吾の存在を知ったのは小学生の時で、小学館の「小学六年生」という雑誌の情報からだった。その記事の中で「浜田省吾のライブを座って聴こうなんてとんでもない」というキャッチコピーがあったように記憶している。
子供心に「浜田省吾って、観客を座らせないんだ」なんて思ったものだ。そんなライブを30年も継続している浜田省吾には、本当に頭が下がる。
(追加すると、初めて浜田省吾の曲を聴いたのは、大学に入学した18歳の時だった。)
浜田省吾はライブ一徹で頑張っている。同世代の熟年層も、会社を定年退職したくらいで老け込むはずは無いだろう。
日本を経済大国に導いてきた原動力は、間違いなく現在の熟年層だ。まだまだパワーのあるところを随所で魅せてくれるはずだ。
浜田省吾のライブ・ツアーは、当然ながらファンには熱烈に支持されている。しかし、バンドのメンバーやスタッフには過酷な日程となるようだ。
ツアーというからには、日本中の主要都市や地方都市を巡回する。過去には、バンドメンバーは26泊27日の旅というような状況が日常となってしまうこともあったそうだ。スタッフに至っては40泊なんて事態にもなる。
これでは自衛隊の潜水艦乗りのようなライフスタイルになってしまうだろう。
そのようなツアーが定期的に続けば、当然ながらメンバーやスタッフ個々の家庭生活に影響がある。
アパートを引き払うことを余儀なくされたり、恋人と別れたメンバーもいるという。
実に過酷なライブ・ツアーではないか。
それでも、ライブ・ツアーである「ON THE ROAD」は長く続き、メンバーやスタッフも楽しんでいる様子はファンクラブ会報から伝わってくる。
そもそもファンを楽しませるライブで、主催者が苦痛のみでやっていたら、興行として成立しないだろう。
バンド・メンバーやスタッフは、ライブ・ツアーという共通目的に結束する運命共同体であり、そのチームワークがライブという事業の成否を分けると言えよう。
そんなバンド・メンバーに対する浜田省吾の認識は、次のとおりだ。
「いっしょにやってきた人たちは、僕の曲がすごく好きでやりたいからやったというんじゃないと思う。
そんなに話は美しくないし、僕だって特に昔は、みんなが“これはいい曲だ”と思えるような曲をたくさん書いてたとは思えないからね。(中略)
その中で、僕といっしょにやるということは、ある部分では仕事だし、経済的なもの。(中略)
あるソング・ライターがいてそのバッキングでレコードをつくったりステージをやるミュージシャンというのは、基本的に個人ですよ。若い頃はそれ以上のものを望んでいたこともあるけど、それは望むほうが無理というもの。ただ、いいミュージシャンはどんなものにも全力を投球するし、楽しむ。それが観客にも伝わるでしょう。」
「セッションをやるミュージシャンというのは、みんな自分の夢を持ってる。でもそれは別にして、どれだけそのときに全力で、いいバイブレーションでやってくれるかなんです。お仕事っていうふうに見える人もいるのね。僕が全力をかけているのに後ろで仕事をしている人がいると雰囲気が醒めるでしょう。」(以上「ROAD&SKY 60号」より抜粋)
つまり、いいライブをつくるためには、良いミュージシャンを揃えなくてはならない。しかし、良いミュージシャンは個人の目標があり、いつまでもライブに協力してくれるとは限らない。
そうしたシビアな現実を認めつつ、目前のライブに全力投球を続けるわけだ。確かに独立を考えるくらいの意欲を持った個人でなければ、音楽の才能を研ぎ澄ますことはできないかもしれない。
事業を継続するという観点で考えれば、いずれ独立を考えているような人材をチームの中に入れるのは、和を乱す行為にも思える。
しかし、チームを全てイエスマンで揃えてしまえば、そこは指示待ち人間の溜まり場となってしまい、組織の活力は生まれてこない。
継続させることを自己目的化してしまうと、その組織は顧客サービスという視点は欠如し、自己防衛に向かうようになる。その先に待つのは衰退だ。
一方、乱暴のようにも思えるが、独立志向が強い人間でチームを組めば、その瞬間に発揮するパフォーマンスは大きくなる。
その時点で最高の顧客サービスを提供することだけを考えれば、外部のエキスパートを呼び込むのも有効となろう。
本当に強い組織というのは、構成員に滅私奉公を求めたり、上位下達で縛りをかけたりすることでは作り上げられない。
組織の一人一人が確立した個性を持ち、その優れた個性を共通目的のために結集させる過程が大切だ。もちろん、個性の強い人材でも、組織に所属する間はルールに従わせる必要はあろう。
理想を言えば、優れた個性の集合体をカリスマのリーダーが強烈な理念の下にまとめていくのが最適だろう。しかし、現実にはそう簡単にはいかないことは誰もが承知している。
自分の職場や所属している組織をふりかえれば、マニュアルで縛らないと行動しない人も多いかもしれない。何の意味も理念も無く、無理難題を押し付けることしかしないリーダーも存在するだろう。
遠山もサラリーマン生活は13年ほど経験したが、組織の中の人間関係は難しいものだと痛感してきた。個人の努力では変えようが無いと思える問題は多い。
その結果、独立してフリーになることで、職場の人間関係からは開放されている。今のところは部下が欲しいとも思わない。(もちろん、上司もいらない)。
しかし、様々な局面で集団や組織に属することは多いものだ。
強い組織をつくることを“理想論”だと決め付けてしまうと、そこからは何も生まれない。一人一人が自己の能力を高めることに関心を持ち、組織がそれを支援しつつ構成員の意欲を引き出す。そんな循環を生み出せる人が、真のリーダーといえるのではないだろうか。
浜田省吾のファン層は実に幅が広い。ライブ会場に行けば、下は親に連れられた小学生から、上は70歳近くの年配の方まで、様々な世代のファンに出会うことができる。
それだけ世代分布の広いロックのライブというのも珍しいのではないだろうか。
どうしてそれほど支持層が広いかといえば、やはり30年間の音楽活動で蓄積してきた曲のバリエーションの豊富さだろう。
その30年の間に、浜田省吾は23歳から53歳となった。それぞれの時期に、その世代の視点で真摯に曲つくりをし続けた結果、10代から60代までの世代が共感する曲のラインアップが出来上がったと言えよう。
「19のままさ」では、予備校生の儚い恋愛を唄い、学生や若い社会人の共感を得ている。「星の指輪」では、子供のいる夫婦が束の間のデートを楽しむ様子を描いた。「君と歩いた道」では、老境に達した視点から人生をふりかえる。
このように浜田省吾の曲には30年分の蓄積があるのだ。これはどんな大ヒット曲を生み出すミュージシャンでも、簡単には真似のできることではない。
10代のミュージシャンが50代の境遇を歌にしても説得力は無い。逆に50代のミュージシャンが新たに10代の心情の歌をつくってもリアリティに欠けるだろう。
やはり、浜田省吾がそれぞれの時期で、そのときの思いを真剣に曲にしてきたから、例え古い曲であっても支持されるのであろう。
例えばアルバム「J.BOY」を現在の高校生や大学生が聴いたとしても、充分にインパクトある仕上がりになっている。
だから、10代や20代のファンも新たに獲得することができているのだ。
ところで、音楽CDのメインの購買層は10代だという。かつて10代であった現在の30代や40代の世代は、昔はよくアルバム購入をしていたはずなのに、現在はあまりCDを買わないらしい。
遠山も現在30代だが、確かに浜田省吾のアルバムを除いては、音楽CDを買うことは少なくなった。
そのためか、音楽の制作会社は10代をターゲットとしたマーケティング活動を展開している。
必然的に若いミュージシャンが重宝され、そのミュージシャンが加齢していくと賞味期間切れのような扱いをする。
ミュージシャンが年を重ねたとき、同一世代の共感を呼ぶような曲つくりをするのが、何だかタブーとされるような雰囲気もある。
これはマーケティングの功罪ともいえないだろうか。
確かに統計的に裏付けのある10代を対象とした曲つくりは、マーケティング的にセオリーなのだろう。
しかし、それがウケるからといって、長期間ずっと同じ手法で特定マーケット層に向けた商品(曲)供給を続けたら、やはり人間は飽きてしまう生き物なのだ。
10代が成長して20代や30代になったとき、自分の気分にあった音楽を耳にする機会がなければ、CDを買おうとは思わなくなってしまう。
つまり、若年層を対象としたマーケティング活動が、人口比の多い30代以上の年齢層を置き去りにしているともいえよう。
短期的には10代の購買層への訴求は正解かもしれないが、長期的にはより大きな市場を喪失していると言えるかもしれない。
折りしも、日本の人口構成は少子高齢化に向かって突き進んでいる。この先、10代のマーケットは益々縮小していくのだ。
都心部であっても小学校の学級数は減り、統廃合が進んでいる。地方になると、もっと事情は深刻だ。
そんな縮小していくマーケットに照準を固定し続けるのは、やはり正気の沙汰ではないだろう。若手のシンガー・ソング・ライターが登場して、ヒット曲を連発する様子を伝える歌番組には、かつての太平洋戦争末期の大本営発表を連想させられる。
ああ、音楽制作者側も必死なんだなと。もちろん、遠山はリアルタイムで大本営発表を聞いたことは無いわけだが。
もちろん、今後の人口動態などは音楽制作会社はキッチリ把握している。そんなことは言われなくてもわかっている。30代や40代を対象とした曲を、それなりのドラマとタイアップしてプロモーションをしていると主張するだろう。
それでも30代以降の世代は手強く、なかなかCDを買おうとしないと弁明するに違いない。
問題は根深く、30代以降の年齢層に支持されるミュージシャンを育てる努力を怠ったのではないだろうか?
10代の小娘に「オヤジ!頑張れ!」という応援歌を作って貰ってもありがたくはない。では同世代のミュージシャンはというと、バンドを解散してしまったり、アルコール依存の末に自殺してしまったりして、多くは現役でなかったりする。
幅広い支持層を獲得している浜田省吾に頼りたくとも、浜省はテレビに出ないというのが定説になってしまった。
新しく30代や40代にウケるミュージシャンを育てるには時間がかかる。
それ故に、浜田省吾は30年間という音楽活動の蓄積が最大の武器とも言えよう。このキャリアは誰にも真似ができない。
ビジネスにおいても、その時期に応じて積み重ねてきた商品開発や顧客からの信頼が、何にも変えがたい財産となるはずである。
やはり“継続は力”なのである。
浜田省吾の所属事務所であるROAD&SKYは、公式なファンクラブも運営している。普通、ファンクラブ入会のメリットと言えば、真っ先に思い浮かぶのはライブ・チケットの優先予約ではないだろうか。
人気ミュージシャンのライブ・チケットは、競争率が高くて簡単には確保できるものではない。イベンターのチケット発売日には、予約のための電話回線が繋がらず、何時間も待たされることは珍しくないだろう。
そういう事情を知っているからこそ、ファンはファンクラブにチケットの優先予約権を期待する。
ミュージシャン側もファンクラブの優先予約で入場者数を確保して、囲い込みができれば都合が良いだろう。そうすればライブの収支予測も立てやすくなる。
しかし、浜田省吾の公式ファンクラブはチケットの優先予約をしていない。ホームページのファンクラブ入会案内にも、「チケットの優先予約はしません」とハッキリ告知している。
これを意外と感じる人は多いだろう。遠山も過去に幾度と無く次のような会話をしてきた。
遠山「今度、浜田省吾のライブがあるんだけど、なかなかチケットが取れなくて困るんだよね。」
友人「それなら、ファンクラブに入会してチケットを取ればいいじゃん。」
遠山「それが、ファンクラブはチケットの優先予約はしてくれないんだよ。」
友人「エッ!! 信じられないな。そんなのファンクラブのメリットは無いよねえ。」
恐らく浜田省吾ファンであれば、そんな話題を耳にした経験はあるはずだ。
このような、ある意味では非常識とも言えるファンクラブにチケット予約優先権を認めない理由を、浜田省吾は次のように解説している。
「ファンクラブにチケット優先権を認めると、現状ではファンクラブの会員しかライブに参加できないことになってしまう。ファンにはいろいろな人がいて、初めて浜田省吾の音楽に興味を持つ人もいる。ファンクラブ会員しかライブに参加できないことにしてしまうと、そういう人がライブに来れなくなってしまう。それは健全な状態ではないと思う。」
ここにも浜田省吾の人柄と言うか哲学を感じ取ることができないだろうか?
ファンクラブが優良顧客となり、イベンターを通さなくてもチケットが完売できれば、ライブ運営もいくらかは楽になるだろう。
そのメリットを捨ててまで、全てのファンが公平にチケットを取るチャンスを提供しようというのだ。
その平等や公平を求める意識は、さすがと言うしかない。
翻って、90年代以降の企業の不祥事を振り返ると、悲しいかな日本には不平等感が充満していることに気が付く。
古い話になるが、1991年には大手証券会社が自社の優良顧客に対して、株取引の損失補てんや利益の追加をしていたことが発覚した。小規模取引の個人客が株取引で損失をしても、その補償がされることはありえない。
というか、株取引に関する損失はクライアントの自己責任というのが原則のはずだ。しかし、優良顧客(総会屋だったりするのだが)に対しては原則を曲げて損失補てんを続けたことが明るみになった。(この損失補てん事件を起こした山一証券は、1997年に破綻してしまったわけだが。)
それから、公共事業に関する談合事件は、昔から現在まで途絶えることなく続いている。大手の業者が落札順を決めて、その順番通りに仕切られる。そして、建設業では工事を下請けに丸投げというのもお馴染みのパターンとなっている。
巧妙なところでは、仕様作成やコンサルタント業務の入札を格安で落札し、その後の本事業の仕様を自社に有利に設計するケースも後を絶たない。このようなコンサルタント業務入札では「1円落札」なんてことも話題に上る。
このように、大手企業や公共事業ですら、平等や公平という原則を見失うこともある。もちろん、ビジネスの世界では戦略として、優良顧客やリピーターに優遇策をとるのは間違いではない。
しかし、利益追求のあまり法令違反をすることに躊躇いを感じなくなるようでは問題だ。それではコンプライアンス(法令遵守)に対して不感症と言われても仕方がない。
「危ない橋を渡る」とか「やったもの勝ち」という、グレーな仕事ぶりを賛美するような風潮は実に危ういものなのだ。
法令の網をくぐり抜けて利益をあげたとすると、それを維持するには法令違反を継続しなくてはならない。そんな事を続けていれば、いつかは綻びが出て破滅への道が待っている。
そのようなグレーな仕事は、組織ぐるみで継承されることも多い。そんな環境に身を置いていると、自分のやっていることが法令違反であるという自覚が薄れることもあるだろう。
しかし、法に触れることに慣れが生じても、その罪は決して帳消しにはならない。慢性的な法令への抵触行為が続けば、いつかは必ず手痛いしっぺ返しが来るものだ。
そこで、事業の長期継続性ということを真剣に考えるなら、法令に沿った内容で営業を行い、その上で適正な利益を出すという仕組み作りに励む必要がある。
そのためには顧客からの信頼を得る必要があり、公平な対応とコンプライアンスの徹底と言うのは最低条件となるだろう。その姿勢を常に示し続ければ、顧客が猛烈なファンとなってくれるはずである。
音楽においてロックンロールの対極にあるのがクラシックではないだろうか。ロックが観客も参加して大騒ぎする“動”の音楽で、クラシックは落ち着いた聴衆が聴き入る“静”の音楽といえるだろう。
通常のロックコンサートであれば、そこで使用される楽器はギター・キーボード・ドラム等というのが一般的なイメージだ。
チェロ・ビオラ・バイオリンといういわゆるストリングスは、普通ならクラシックの楽器だ。しかし、浜田省吾のライブツアーであるON THE ROAD 2001では、そのストリングスを同行してバリバリのロックに取り込んだ。
ツアーの当初はライブの中でバラードを3曲演奏するだけの役割だったストリングスだが、ライブの回数を重ねるうちにヒップホップやロックまで参加して、新境地を披露するようになった。
ストリングスメンバーの4人は東京芸術大学出身の女性で、アカデミックな才媛たちだ。ロックや歌謡曲とは縁遠い教育を受けてきたはずだ。それでも浜田省吾のロックライブに参加して楽しそうに演奏する姿は印象的だった。
なぜ、ロックのライブにストリングスを取り入れたのかというと、「なかなか生の弦楽器の音をコンサートで聴く機会がない地方のファンに楽しんでもらいたくて」と浜田省吾は語っている。(日経エンタテイメント 2000年2月号より)
その目的はファンへのサービスということだろう。
既に自分たちで確立したロックライブのスタイルでも満員御礼となるわけだから、その手法を継続するのが無難な気はする。
だが、そこに気の緩みとかマンネリの危険性が潜む。安定的な評価はマンネリと紙一重と言えるかもしれない。
そこで、意外とも思える取り合わせで、より高いレベルでのファンサービスを図る意欲はさすがだ。
このようなマンネリとの格闘は、外食産業でも垣間見ることができる。定番商品だけで充分に人気店となっても、年に何度かは新メニューを登場させる努力をしているものだ。大抵はおいしさに納得がいくメニューだが、時には外すこともあろう。湯豆腐にイチゴジャムをトッピングするようなインパクト勝負に出て、失敗するのも愛嬌かもしれない。
もちろん、新メニューの追加など一切無しに繁盛している専門店もある。伊勢の赤福もちのように、それ一本で営業を続ける老舗は存在する。だが、それは長い歴史で培った信用であり、一朝一夕で築き上げられるものではない。
やはり、大多数のビジネスマンにとって、新しいサービスや新企画には絶えず挑まなくてはならないものだろう。
そんな新しいものへのチャレンジは、疲弊しきった組織にはハードルが高い。組織の内部で風通しが悪く、不信感がうごめくような人間関係では、冒険は許されない。
浜田省吾のライブで、ストリングスがヒップポップやロックに参加するようになったのも、ストリングスのメンバーと従来からのミュージシャンが深く熱いディスカッションを交わしたからだ。
その際に、浜田省吾が独善的であったら、ロックにまでストリングスが加わるコラボレーションは生まれなかっただろう。
それはミーティングで本音を語り合える環境作りに成功したということだ。ただ、そのような意見交流が出来るようになるまで、数ヶ月は要したようだ。真に深いディスカッションができるようになるには、ある程度の時間は必要だ。
何か新しいことに挑みたくても、組織の中で自由に物が言えない雰囲気があれば、どうしてもその組織の活動は停滞してしまう。
そんな組織が嫌だと思いつつも、そこからは離れられないのがサラリーマンの辛いところだ。
ただ、諦めてしまえばそこで終わりである。その組織に所属している間は、人事異動でもない限り停滞した雰囲気に身を委ねる事になってしまう。
それを変えるには、誰かが一歩踏み出さなければ始まらない。
強い組織というのは、新しい企画について冒険ができるものだ。その前提条件として、事業の見通しなどを本音で語れる人間関係が必要だ。各自が方向性について意見を戦わせても、互いの信頼感を見失うようなことがなければ本物と言えよう。
浜田省吾の歌にはアメリカへの思いが込められているものが多い。例えばアルバム「J.BOY」では「アメリカ」というタイトルの曲も存在する。
その「アメリカ」の中で「映画の中のアメリカンドリーム」とも唄っている。
ただ、浜田省吾の思いには、単なるサクセス・ストーリーとしてのアメリカンドリームだけではなく、もっと複雑な感情があるような気がする。
それは浜田省吾が高校生のときに、呉の弾薬庫前の反戦デモに参加し、警官隊と対峙したときに感じた緊張であり、その米軍基地向けに放送されていたFENから聴こえるロックやR&Bの軽快なリズムでもあっただろう。
当時はベトナム戦争の最中で、多感な若者の間には反戦気運が高まっていた。特に政治思想があったわけではない高校生も、反戦デモに参加するのは珍しいことではなかったという。
そのような単に平和を望むだけのデモ隊に対し、警官隊を使って威圧する姿が、アメリカの横暴と映ったことは容易に想像できる。
一方でFENから流れるロックやR&Bには純粋に憧れを抱き、ギターでそれらをコピーした。また、浜田省吾の初恋はロスから来た17歳の女の子であり、18歳であった彼は彼女の故郷にも興味を持っただろう。
つまり、圧倒的な軍事力を背景に服従を強要する世界の嫌われ者としてのアメリカと、優れたミュージシャンや映画俳優が活躍する自由の国としてのアメリカが、浜田省吾の中で混沌として同居していたのだ。
そのためアメリカの音楽を聴いて、その文化を積極的に享受しながら、米軍基地に対しては嫌悪感を抱くという葛藤を味わった。
このような感性は、実は浜田省吾だけの問題ではなく、現在の日米関係でもそのままあてはまるのではないだろうか?
経済や文化の交流という面では、日米は密接な関係にある。もちろん、政治や軍事面でも同様だ。
アメリカが提供するハリウッドの娯楽やIT技術は好きだが、湾岸戦争時の戦費調達や工業製品の輸出規制など小うるさいところは嫌いだという人は多いだろう。
しかも、うるさいだけでなく、このような無理難題を吹っかけてきたときには、力づくでそれを押し通してしまう。まるでドラえもんに出てくるジャイアンのような厚かましさだ。
それでも、アメリカが優れている点は多いことを認め、アメリカとの関係は良好に保ちたいというのが平均的な日本人の感覚ではないだろうか。
実際に経済やIT、マーケティングの分野では、アメリカの技術は進んでいる。アメリカで流行したことが1~3年遅れで日本に伝播するという現象は、いまだに日本はアメリカの技術を取り入れてカスタマイズすることで成立しているという事実を示している。
例えば、小売業であればウォルマートの事例研究に熱心で、POSの活用等もアメリカ発の技術を日本でローカライズさせて発展させたものだ。コンビニエンスストアやフランチャイズ契約という事業形態もアメリカからの輸入物だ。
ITの分野になれば、更に露骨となる。パソコンに関する主要技術は、ほとんどアメリカが先導している。
OSの分野ではWindowsを開発するMicrosoftの独壇場だし、ワープロ・表計算のオフィス・ソフトも同様だ。
CPUはIntelの独占状態と言えよう。マッキントッシュも国産機ではない。
インターネットの世界でも、検索エンジンのGoogleとYahooはアメリカ産だ。この巨大検索エンジンと連動して成長していく広告ビジネスも、アメリカに持っていかれるだろう。
ちょっとアングラ色の強いビジネスも、アメリカから輸入されてしまう。最新の健康器具や資産運用のビジネスなど、いわゆるマルチ商法のネタ探しは、もっぱらアメリカで物色されている。(マルチ商法自体は合法だが、営利優先のあまり販売トラブルが多いことは否定できない。)
このようにアメリカの先進技術を輸入して、それを日本市場向けにアレンジしてリリースするのが、戦後から続く一つの商売成功の方程式となっている。
この方程式は現在でも有効だから、進歩が無いと言えるかもしれない。
もちろん、自動車や精密加工、アニメーションなど、日本が世界に誇る技術分野も存在する。
しかし、このような先進分野は安価な労働力を求めて海外移転が止まらない。日本国内では、世界最先端分野での若者の就労機会が減少し続けている。
来るべき海外赴任に備えて、誰もが英会話学習に余念が無いという状況には、何か皮肉を感じてしまう。
本来であれば、日本の先進分野をどんどん拡大していくのがベストだ。だが、実際にはIT関連技術のように、大きく遅れをとった分野が存在するのが現実だ。
その現状認識を正しく持ち、立ち遅れた分野に関しては真摯に学んで、いつかはそれを克服していく努力が必要だ。
浜田省吾はアメリカに対する憧憬と嫌悪感を共存させつつ、決してその片方に傾くことはしなかった。
良いものは良くて、悪いものは悪い。その価値判断を個人の中で適切に消化できれば、良いエネルギーのみを吸収できるはずだ。