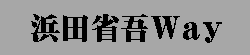
2006年04月
ファン・サイトの浜田省吾Wayです。
浜田省吾のデビュー30周年時に公開の個人ブログ。【祝・40周年】
2006-04-21
僕がこのページを書いている2006年4月21日は、浜田省吾のソロ・デビュー30周年となる記念日です。
流行廃りの激しい音楽業界で、30年も現役で活動を続けることは偉業と言って良いでしょう。
多くのファンが浜田省吾氏に「素晴らしい曲をありがとう」「これからも頑張って」と言いたいと思います。
僕もお祝いの言葉をここに書きます。
浜田省吾さん、たくさんの感動をありがとう。
30周年ってスゴイことですよね。
現役であり続けることが、何より素晴らしいと思います。
まだまだライブで楽しませてください。
投稿者 : 04:57 AM
2006-04-12
浜田省吾は現在ROAD&SKY(ロード・アンド・スカイ)という事務所に所属している。デビュー時にはホリプロダクションに所属していたが、1983年4月1日に独立してROAD&SKYを設立した。(社長は愛奴時代のベーシストだった高橋信彦が務めている)。
このROAD&SKYを設立して独立するきっかけとなったのは、ライブに関するホリプロとの認識の違いにあったようだ。ホリプロは音楽業界のセオリーに従って、レコードのセールスを第一と考え、ライブについてはレコードを売るための販促活動の一手段と考えていたようだ。
浜田省吾自身は、それまでのライブ活動に手応えを感じていて、ライブを自らの音楽活動の中心にしたいと思ったのであろう。そこに互いの認識のズレが生じ、浜田省吾は独立する必要性を感じたようだ。
だからといって、ホリプロと浜田省吾の間に軋轢が生じたわけではない。ファンクラブ会報「ROAD&SKY 61号」の中で、「ホリプロの堀社長には、独立を理解してもらって今でも感謝している」と語っている。
金銭や人間関係で揉めれば、所属事務所とミュージシャンの間で法廷闘争も含めた泥仕合になる事例もあるが、浜田省吾の場合はそのようなトラブルとは無縁だった。それは浜田省吾の音楽に対する姿勢が明確で、ホリプロもその信念に納得できるところがあったからだと想像できる。
晴れて新事務所を作って独立することになった浜田省吾は、事務所名をジャクソン・ブラウンのアルバム「LATE FOR THE SKY」の5曲目に収録された「ROAD&SKY」から引用した。
このROAD&SKYという名前に込める思いについて、浜田省吾は次のように語っている。
「ROADという言葉は、ON THE ROAD、つまり永遠に続くツアー。」
「SKYは無限に広がる音づくり。つまりレコード制作。」
ライブ・ツアーと音楽製作をイメージして、それを事務所名にするのは浜田省吾らしい。スタッフやファンに対して、ライブと音楽製作を通じて活動していくというメッセージが明確にされている。
理念や目的がハッキリしていれば、周囲も安心するものだ。カリスマやリーダーと呼ばれる人達は、活動の理念を熱く語らねばならない。その義務に対して、浜田省吾は答えを用意していたのだ。
しかし、独立直後のROAD&SKYには難問が立ち塞がっていた。それは1983年8月に、福岡県の海の中道公園で大規模な野外コンサートを企画したことだ。
ライブで生きていくことを宣言した浜田省吾とROAD&SKYにとって、これは失敗が許されないイベントだった。集客が思うようにいかなければ、大赤字となり事務所がいきなり潰れるリスクもあった。
傍観者の立場で眺めれば、何も独立直後の資金の厳しいときに、事務所の命運を賭けるような冒険をしなくてもと思ってしまうところだ。
それだけ浜田省吾はライブにこだわり、大規模な野外コンサートを成功させることで道を切り開きたかったのだろう。
結果として、この海の中道公園の野外ライブは18,000人を集客し、大成功となった。この年の浜田省吾は、138回の公演を行い約258,000人を動員している。その7%近い集客を海の中道で達成したわけだ。このときの感動は忘れられないと、様々なインタビューで答えている。
このようなイベントを成功させるためには、スタッフの協力は不可欠だ。資金や日程に余裕は無く、関係者がどれだけ本気で尽力できるかにかかっている。
無謀ともいえる企画を押し通すには、周囲やスタッフの理解無しには進まない。
どんな職場でもそうだが、無茶な計画や業務命令は従業員のモチベーションを低下させる。例えば、月末締め日の直前になって、「今月の予算は200%上方修正する」と言われたらどうだろうか?
ほとんどの人は、その時点で「終わってるな」と冷笑するだけだろう。実際に上方修正された新目標に対して努力するわけは無い。
同じように、一歩間違えれば浜田省吾のライブ優先の活動は頓挫するリスクはあったと思う。それを回避して、ライブの帝王の座を獲得することになったのは、スタッフの努力であり、リーダー(またはカリスマ)としての浜田省吾の力量であろう。
人は無謀な目標や計画にはついて来ないが、理念に共感できるところがあれば動くものだ。単に上位下達で目標を押し付けるのではなく、理想を語り、その実現への道筋を予感させるリーダーがいる組織は結束が強固となる。そんな組織は常勝集団となるだろう。
ただ、浜田省吾も何の見込みも無く無謀な大規模野外ライブを企画したわけでは無いだろう。前年までのライブの手応えを感じていて、この流れなら冒険はプラスに作用するという読みはあったはずだ。
何の根拠も無い(マーケティング調査に基づかない)冒険であったなら、周囲を説得できずに企画実施すらできなかったであろう。
あらゆる組織のリーダーは、現実の成績をベースとして把握しながら、将来を向いた理念を語らなくてはならない。そして、その理念に共感するスタッフに恵まれたなら、リーダーは組織内のカリスマとなり、事業の成功は約束されるだろう。
投稿者 : 03:29 AM
浜田省吾といえば、数多くのラブ・ソングもリリースしているが、メッセージ性の強い歌を作るシンガーという印象も強いと思う。実際に、戦争や平和をテーマにした曲は多い。
そうしたメッセージ性のルーツを、過去の学生運動にあるのではと邪推するファンもいるが、浜田省吾自身はそれを否定している。
確かに学園紛争が盛んな頃の神奈川大学に籍を置いていたことは事実だが、ストによって講義が行われなかったり、学生の派閥抗争によって荒廃する大学に嫌気が差し、1年半で退学している。
浜田省吾は平和に対する思い入れの原体験として、広島生まれであることを挙げている。それは小学生の時に原爆資料館を見学したときの衝撃であったり、被災者救助に駆けつけて二次被爆をした浜田の父親の体験談を聞いて、戦争は嫌だと強く思うようになったことであったりする。
そうした思いが底流にあり、反戦や平和をアピールする歌詞を多く書いている。そうした曲からは、その鋭い洞察力に圧倒されるばかりだ。
1986年に発売されたアルバム「J.BOY」に収録された「NEW STYLE WAR」では、「地下から地下へ運ばれたBOMB(爆弾) 国家に養われたテロリスト」と風刺をしている。
また、同時期のインタビューでは、「日本は平和だし、世界も今は、ほら、ソ連とアメリカも一時の緊張感ってなくなってきてるでしょう?だけど、これからの戦場っていうのは国境で区切られている戦場ではなくてね、いきなり東京の丸ノ内のビルが爆破される戦場かもしれないし、病原菌や自然破壊やそういったことが新しい戦場になるわけで、ある意味では今まで以上に平和な時代ではないんじゃないかなって。」(「青空のゆくえ」ロッキングオン)と答えている。
ちなみに、猛毒サリンを使ったオウム真理教の無差別テロである地下鉄サリン事件は1995年。アメリカの世界貿易センタービルやペンタゴンに対する同時多発テロ(9.11事件)は2001年に発生している。
このような陰湿で無残なテロの可能性を、浜田省吾は1986年の段階で予見していたともいえよう。
このような普遍性・予見性を持つ歌を作り出す才能には、本当に驚愕してしまう。
この「NEW STYLE WAR」では、このような新しい紛争の原因は「飽食の北を支えている 飢えた南の痩せた土地 払うべき代償は高く」と分析している。
つまり、豊かさや富の偏在が、一方で圧倒的な貧困層を生み出し、その矛盾がテロを誘発するという解釈ができる。
翻って、現在の日本では格差社会の是非が問われている。
ヒルズ族に代表される億万長者と、生涯を企業勤めで終える一般のビジネスマンとの間には、実に大きな経済格差が生まれている。まして、就労の意欲すら持てないニートに至っては、比較にすらならない。
もちろん、日本は資本主義社会だから、たくさん働いて多く稼いだ者が笑うのは当然だ。そのことに異を唱える人はいないだろう。
しかし、それは自由競争の原理が正常に機能することが前提となる。平等の条件の下で競争を行って、その結果より多くの努力をして汗を掻いた者が報われる経済システムであれば、誰も文句は言わない。
だが、競争のスタートラインが平等ではなく、既に経済力を持つものが優遇されるならば、建前の競争など意味はなさない。
例えば、官公庁のコンピューター・システムの入札でも、仕様書を厳密に指定すれば、実質的に対応できる業者は限定されてしまう。その仕様書策定の過程が不透明であれば、競争は機能しない。
巧妙な細工で、富を持たざるものを排除することは可能なのだ。
現在、ニートが急増しているのも、競争による上昇志向をイメージし難く、社会の閉塞状況を敏感に感じ取っているからではないだろうか。
日本は少子高齢化社会を迎えるのに、働き手である世代にニートが増えているのは、日本経済にとってマイナスである。本来なら貴重な若手の労働力として期待したいのに、その層を親や国家が扶養しなくてはいけないのでは、本末転倒だろう。
これは個別の企業や職場においても同様であろう。勤労意欲に乏しい若者を一方的に責めるのではなく、どのようにして彼らの意欲を引き出すのかが問われている。
そのためには、前提条件の整備が必要だ。つまり、平和・平等をモットーとして、公正な競争を図り、努力した者が報われることを明らかにすることだ。
そんな単純なスタート・ラインの整備ができない職場も多いのではないだろうか?
投稿者 : 03:28 AM
うつ病(鬱病)はストレスに起因する精神の病気で、生きる活力が落ち込み、その結果として体のあちこちが不調となる症状が表れる。
現代日本では、5人に1人は一生のうちに一度はうつ病を経験すると言われるほど、精神的に参ってしまう人は増えている。
これほどうつ病の患者が増えているということは、花粉症と同様に文明病・国民病として認知されるべきかもしれない。
どうやら“ロックスター”浜田省吾もその洗礼を受けてしまったようである。
彼が精神に変調を来たしたのは、1992年の夏だ。
この年、「悲しみは雪のように」が大ヒットし、シングルチャートの売上1位を8週間連続で確保した。いわゆる浜田省吾の社会的評価が絶頂に達した時期でもあった。
これは実に皮肉な現象といえよう。世間で一番認められたときに、その張本人がうつ病で表舞台に出られる状態では無かったのだ。
つまり、うつ病というのは社会的成功者であっても容赦なく陥る可能性がある。
この時期を振り返った浜田省吾の言葉を引用しよう。
「 その92年の夏、僕はちょっと精神的なバランスを崩してしまいまして。2週間ぐらい全く家から一歩も出ないで、居間の窓に-まあ窓から空が見えるんですけど、ずーっとボーッと2週間何もせず。」
「ええ。非常にヤバイ状態だったんですよ。かつてない、いちばんヤバイ状態で。その時のイメージ-その時は楽曲なんて作れる状態じゃないですから、それから少しずつ少しずつ立ち直って。(中略)僕自身の心の危うさっていうんですか。で、精神の危うさっていうのは、こうやってみんなを見てても、誰を見ててもみんないい奴で、問題も抱えてたりするんだけど陽気な部分もあったりして、でも何かひとつがポロッと壊れた瞬間に、誰もが大きく精神のバランスを崩す可能性を持ってるのが、自分自身の体験からよく分かったんですよ。」(BRIDGE 2001年10月号より)
どうやら浜田省吾自身も、自分がうつ病になるとは思ってもみなかったようだ。心身ともに健康なときに、自分がバランスを崩したことを想像できるわけはない。
それだけに、誰もがそのような精神状態に陥ったり、または家族や知人にうつ病になる人がいた場合、その対処法を理解しておいて損は無いだろう。
遠山も仕事で離婚協議書を作成する機会は多いが、多くの場合、依頼者はうつ病の診断をされている。他にも傷害事件の後遺症として、うつ病が治らないケースもある。
何かトラブルを抱えると、人は心身の均衡をとれなくなり、睡眠障害などの体調不良に見舞われる。体重が激減したり、逆に過食で急速に肥満になったりもする。
そんな局面には、何をするべきだろうか。
まず、うつ病の症状を把握しておく必要があるだろう。その症状は精神面と肉体面の両方に表れる。
精神的症状としては、集中力が散漫になったり、常に悲観的な考え方をするようになる。人と会ったり話をするのが極端に嫌になり、何もする気が起きなくなる。そして、ただひたすらボーッとすることが多くなる。
肉体的症状としては、食欲不振、便秘、肩こり、不眠、頭痛、動悸、異常な寝汗、性欲低下、月経不順などが顕著だ。
こうしたうつ病の症状も、重度の人は外出困難となり就業は不可能だが、軽度の場合は上記のようなトラブルがありつつも何とか仕事をこなしているケースもある。
だが、そんな苦しい状態が数年も続くこともあり、できれば早期に治療をした方が良いだろう。
うつ病になった人は、自分の精神が変調していることを理解できなかったり、認めようとしない場合も多いようだ。
周囲の人がうつ病の傾向に気づいたら、治療を勧めてあげる必要があるだろう。
その具体的治療法としては、通院をする意欲が起こるまで先ずは休養をとることだ。その上で精神科に通い抗うつ薬の処方をしてもらう。その後、医師やカウンセラーの指示に従って精神療法を受ける。
もちろん、うつ病となるきっかけが明確になっている場合は、その問題を解決することも大切だ。しかし、問題に対峙するエネルギーが残っていない場合は、まずは治療を優先しなくてはならない。
うつ病は治すことが可能な病気であるという認識を広めることも重要だ。精神的に追い込まれた患者は、自分の怠け心のせいだと思い込んで、更に自分を責める傾向にある。
うつ病の症状が明確になった場合は、まずは休養を取り、1年単位で通院して治療をすることも視野に入れた方が良い。軽症であれば、休業は最低限に抑えて、治療は通院で済むことも多い。
風邪をひけば内科に通うように、精神が病んだら専門医にかかるべきだ。その方が治癒も早くなる。
浜田省吾も最も忙しい時期に休養を取り、うつ病の治療に取り組んだ。そして、徐々に曲作りに復帰して素晴らしい作品をリリースし、ライブもバリバリにこなせるようになった。
もし、うつ病を抱えてしまったときには、急がば回れのことわざとおり、休息をすることが何よりも大事なようだ。
投稿者 : 03:27 AM
国際的な交流が進んで、現在では日本にいながら音楽や料理などバラエティに富んだものが楽しめる。
テレビ番組もいろいろな国の習慣を紹介したり、異文化に飛び込む日本人の姿を放映している。もちろん、インターネットを使って直接外国の様子を調べることも可能だ。
そんな中で、各国の良いものはすぐに輸入され、日本人の音感や味覚にあったカスタマイズが行われ、そしてJAPN仕様となって流行していく。
こうしてブレイクしたものは、不思議なもので昔から日本にあったかのような存在感を示し定着していく。
文化の融合とはそんなもので、それぞれの出自を明確に意識する必要なんて無いのかもしれない。
だが、浜田省吾はプロフェッシャルゆえに音楽のルーツにはこだわっているようだ。彼の制作するロックやR&B、バラードといった種類の音楽は、元はアメリカから輸入されたものだ。
その音楽や文化の浸透について、浜田省吾は次のように語っている。
「 例えばアメリカ人なら音楽的にいき詰ったり、アイデンティティにいき詰っても、カントリー&ウェスタンとか開拓精神といった原点に帰って行けるでしょ。オレはどうかと言えば、帰る場所がきっとあるハズなんだろうけど、伝統的な和楽とは感覚的にかけ離れ過ぎてて、そこには帰って行けない。それは一体何なのだろう。ひょっとしたらオレは戦後の子供だということをしっかり認識しないで、オブラートに包まれて育ってきたんじゃないかって思った。どういうことかと言うと、日本はかつて人類史上例の無い原爆ってやり方で占領された。つまり強姦され、その結果生まれてきた子供じゃないかってことなんです。」(FM fan 1988年3月7日号より)
ちょっと過激な表現だが、音楽にしても文化全般にしても、戦後の日本はアメリカから積極的に吸収しようとして、結果として古来からの伝統文化は軽んじることになったという事実は認識できる。
それで、今更伝統文化に立ち返って琴や尺八をやろうとは思えない。能や歌舞伎が見直されているとといっても、ハリウッド映画に匹敵するような観客動員数を見込むことはできない。
そう考えると、戦後と戦中以前では日本という国の文化はガラリと変わってしまったことになる。本来なら音楽も含めた文化や歴史というのは、気の遠くなるような年月を経て継承されていくものだ。
しかし、日本の場合は伝統文化が急速に弱体化し、アメリカから輸入された文化がコンピュータウィルスのように瞬時に爆発的に普及した。
そのようなアメリカン・ライフスタイルに憧れた人々が、物欲を刺激されてそれを手に入れようと懸命に働いた。その結果、高度経済成長を実現し経済大国と言われた礎を作った。
テレビで流れる音楽も、ポップミュージックが主流となり、和楽は影を潜めた。
このように戦後はアメリカを向いて突っ走って来たわけだが、走り疲れてふとふりかえると、そこには昭和初期の故郷の面影は消滅していた。
故郷を探して明治の町並みを見ても、そこは居心地が悪い。結局、東京的な暮らしや文化から離れることはできない。
実はこのような戦後の文化変容の体験は、日本は近代にも体験している。
そう、明治維新だ。
明治維新は外圧による影響が大きかった。黒船来襲ってやつだ。欧米列強に開国を迫られ、サムライはちょんまげを落とした。
もちろん、第二次大戦のようなアメリカによる占領という事態までには至らず、幕府を倒して新政府を樹立するというのは、基本的には日本人の手で行われた。この点は戦後のアメリカ盲従との相違点だ。
だが、急速に近代化を急ぐことになり、欧米の文化輸入は最高のハイカラとして崇拝された。
現代日本のイタリアやフランスのブランド信仰などは、この頃に形成されたのかもしれない。
そして、大正デモクラシーやいくつもの戦争を経て、1945年にアメリカに占領されることとなった。
戦争中に鬼畜米英と刷り込みをされていても、明治の代で変わり身の早さを経験していた日本人は、手のひらの返し方は体得していた。
それはもう、驚くほどのスピードでフォードやクライスラーを研究し、世界のトヨタやホンダを生み出した。
音楽の分野では、初期の頃はビートルズやエルビス・プレスリーを丸ごと受け入れて崇拝したが、歌詞が何を言っているかわかんねえやということになる。
そこで、洋楽のリズムにのせて日本語で日本人の心情を唄うヒーローたちが出現した。浜田省吾はその代表格で、既に日本人のリズム感として市民権を得たロックで「J.BOY」と叫んで喝采を得るようになった。「J.BOY」とは、もちろんJAPANESE BOYのことだ。
みんなが大好きなアメリカ文化は取り入れつつ、全てをマネしているわけではない。かといって、復古主義で演歌を唄うわけでもない。
現在の日本人が抱いている気分を、忠実に歌詞へ反映してくれる。それが浜田省吾ではないのだろうか。
アメリカとの距離感を丁度良く保って、日本人の精神性も大事にする。この現実を受け入れて独自の道を模索する姿が、あらゆる分野で求められているのではないだろうか。
投稿者 : 03:25 AM
ビジネスマンは一日の大半を仕事に費やしている。仕事というのは職場での労働だけを指すだけではなく、家庭での家事労働も含まれる。
だから、いわゆる専業主婦(主夫)も仕事に割く時間は大きい。人生の中で、仕事をしている時間が最も割合的に多くなる人がほとんどだろう。
ちなみに、遠山は睡眠時間が長いタイプだが、できれば仕事よりも睡眠時間を長く出来ないだろうかと密かに願っている。無論、それは叶わぬ夢だが。
その人生の中で最も多くのエネルギーを投入し、多大な時間をかけているのが仕事なわけだ。
すると、仕事が充実して楽しくて仕方が無い人というのが、最も人生を上手に生きている人だと言えないだろうか。仕事が楽しければ、一日の大半の時間が快適に過ごせるということだから。
そこで、浜田省吾は「仕事」についてどのように考えているかを探ってみよう。
「 仕事っていうのは、ただ、お金をもらって生活するためだけのものだったら、どこか寂しい気がするんですね。人は社会的な生き物ですから、仕事をすることによって、社会の中のつながりとか誰か人のためになっているとか、そういう存在価値みたいなものを見出せたらすごく幸せだと思うんです。
主婦っていうのも、やっぱり仕事だと思うんですよ。家族をケアしながら子供を育てていくことも社会とつながってることだし。その中で社会に対する存在価値を見いだせなくなっているとしたら、不幸なことだという気がします。」(日経エンタテイメント 1999年12月号より)
納得である。現代社会は物の生産や流通が高度化して、仕事の内容が分業化・細分化されている。
過去においては、仕事の企画段階から原料仕入れ、加工製造、運搬、販売に至る過程を少人数でトータルに実施されていた。
それが社会の経済システムが高度化するにつれて、各作業が分担されるようになり、それぞれの作業現場でのスペシャリストが誕生した。企画立案のプロ、バイヤーとして凄腕を発揮する営業マン、神業とも言える加工技術を発揮する熟練工。それぞれが極めて狭い範囲でのプロフェッショナルぶりを発揮する。
例えば、工場の中で精密回路のハンダ付けの作業を任された場合、ただひたすらにハンダと格闘する。黙々と作業をこなすうちに、その作業速度は神の領域に達し、プリント基板の極小の不良についても一瞬で見抜く超能力を会得するようになる。
一方で、それ以外の仕事が見えないわけだから、同じ会社にいても他の人の作業内容は不明だったりする。ハンダとプリント基板についてはプロになっても、自分のやっていることが社会のどこで役に立っているか、その根本的なことを知らないということもあるだろう。
上司も、この部品がどんな製品に使われるのか教えてくれないことも珍しくない。
そんな状況で、朝礼時に「お客様のために貢献しろ」とか「仕事に誇りを持て」と言われても、それは虚しいスローガンとして耳の左から右へ抜けていくだけだろう。
何しろ、自分がどんなお客様に対して、何を作っているのかわからないのだから。
逆に消費の場面でも同様だ。今晩の夕食の刺身について、その生産や流通過程に携わる人々の苦労にどれだけ意識はいくのだろうか。
魚が切り身になるまでは、養殖業者の手で何ヶ月も世話をされた魚が水揚げされ、鮮度が落ちないうちにトラックで運ばれ、加工センターで切り身にされる。その後、店頭に並ぶわけだ。その間では熾烈な価格交渉があって、そこでストレスを抱える人もいるはずだ。
スーパーのバイヤーは納入業者の価格を買い叩き、納入業者は漁師を叩く。尊大な大口顧客が小規模な納入業者に無理を言うという連鎖が延々と続いていく。
笑い話で、小学生に魚の絵を描かせると、切り身が泳いでいる絵を描いたという話がある。夕食の刺身が、水族館で見たことのある生きた魚のパーツであるということが認識できないのだ。無論、お母さんが魚をさばいているところを見たことは無い。魚は切り身で買ってくるものだと学習している。
それほどまでに現代人は、かつては自らの手で行っていた工程の一部しか見ることができず近眼になっている。
そんな断片的な日常を繰り返していると、自分が社会の中でどのような役割を担っているかを感じ取るのが難しくなる。
浜田省吾も語るように、社会とのつながりを認識しないことには、人間は孤独や疎外感から開放されることはない。面倒に思える作業になるかもしれないが、自分のやっている仕事が何の役に立っているのかを調べ、その全工程や全体像を把握する努力を行い、それを家族と語って確認することが幸せにつながるのかもしれない。
自分がやっている仕事がどんな役に立っているのか、それをイキイキと語る様子が子供たちにもまぶしく映るだろう。
投稿者 : 03:23 AM
人間にとって何が幸福かってことは永遠のテーマになるだろう。とにかく衣食住は足りて、生活が満たされることを優先する人もいれば、精神修養を第一に掲げる人もいるだろう。
人それぞれで大切なものも違う。遠山の場合は、とりあえず好きな時に渓流釣りができて、パソコンは四六時中ネットにつないでいれば、かなり満足してしまう。
もちろん、家族や友人も大事だし、仕事も順調にこなしたい。
大事にしたいのは、恋愛だったり、友情だったり、ビジネス的成功だったり、趣味を極めることだったりもする。
このあたりは、人によって千差万別だろう。
幸福の条件として、それが物欲であればわかりやすい。
「純白のメルセデウス プール付きのマンション 最高の女とベットでドン・ペリニヨン」
これはある有名な歌手が作った歌詞だが、このように欲しいものを列挙すれば、どれだけ手中に収めるかで満足度を図ることもできる。
でも、ここに挙げられたモノを手に入れるには、かなり頑張らないとキツそうだが。
それほど物にはこだわらない人もいるだろう。とにかく三食に不自由なく暮らせれば、それで充分だという向きもあろう。
でも、独りだと寂しいから友達や恋人は欲しいと思ったりする。
浜田省吾も、デビューしたての頃は世俗的な成功を夢見ていたそうだ。アメリカで流行したロックで一山当てて、豪邸でも建てようかという野心はあったという。
だが、実際に長者番付に掲載されるくらい稼ぐようになると、今度はゆとりがほしくなったそうだ。
そりゃそうだろう。全国を移動しながら年間に150回近いライブ数をこなし、合間にアルバム制作をするという過密スケジュールだったら、儲かるだろうがプライベートな時間は限られてしまう。
企業戦士でも同様だが、超多忙になると自分のことに構っている時間は無くなってしまう。“オレはバリバリに働いて充実しているんだ”と強がってみせても、休日も無く帰宅したら疲れて寝るだけの生活に嫌気が差すこともあるだろう。
そんな追い立てられるような仕事漬けの毎日を送っていると、本を読んだり映画を観たり、家族や友人・恋人とゆっくり過ごす時間が欲しいと思うようになるものだ。
でも、時間にゆとりがあってもサイフにゆとりが無いのはカンベン願いたい。
すると、ビジネスで成功していても、無尽蔵な時間を持て余していても、どちらにしても不満は生じるということになる。これは困った。人とはいかに小難しい生き物なのか。
そんな人間の幸福についての考察を、浜田省吾は次のように述べている。
「 基本的には幸福になるための要素は三つあると思う。
それはものすごくシンプルなことで、一つは“健康”であること。それから、“平和”であること。それは世の中が平和であることもそうだし、自分の心が穏やかであることも含めて。もう一つは“孤独”でないこと。この三つがそろえば幸福なんだと思うんです。
そりゃあ、やりがいのある仕事だとか趣味とかほかにもいろいろ細かいことはあるかもしれないけど、基本的にはひとりぼっちじゃなくて健康で平和だったら、それは幸福なんだと思う。その三つを自分のために揃えて、幸福になりたいと思うのなら、それを勝ち取ってやるという努力が必要なんですよね。」(JUNON 1990年9月号より)
これは実に的確な指摘だ。健康でなければ何も始まらないし、平和でなければ恐怖に怯えなくてはならない。孤独は人を追い詰める。
しかも、この三つの要素を得ていくためには、努力が必要だとも言っている。
つまり、健康を維持するためには、食生活や運動量に気を配らなくてはいけない。平和を享受するためには、その存在を脅かす動きに警戒を怠ることはできない。絶えず、社会情勢に関心を持つことが必要だろう。
孤独を脱するためには、進んで人とコミュニケーションを図らねばならない。
このように、幸福を形成する三要素は、受身では待ち人のところに来てくれないのだ。自分から積極的に取り込んでいく努力が不可欠といえよう。
また、人は初期の段階では自分だけの幸福で満足できる。これら三要素がスロット台のようにゾロ目で揃ったら、とりあえず満足するだろう。
だが、その満足感は永続しない。
次の段階として、“孤独ではないこと”と関連するのだが、自分が社会とつながることで役立ちたい。人に認められたいという意識が働くようになる。
そのようにして、幸福への欲求のレベルは上がっていく。
単に物欲に振り回されているうちは、足もとの幸福には気づかない。当たり前だと思っていたことに関心を持ち、身の回りのものを大事にして、人とは進んで接する。
それを意識的に繰り返せば、自ずと幸福を実感できるものなのかもしれない。
投稿者 : 03:22 AM
男女の恋愛が結実すると、それは結婚につながり、やがて親子や家族という関係が発生する。もちろん例外もあるだろうが、一般的にはそういう過程を辿るだろう。
つまり、恋愛感情は家族愛に昇華していくものだ。
その家族愛では、親子というのも重要なキーワードとなる。親子の愛情というと、普通は母親と子供の関係を連想するだろう。
子供にとって母親というのは、無条件に受け入れてくれる特別な存在なのだ。実際に遠山の家庭においても、子供が慕うのは母親であり、父親は半歩離れたところにポジショニングされている実感はある。子供が年頃になった暁に、洗濯物を箸でつままれるような状態にはならないよう気をつけたいものだ。
また、遠山自身の育った環境が父親とは死別による母子家庭だったため、父親の存在感がどういうものなのかリアルにはわからなかった。物心ついたときには母親しか存在せず、よその家庭で茶の間に父親が鎮座しているのを目にすると、何か敬遠する心境が働いた。 そのため、自分の感覚では親イコール母親であったので、父親象のイメージが貧困であることをお断りしておく。どうも、「父親なんていなくても子は育つ」という感覚が染み付いていることは否めない。
だからといって責任転嫁するつもりは無いが、自分が父親になったときには、妙な違和感があった。どう対応すべきかわからないというか、所在無さみたいなものを感じた。それは、初めて我が子と対面した父親なら誰でも感じることかもしれないが。
それでも10年も父親業をしていると、それなりにやるべきことは心得てくる。そんな今になって、亡き父親の胸中や母親の苦労に思いがいくようになった。
そんな遠山の抱く個人的な父親像は別にしても、世間一般の認識においても現代の父親は家庭で疎外されているのかもしれない。
父親は仕事だゴルフだ釣りだといって家にいないから、どうしても子供は母親についてしまう。仕事で疲弊しきっていることは確かなので、たまの休日は寝転んでいると子供にはグウタラしているようにしか映らない。その子供が思春期になれば「子供が口をきいてくれない」と嘆く父親は多い。
実に頼り気の無い父親像になってしまうが、意外にも浜田省吾は父親との関係を歌にしているものが多い。
1984年に発表された「DADDY‘s TOWN」では、「GOOD-bye Little Daddy’s Town 何もかも閉ざされたMy Hometown」と父親の住む街に毒づいて、家と街を飛び出すことを宣言する心境を曲にしている。
そこには父親が少年の抑圧の対象として描かれている。
1988年の「DARKNESS IN THE HEART」では、「思い出す病室で痩せていく父の姿を 痛みから解かれて去って行った独りきり 車の窓に映っているおれの顔 彼に似ている」と癌との闘病生活の末に亡くなった父親を回顧している。
それは父親に対する伝え切れなかった思いと、その血をひく自分がどう生きるかという自問がある。
そして2005年の「I AM A FATHER」では、「傷ついてる暇なんか無い 前だけ見て進む」「嘆いてる暇なんか無い 命がけで守る」と父親としての決意表明をしている。
浜田省吾自身には子供はいない。それでも、父親世代の心情を代弁して、かつては少年だったが自分が今では父親になったことの自覚を軽快なロックにしている。
このように少年時代は威圧的な壁として存在していた父親が、実は社会の荒波からの防波堤として身を捧げてくれていたことに気づき、今度は自分が子供のために堤防となっていくことを一連の歌にしている。
浜田省吾の30年の音楽活動の流れの中で、父親というキーワードの視点が対立の対象から和解、そして踏襲へとシフトしている気がする。
少年期の父親ならびに社会への反抗というテーマでは、佐野元春が「ガラスのジェネレーション」で唄った「つまらない大人にはなりたくない」というフレーズも有名だ。
1960年代から70年代にかけては、Don’t Trust Over Thirty(30歳以上の大人の言うことを信用するな)というスローガンも流行したらしい。
これは大人社会に対する不信感から、反抗という自己表現をする若者らしい特性を表している。
そんな反抗期を経て、かつては嫌悪の対象であった大人になってしまった現在の父親世代は、もうハラをくくるしかない。
傷ついて感傷的になったり、不遇を嘆いている暇など無く、現実的な問題が次々と目の前に出現するのだ。これはもう、命がけで前に進んでいくしかない。その生き様を子供に対して背中で語るしかないだろう。かつては自分たちの父親がそうしてくれたように。
でも、自分が子供の頃の父親には問答無用の理不尽さがあったと思うなら、そこは改めて子供には向かい合いたいものだ。
今の父親は育児や子育てに積極的に関わろうとしても、残業や休日出勤などビジネスマンの苦役はキツく、なかなか時間が確保できないという問題はある。
また、子供を巻き込んだ凶悪犯罪は増え、世の中が世知辛くなってきている。そのような困難はあるが、だからといって子育てを放棄するわけにはいかない。
そのような父親世代の決意の曲として、I AM A FATHERは歌い継がれている可能性を秘めている。これは時代を反映し、家族のあるべき姿を予見する曲と言っていいだろう。
投稿者 : 03:21 AM
浜田省吾はよく「単純なラブソングが好きだ」と語っている。また、実際に数多くのラブソングをつくっており、ファンはその世界に陶酔する。カラオケでも定番となっているバラードも多い。
「もう一つの土曜日」や「愛しい人へ」のような苦労の末のプロポーズや結婚への決意表明を歌った曲もあれば、「片思い」や「陽のあたる場所」のような成就することの無い後暗い情感あふれる曲もある。
どちらかといえば、うまくいかない恋愛を唄った曲の比率の方が高いだろう。それ故に「浜省の曲って暗いよね」っていう評価もつきまとうが、それも歌詞の素晴らしさの勲章と言えよう。
こうしたバラードは、見事なストーリー性を構築しており、その歌詞で60分枠の恋愛ドラマが一本できるほどだ。それほど歌詞の情景描写は見事で、聴き入るほどにそんなドラマの1シーンが瞼に浮かんでくるようだ。
そのような男女間の恋愛については、普通は結婚までが一つのクライマックスとなるだろう。(結婚してからも婚外恋愛で盛り上がってしまうイケナイ恋愛体質の人もいるでしょうが・・・)
恋愛の一応のゴール(通過点という説が主流だが)である結婚までには、くっついたり離れたり、時には横恋慕があったりと様々なドラマがある。
結婚してからも家族のドラマはあるわけだが、それは別の章で述べることにする。
その結婚式という社会的儀礼を通過すると、自由恋愛の頃とは違った責任が発生する。恋愛や結婚について話すのに、“責任”とか持ち出すのは興醒めだが、逃れようの無い事実なのだ。
その責任とは、同居や協力扶助の義務であったり、夫婦貞操の義務であったりする。ちなみにこれは民法第752条や同法第770条にキッチリと定められている。
正確に言うと、その“責任”は結婚の時点ではなく、結婚を誓い合った時点(いわゆる婚約)から発生するという見解が主流になっている。
つまり、婚約以前の自由恋愛の状態であれば、一方的に別れても損害賠償の責任は生じない。平たく言うと、慰謝料を支払う必要は無いってことだ。
しかし、いったん婚約なり結婚をすると、これは契約が成立したってことになり、一方的に破棄をする場合は損害賠償責任が発生する。こんなケースでは、身勝手に別れると言った方は、ガッポリと慰謝料を持っていかれることになる。その別れる原因が浮気ということなら、もう逃げようがない。
すると、自由恋愛のうちは失敗したり傷つくのも自己責任ということになる。浜田省吾も「彼女はブルー」の中で「愛ははかなく 契約なんてないのよ」と唄っている。
結婚という契約が成立すれば、法律が守ってくれる場合もある。でも、婚約前の自由恋愛は、どれほど失恋のショックを受けようとも、その苦しみは自分ひとりで背負わなくてはならない。それが近代の原則であり、自己責任ということだ。
今は婚約破棄や離婚について苦しむ人は増えている。それは辛い出来事であるし、その人の人生においては大きな悲劇だ。統計的な離婚率の上昇を見て嘆く人も多い。
しかし、明治以前であれば、婚約を拒んだり離婚をする自由はなかった。不本意な結婚生活であっても、それを断ち切る自由がなかったわけだ。当時でも、離婚の自由が認められ、経済的にも問題が無ければ、恐らく離婚率は格段に上がっていただろう。
そういう意味では、婚約破棄や離婚の自由が広まったと言えよう。何も我慢して嫌になった相手と同居を続ける必要は無いということだ。
交際相手も自由に選べ、婚姻生活が我慢の限界を超えるようなら、離婚するのも自由なのだ。
だからといって、別れるのを前提とするような非生産的な疲れる交際の仕方はオススメできない。男女恋愛をするなら、本気で相手を愛し抜く気概を持つべきだと思う。
ビジネスでも、失敗を前提として企画を打つことはありえないだろう。失敗を「想定の範囲内」等と取り繕ってみても虚しいだけだ。
同じように、恋愛でも長続きしないと思いながら付き合うのは、やはり虚しいだろう。交際をするからには、結婚を意識できる相手と付き合った方が健全だ。真剣に付き合ってみたものの、結果としてうまくいかない場合もある。そんな時は、かなり落ち込んでしまうのは仕方ない。
しかし、いつまでも沈んでいても始まらない。ひとしきり辛さを噛み締めたら、その後は立ち上がらないといけない。
恋愛の破局時には半狂乱になる人も多い。その心情は理解できる。ただ、それは相手に対する依存心が強すぎるということだ。
恋愛をするのは自立した男女だ。その自立が怪しいと、相手に精神的にドップリと依存してしまう。恋愛がうまくいっているうちは、それでも何とか回るものだが、別れることになったときには取り乱してしまうことになる。
人生には挫折とか失敗はつきものだ。受験や就職に失敗することもあれば、事業に失敗することもある。恋愛や婚姻生活の挫折も、そのような失敗の一つと言える。その挫折のたびに半狂乱となっていては、やはり強くなっていくことはできない。
浜田省吾は成就しない恋の歌を数多くつくっている。それは、転んでも起き上がることの大切さを説き、辛い気持ちの人の背中を押してくれる優しさもある。そんなラブソングを人生の応援歌と思って、活力に変えていきたいものだ。
投稿者 : 03:19 AM
芸能人にとって、プライバシーの確保は頭の痛い問題だろう。その苦悩は一般人からは窺い知れない。
中にはゴシップを売名行為に利用するしたたかな著名人もいたりするが、本音は静かにしておいて欲しいところだろう。
私生活と芸能ネタが密接に絡むお笑い芸人でも、プライバシーの侵害は有名税として受け入れるにも辛いものだ。
浜田省吾の場合は、ミュージシャンとしてプロ意識が高いだけに、ステージや広報以外で個人的話題に触れられるのを敬遠しているように思う。
注目されるのは音楽やステージの上であって、プライバシーを切り売りしたくないという意志を感じさせる言動も多い。
例えば、ファンクラブの会報でも以下のような受け答えをしている。(1991年 ALL ABOUT SHOGO HAMADAより)
Q:兄弟・姉妹関係をはっきりと明記して下さい。
A:ひみつ!
Q:“生まれたところを遠く離れて”に省吾と一緒に写っているのは奥さまですか?
A:そうです。が、プライベートはそっとしてあげて下さい。誰でもプライバシーはあるのだから・・・
Q:ファンの人にしてほしくないことってありますか?
A:自宅に来ること。車の後を追いかけてくること(本当にイヤなんだ)
このように家族や個人的事情に触れることは話題にはしたがらない。曲の歌詞では浜田省吾自身の精神的内面を描写するものも多いだけに、ファンは自己解釈の上では彼の内なる世界に容易に入ることができる。
しかし、プライバシー開示に関して頑なな拒否反応をする浜田省吾を見て、初めて彼にも触れられたくない話題があるのだと理解する。
トレードマークとなっているサングラスにしても、ファンの前や雑誌に登場する場合は、絶対にそれを外さない。これはサングラスによって素顔公開を拒んでいるのだ。
普通の芸能人は、プライベートで行動するときは素顔を隠すためにサングラスで変装をする。それとは逆に、浜田省吾の場合はビジネスの時はサングラスをして、オフは素顔になる。テレビに同調しない姿勢にしても、このサングラスの活用法にしても、通常とは逆の行動をするところに浜田省吾らしさを感じる。
また、浜田省吾は「音楽制作をしているときは仕事という意識は無く、雑誌取材やカメラ撮影を受ける時は仕事だと感じる」と語ったこともある。
スタジオで創作や演奏をしているときはサングラスではなく、マスコミ取材には全てサングラスをしている。ここには「サングラス=仕事」という図式も成立しそうだ。
つまり、浜田省吾は仕事に入る時はサングラスをして、オフになれば外す。サングラスをすることで、仕事モードにスイッチが入るというわかりやすいメリハリだ。それはビジネスマンがネクタイを締めるのと似たような感覚なのかもしれない。
大抵のビジネスマンも、仕事とプライベートのケジメをつけるようにしていると思う。中には仕事と結婚をして、公私の境がボーダレスになっている人もいるかもしれないが。
遠山も自宅開業の個人事務所のため、そのあたりの境目があいまいになる時はある。仕事が一段落して、昼寝をしているときに電話で起こされると、さすがにまずいという意識は働く。
昔の栄養ドリンクのCMではないが、「24時間闘えますか」とはいかないものである。人は働く時は気合を入れて頑張り、仕事が終われば羽を伸ばすというシフトチェンジをして生活が成り立つ。
よく「家庭に仕事を持ち込むな」という酒席での会話を耳にする。これはいくら仕事が忙しくても、そのストレスを妻や子供に向けてはならない。それが家庭円満の秘訣だという人生訓だろう。
逆に「仕事にプライベートを持ち込むな」という上司の叱責を受けたことのあるビジネスマン諸氏も多いだろう。何を隠そう、遠山も企業勤めの新人の頃は、そんな教育的指導を受けてきた。
これは小さな意味では「仕事を早々に切り上げてデートに行こうなんて考えるな」という程度の話だ。大きな意味では「個人的な縁故を利用して私利私欲を満たそうとするな」という戒めだ。もちろん、遠山が小言を貰っていたのは前者の方だ。
そんな公私混同を避けるためにも、仕事モードに入る時はスーツを着るとか、作業着に着替える、社章を付けるといった儀式は有効なのかもしれない。すると、制服には批判もあるが一定の精神的役割は果たしていると言えよう。
それから、芸能人のプライバシー侵害問題にはピンと来ない人も多いだろう。だが、インターネットの巨大掲示板である2ちゃんねる等に、自分の職場での失敗や部署名等を晒されたことをイメージするとどうだろうか?
更に悪ノリをされて、自宅住所まで書き込まれた時には、誰でも堪忍袋の緒が切れるだろう。「テメー!訴えてやる。」という心境になるはずだ。
恐らく浜田省吾もそんな憤りに身をワナワナと震わせた出来事はあっただろう。自分が不快だと思う誹謗中傷や個人情報の暴露は、厳に慎むべきだ。
今日では、ネットを利用して誰もが公然と侮辱を受けるリスクは高まっている。そんな社会だからこそ、個人の良識が問われるといえよう。
投稿者 : 03:18 AM
現代社会にはストレスが蔓延している。ビジネスマンにとっては、今も昔も仕事によるストレスが最も悩ましいところだろう。
具体的には、上司や部下との人間関係であったり、残業や休日出勤、早朝からの通勤や転勤もあろう。給料が安いというのはかわいい方で、何も決まらぬ生産性のない会議や無意味なアリバイ工作のための成果報告書の作成なんかもイライラ感を募らせてくれる。
そんなストレスを発散するためには、ゴルフや野球等のスポーツで汗を流したり、食欲やアルコールに走ることもあるだろう。クレジットカードで衝動買いをしてしまうのもアリかもしれない。
仲間内で騒ぐときは、カラオケでガンガンやって憂さ晴らしというのもベタな解消法だ。
それで、カラオケで浜省を選曲するなら、そんな気分のときは「J.BOY」や「MONEY」あたりになるだろうか。
「J.BOY」では「仕事終わりのベルにとらわれの心と体取り返す夕暮れ時」とか「そしておれは心の空白埋めようと山のような仕事抱え込んで凌いでる」という歌詞あたりで力が入ってしまう。
「MONEY」では、「俺は何も信じない 俺は誰も許さない 俺は何も夢見ない 何もかもみんな爆破したい」と絶叫すると、最高に気分が良くなる。
また、浜田省吾のライブに参加すると、「Oh Yah!!」と絶叫した後に彼がこう語る。
「Oh Yah!!と叫んだところで何が変わるわけでもない。何も問題は解決しない。でも何故か気分は良くなるだろう。だから一緒に叫ぼう。」
こういう軽快なトークに乗せられ、会場の中はかつてのドリフの「8時だよ!全員集合」並みに何度も「Oh Yah!!」が連呼される。(「8時だよ!全員集合」の掛け声は「オッース!」だったが。)
カラオケやライブに行っても、浜田省吾が言うように問題がそれで解決するわけではない。ただ、その場で気が晴れるだけである。
それでも、日々鬱積するストレスが多少でも和らぐことは確かだ。
このストレスというのは物事の受け取り方で変化するもので、あるプロジェクトを任された場合に、それを負担に感じるのか、それとも奮い立つのかで180度異なった精神状態となりうる。
だから、最初は憂鬱に感じていた仕事も、同僚とカラオケに行くことによって、楽しく思えるような劇的変化をすることもある。もっとも、カラオケの18番を奪い合いあって血の雨が降り、益々職場の人間関係が悪化する可能性もあるわけだが。
職場というのは集団行動の場だから、一定のルールに拘束されるのは仕方が無い。わがままは通らないので、仕事の目的を達成する範囲で行動の自由は制約を受ける。そこは社会人として受け入れなくてはいけない。
しかし、理不尽な事件や納得いかない処遇というのも、残念ながら起こりうる。そんな場面に遭遇すると、ストレスの臨界点に達してしまうこともある。
その状況が長期化すれば、精神的に不安定となり体調まで崩してしまうことも多い。ひどい場合は、鬱病になったり過労死につながったりもする。
そこまで嫌になってしまった職場なら、辞めてしまえばいい。それができるなら、ストレスなんて溜まらない。
その仕事や職場が嫌で嫌で辞めたいと思っても、辞めることができないときにストレスが極大化する。
つまり、嫌な仕事を我慢しながら続けざるを得ない状態が最大のストレスともいえよう。
話は変わって、バブル後のリストラ旋風が吹き荒れた時期を経験し、もはや終身雇用は幻想だということを誰もが肌で感じ取っている。
公務員ですら合併や合理化で人員削減が進んでいる。都市銀行が破綻し、大手証券会社も破産するのも目撃した。無条件で安泰な勤務先なんて存在はしない。
そんな終身雇用が期待できない職場で、心底から嫌だと思う会社に依存する理由は何であろうか?
それは、次の働く場所が見つからないということが大きな原因といえよう。
では、嫌だと思っている職場でも、「辞めようと思えばいつでも辞められる」という心構えができていればどうであろうか?
恐らく、精神的ストレスは格段に軽減するに違いない。命令口調の上司にも、口ごたえの一つもできる余裕が生まれるだろう。
そのためには、「辞めようと思えばいつでも辞められる」と思えるだけの裏付けが必要となる。
つまり、自分には技術があり、その技術があれば次の職場はそれほど苦労しなくても見つかるだろうという根拠が必要だ。
しかし、技術なんて簡単には身につくものではない。もっとも手っ取り早いのは、今の職場の仕事に精通し、同業であればどこに行っても通用するというスキルを積んでおくことだ。会社が資格取得を奨励しているなら、自分のために積極的に取っておくべきだろう。
そのためには、一定の修業年数が必要だ。石の上にも三年とは、よく言ったものだ。
現在の職場では特に何の技術も身につかないという状況であれば、余暇時間を利用して自分で努力をするしかない。
そうして自分の技術に自信が持てるようになれば、気がつく頃には会社は恐くなくなっているから不思議なものだ。
ストレスに打ち克つには、適度に息抜きをしながら、職場のスペシャリストとして自立していくことだ。
投稿者 : 03:17 AM
浜田省吾のファン層は、ティーンエイジャーから熟年世代まで幅広い。浜田省吾自身は1952年生まれだから、2006年4月現在では53歳だ。
当然ながら同世代のファンも数多く存在し、その上の年齢層にも支持されている。
浜田省吾より年上のファンといえば、年代的には戦後のベビーブーム世代であり、いわゆる団塊の世代である。
この団塊の世代が2007年から2010年の間に60歳に達し、その人数は300万人とも言われる。60歳といえば、多くの企業や公務員の定年退職の年齢だ。
短期間に大量の退職者が発生するので、その補充は新卒だけでは埋めきれず、人事担当者を悩ませることになる。
これを労働市場の2007年問題と呼ぶ。
バブル崩壊以降の雇用抑制が続いたので、どの職場も余剰人員はなく、ギリギリの状態で回っているのが実情だろう。
そんな中で同時多発的に定年退職者が発生するのだから、現場は悲鳴をあげることになってしまう。
しかも、折からの少子化進行で新卒の人数は減少傾向だ。補充は簡単ではない。
また、製造業の現場では、団塊の世代は貴重な熟練工となっている。日本の精密加工を支えてきた熟練技術は、単に若年層を補充するだけでは継承されない。
このような2007年問題に対して、産業界は定年退職後も雇用延長を図ることで対処しようとしている。
しかし、経営再建の名の下に、リストラや賃金カットに耐えてきた団塊の世代の中には、定年後の継続勤務に関しては複雑な感情もあるだろう。
それでも、団塊の世代に対する社会的要請は高いと言える。
では、晴れて定年を迎える団塊の世代のビジネスマンには、リタイア後にはどのような選択肢があるのだろうか?
最も羨ましいのは、退職金を得て充分な貯蓄をし、経済的な不安が無い状態で趣味に生きる生活だろうか。これは本当にあやかりたいものだ。
ちなみに、2007年からの3年間で動く退職金の総額は、80兆円にも達するという試算もある。
他にはボランティアや地域貢献に励む人々もいるだろう。地域の世話役等で、新たな才能を発揮する場面もあるかもしれない。
仕事を継続する場合も、勤務していた会社の定年延長に応じてもよし、気分を変えて他の会社で働くのもいいだろう。
かつてのリストラとは逆の風が中高年に吹くかもしれない。
こうして考えてみると、団塊の世代のリタイア後の人生は、明るく熱いものになるかもしれない。
かつての定年退職後の侘しいイメージは、払拭される可能性もある。
しかし、問題が無いわけではない。
熟年世代にも重荷はのしかかっている。住宅ローンが定年までに払い終えられない人も多いだろう。同様に遅くに子供ができた人は、高等教育の学費支払いに頭を抱えなくてはならない。ひょっとしたら、子供がニートになっていて、その自立を促すために家庭内でひと悶着あるかもしれない。
それから、親が存命であれば介護の問題も抱えているだろう。
必死の思いで長い間働いて老後の資金を貯めても、それを狙う詐欺師も存在する。巧妙な口車に乗せられて、数十年の集大成とも言うべき貯蓄を、ほんの数ヶ月で掠め取られるリスクもある。具体的な手口については、別の章で詳細する。
そこには古きよき時代の日本の美徳は通用しない。
それでも、戦国の世で人生50年と言われた頃を考えれば、今の熟年世代は熱く生き生きとしているのではないだろうか。
団塊の世代が高度経済成長期を演出し、バブルとその崩壊を経て、豊かなリタイアを迎えたのだから、まだまだ何かをやってくれるという期待はかかる。
何しろ80兆円もの資産を手にするのだから、周囲もその動向が気になって仕方がない。
また、熟年世代に属する浜田省吾は、今でも現役のロックスターであることは間違いない。そのライブに熱狂する10代の少年少女も存在する。
これはとんでもない偉業だと思う。浜田省吾がデビューをした1976年頃に、ロックというジャンルの音楽で生計を立て、その30年後もライブでティーンエイジャーを夢中にさせるなんていうことを、誰が想像できただろうか。
もちろん熱狂的なファンは、熟年層にも多い。
余談だが、遠山の微かな記憶では、初めて浜田省吾の存在を知ったのは小学生の時で、小学館の「小学六年生」という雑誌の情報からだった。その記事の中で「浜田省吾のライブを座って聴こうなんてとんでもない」というキャッチコピーがあったように記憶している。
子供心に「浜田省吾って、観客を座らせないんだ」なんて思ったものだ。そんなライブを30年も継続している浜田省吾には、本当に頭が下がる。
(追加すると、初めて浜田省吾の曲を聴いたのは、大学に入学した18歳の時だった。)
浜田省吾はライブ一徹で頑張っている。同世代の熟年層も、会社を定年退職したくらいで老け込むはずは無いだろう。
日本を経済大国に導いてきた原動力は、間違いなく現在の熟年層だ。まだまだパワーのあるところを随所で魅せてくれるはずだ。
投稿者 : 03:15 AM
浜田省吾のライブ・ツアーは、当然ながらファンには熱烈に支持されている。しかし、バンドのメンバーやスタッフには過酷な日程となるようだ。
ツアーというからには、日本中の主要都市や地方都市を巡回する。過去には、バンドメンバーは26泊27日の旅というような状況が日常となってしまうこともあったそうだ。スタッフに至っては40泊なんて事態にもなる。
これでは自衛隊の潜水艦乗りのようなライフスタイルになってしまうだろう。
そのようなツアーが定期的に続けば、当然ながらメンバーやスタッフ個々の家庭生活に影響がある。
アパートを引き払うことを余儀なくされたり、恋人と別れたメンバーもいるという。
実に過酷なライブ・ツアーではないか。
それでも、ライブ・ツアーである「ON THE ROAD」は長く続き、メンバーやスタッフも楽しんでいる様子はファンクラブ会報から伝わってくる。
そもそもファンを楽しませるライブで、主催者が苦痛のみでやっていたら、興行として成立しないだろう。
バンド・メンバーやスタッフは、ライブ・ツアーという共通目的に結束する運命共同体であり、そのチームワークがライブという事業の成否を分けると言えよう。
そんなバンド・メンバーに対する浜田省吾の認識は、次のとおりだ。
「いっしょにやってきた人たちは、僕の曲がすごく好きでやりたいからやったというんじゃないと思う。
そんなに話は美しくないし、僕だって特に昔は、みんなが“これはいい曲だ”と思えるような曲をたくさん書いてたとは思えないからね。(中略)
その中で、僕といっしょにやるということは、ある部分では仕事だし、経済的なもの。(中略)
あるソング・ライターがいてそのバッキングでレコードをつくったりステージをやるミュージシャンというのは、基本的に個人ですよ。若い頃はそれ以上のものを望んでいたこともあるけど、それは望むほうが無理というもの。ただ、いいミュージシャンはどんなものにも全力を投球するし、楽しむ。それが観客にも伝わるでしょう。」
「セッションをやるミュージシャンというのは、みんな自分の夢を持ってる。でもそれは別にして、どれだけそのときに全力で、いいバイブレーションでやってくれるかなんです。お仕事っていうふうに見える人もいるのね。僕が全力をかけているのに後ろで仕事をしている人がいると雰囲気が醒めるでしょう。」(以上「ROAD&SKY 60号」より抜粋)
つまり、いいライブをつくるためには、良いミュージシャンを揃えなくてはならない。しかし、良いミュージシャンは個人の目標があり、いつまでもライブに協力してくれるとは限らない。
そうしたシビアな現実を認めつつ、目前のライブに全力投球を続けるわけだ。確かに独立を考えるくらいの意欲を持った個人でなければ、音楽の才能を研ぎ澄ますことはできないかもしれない。
事業を継続するという観点で考えれば、いずれ独立を考えているような人材をチームの中に入れるのは、和を乱す行為にも思える。
しかし、チームを全てイエスマンで揃えてしまえば、そこは指示待ち人間の溜まり場となってしまい、組織の活力は生まれてこない。
継続させることを自己目的化してしまうと、その組織は顧客サービスという視点は欠如し、自己防衛に向かうようになる。その先に待つのは衰退だ。
一方、乱暴のようにも思えるが、独立志向が強い人間でチームを組めば、その瞬間に発揮するパフォーマンスは大きくなる。
その時点で最高の顧客サービスを提供することだけを考えれば、外部のエキスパートを呼び込むのも有効となろう。
本当に強い組織というのは、構成員に滅私奉公を求めたり、上位下達で縛りをかけたりすることでは作り上げられない。
組織の一人一人が確立した個性を持ち、その優れた個性を共通目的のために結集させる過程が大切だ。もちろん、個性の強い人材でも、組織に所属する間はルールに従わせる必要はあろう。
理想を言えば、優れた個性の集合体をカリスマのリーダーが強烈な理念の下にまとめていくのが最適だろう。しかし、現実にはそう簡単にはいかないことは誰もが承知している。
自分の職場や所属している組織をふりかえれば、マニュアルで縛らないと行動しない人も多いかもしれない。何の意味も理念も無く、無理難題を押し付けることしかしないリーダーも存在するだろう。
遠山もサラリーマン生活は13年ほど経験したが、組織の中の人間関係は難しいものだと痛感してきた。個人の努力では変えようが無いと思える問題は多い。
その結果、独立してフリーになることで、職場の人間関係からは開放されている。今のところは部下が欲しいとも思わない。(もちろん、上司もいらない)。
しかし、様々な局面で集団や組織に属することは多いものだ。
強い組織をつくることを“理想論”だと決め付けてしまうと、そこからは何も生まれない。一人一人が自己の能力を高めることに関心を持ち、組織がそれを支援しつつ構成員の意欲を引き出す。そんな循環を生み出せる人が、真のリーダーといえるのではないだろうか。
投稿者 : 03:13 AM
浜田省吾のファン層は実に幅が広い。ライブ会場に行けば、下は親に連れられた小学生から、上は70歳近くの年配の方まで、様々な世代のファンに出会うことができる。
それだけ世代分布の広いロックのライブというのも珍しいのではないだろうか。
どうしてそれほど支持層が広いかといえば、やはり30年間の音楽活動で蓄積してきた曲のバリエーションの豊富さだろう。
その30年の間に、浜田省吾は23歳から53歳となった。それぞれの時期に、その世代の視点で真摯に曲つくりをし続けた結果、10代から60代までの世代が共感する曲のラインアップが出来上がったと言えよう。
「19のままさ」では、予備校生の儚い恋愛を唄い、学生や若い社会人の共感を得ている。「星の指輪」では、子供のいる夫婦が束の間のデートを楽しむ様子を描いた。「君と歩いた道」では、老境に達した視点から人生をふりかえる。
このように浜田省吾の曲には30年分の蓄積があるのだ。これはどんな大ヒット曲を生み出すミュージシャンでも、簡単には真似のできることではない。
10代のミュージシャンが50代の境遇を歌にしても説得力は無い。逆に50代のミュージシャンが新たに10代の心情の歌をつくってもリアリティに欠けるだろう。
やはり、浜田省吾がそれぞれの時期で、そのときの思いを真剣に曲にしてきたから、例え古い曲であっても支持されるのであろう。
例えばアルバム「J.BOY」を現在の高校生や大学生が聴いたとしても、充分にインパクトある仕上がりになっている。
だから、10代や20代のファンも新たに獲得することができているのだ。
ところで、音楽CDのメインの購買層は10代だという。かつて10代であった現在の30代や40代の世代は、昔はよくアルバム購入をしていたはずなのに、現在はあまりCDを買わないらしい。
遠山も現在30代だが、確かに浜田省吾のアルバムを除いては、音楽CDを買うことは少なくなった。
そのためか、音楽の制作会社は10代をターゲットとしたマーケティング活動を展開している。
必然的に若いミュージシャンが重宝され、そのミュージシャンが加齢していくと賞味期間切れのような扱いをする。
ミュージシャンが年を重ねたとき、同一世代の共感を呼ぶような曲つくりをするのが、何だかタブーとされるような雰囲気もある。
これはマーケティングの功罪ともいえないだろうか。
確かに統計的に裏付けのある10代を対象とした曲つくりは、マーケティング的にセオリーなのだろう。
しかし、それがウケるからといって、長期間ずっと同じ手法で特定マーケット層に向けた商品(曲)供給を続けたら、やはり人間は飽きてしまう生き物なのだ。
10代が成長して20代や30代になったとき、自分の気分にあった音楽を耳にする機会がなければ、CDを買おうとは思わなくなってしまう。
つまり、若年層を対象としたマーケティング活動が、人口比の多い30代以上の年齢層を置き去りにしているともいえよう。
短期的には10代の購買層への訴求は正解かもしれないが、長期的にはより大きな市場を喪失していると言えるかもしれない。
折りしも、日本の人口構成は少子高齢化に向かって突き進んでいる。この先、10代のマーケットは益々縮小していくのだ。
都心部であっても小学校の学級数は減り、統廃合が進んでいる。地方になると、もっと事情は深刻だ。
そんな縮小していくマーケットに照準を固定し続けるのは、やはり正気の沙汰ではないだろう。若手のシンガー・ソング・ライターが登場して、ヒット曲を連発する様子を伝える歌番組には、かつての太平洋戦争末期の大本営発表を連想させられる。
ああ、音楽制作者側も必死なんだなと。もちろん、遠山はリアルタイムで大本営発表を聞いたことは無いわけだが。
もちろん、今後の人口動態などは音楽制作会社はキッチリ把握している。そんなことは言われなくてもわかっている。30代や40代を対象とした曲を、それなりのドラマとタイアップしてプロモーションをしていると主張するだろう。
それでも30代以降の世代は手強く、なかなかCDを買おうとしないと弁明するに違いない。
問題は根深く、30代以降の年齢層に支持されるミュージシャンを育てる努力を怠ったのではないだろうか?
10代の小娘に「オヤジ!頑張れ!」という応援歌を作って貰ってもありがたくはない。では同世代のミュージシャンはというと、バンドを解散してしまったり、アルコール依存の末に自殺してしまったりして、多くは現役でなかったりする。
幅広い支持層を獲得している浜田省吾に頼りたくとも、浜省はテレビに出ないというのが定説になってしまった。
新しく30代や40代にウケるミュージシャンを育てるには時間がかかる。
それ故に、浜田省吾は30年間という音楽活動の蓄積が最大の武器とも言えよう。このキャリアは誰にも真似ができない。
ビジネスにおいても、その時期に応じて積み重ねてきた商品開発や顧客からの信頼が、何にも変えがたい財産となるはずである。
やはり“継続は力”なのである。
投稿者 : 03:12 AM
浜田省吾の所属事務所であるROAD&SKYは、公式なファンクラブも運営している。普通、ファンクラブ入会のメリットと言えば、真っ先に思い浮かぶのはライブ・チケットの優先予約ではないだろうか。
人気ミュージシャンのライブ・チケットは、競争率が高くて簡単には確保できるものではない。イベンターのチケット発売日には、予約のための電話回線が繋がらず、何時間も待たされることは珍しくないだろう。
そういう事情を知っているからこそ、ファンはファンクラブにチケットの優先予約権を期待する。
ミュージシャン側もファンクラブの優先予約で入場者数を確保して、囲い込みができれば都合が良いだろう。そうすればライブの収支予測も立てやすくなる。
しかし、浜田省吾の公式ファンクラブはチケットの優先予約をしていない。ホームページのファンクラブ入会案内にも、「チケットの優先予約はしません」とハッキリ告知している。
これを意外と感じる人は多いだろう。遠山も過去に幾度と無く次のような会話をしてきた。
遠山「今度、浜田省吾のライブがあるんだけど、なかなかチケットが取れなくて困るんだよね。」
友人「それなら、ファンクラブに入会してチケットを取ればいいじゃん。」
遠山「それが、ファンクラブはチケットの優先予約はしてくれないんだよ。」
友人「エッ!! 信じられないな。そんなのファンクラブのメリットは無いよねえ。」
恐らく浜田省吾ファンであれば、そんな話題を耳にした経験はあるはずだ。
このような、ある意味では非常識とも言えるファンクラブにチケット予約優先権を認めない理由を、浜田省吾は次のように解説している。
「ファンクラブにチケット優先権を認めると、現状ではファンクラブの会員しかライブに参加できないことになってしまう。ファンにはいろいろな人がいて、初めて浜田省吾の音楽に興味を持つ人もいる。ファンクラブ会員しかライブに参加できないことにしてしまうと、そういう人がライブに来れなくなってしまう。それは健全な状態ではないと思う。」
ここにも浜田省吾の人柄と言うか哲学を感じ取ることができないだろうか?
ファンクラブが優良顧客となり、イベンターを通さなくてもチケットが完売できれば、ライブ運営もいくらかは楽になるだろう。
そのメリットを捨ててまで、全てのファンが公平にチケットを取るチャンスを提供しようというのだ。
その平等や公平を求める意識は、さすがと言うしかない。
翻って、90年代以降の企業の不祥事を振り返ると、悲しいかな日本には不平等感が充満していることに気が付く。
古い話になるが、1991年には大手証券会社が自社の優良顧客に対して、株取引の損失補てんや利益の追加をしていたことが発覚した。小規模取引の個人客が株取引で損失をしても、その補償がされることはありえない。
というか、株取引に関する損失はクライアントの自己責任というのが原則のはずだ。しかし、優良顧客(総会屋だったりするのだが)に対しては原則を曲げて損失補てんを続けたことが明るみになった。(この損失補てん事件を起こした山一証券は、1997年に破綻してしまったわけだが。)
それから、公共事業に関する談合事件は、昔から現在まで途絶えることなく続いている。大手の業者が落札順を決めて、その順番通りに仕切られる。そして、建設業では工事を下請けに丸投げというのもお馴染みのパターンとなっている。
巧妙なところでは、仕様作成やコンサルタント業務の入札を格安で落札し、その後の本事業の仕様を自社に有利に設計するケースも後を絶たない。このようなコンサルタント業務入札では「1円落札」なんてことも話題に上る。
このように、大手企業や公共事業ですら、平等や公平という原則を見失うこともある。もちろん、ビジネスの世界では戦略として、優良顧客やリピーターに優遇策をとるのは間違いではない。
しかし、利益追求のあまり法令違反をすることに躊躇いを感じなくなるようでは問題だ。それではコンプライアンス(法令遵守)に対して不感症と言われても仕方がない。
「危ない橋を渡る」とか「やったもの勝ち」という、グレーな仕事ぶりを賛美するような風潮は実に危ういものなのだ。
法令の網をくぐり抜けて利益をあげたとすると、それを維持するには法令違反を継続しなくてはならない。そんな事を続けていれば、いつかは綻びが出て破滅への道が待っている。
そのようなグレーな仕事は、組織ぐるみで継承されることも多い。そんな環境に身を置いていると、自分のやっていることが法令違反であるという自覚が薄れることもあるだろう。
しかし、法に触れることに慣れが生じても、その罪は決して帳消しにはならない。慢性的な法令への抵触行為が続けば、いつかは必ず手痛いしっぺ返しが来るものだ。
そこで、事業の長期継続性ということを真剣に考えるなら、法令に沿った内容で営業を行い、その上で適正な利益を出すという仕組み作りに励む必要がある。
そのためには顧客からの信頼を得る必要があり、公平な対応とコンプライアンスの徹底と言うのは最低条件となるだろう。その姿勢を常に示し続ければ、顧客が猛烈なファンとなってくれるはずである。
投稿者 : 03:10 AM
音楽においてロックンロールの対極にあるのがクラシックではないだろうか。ロックが観客も参加して大騒ぎする“動”の音楽で、クラシックは落ち着いた聴衆が聴き入る“静”の音楽といえるだろう。
通常のロックコンサートであれば、そこで使用される楽器はギター・キーボード・ドラム等というのが一般的なイメージだ。
チェロ・ビオラ・バイオリンといういわゆるストリングスは、普通ならクラシックの楽器だ。しかし、浜田省吾のライブツアーであるON THE ROAD 2001では、そのストリングスを同行してバリバリのロックに取り込んだ。
ツアーの当初はライブの中でバラードを3曲演奏するだけの役割だったストリングスだが、ライブの回数を重ねるうちにヒップホップやロックまで参加して、新境地を披露するようになった。
ストリングスメンバーの4人は東京芸術大学出身の女性で、アカデミックな才媛たちだ。ロックや歌謡曲とは縁遠い教育を受けてきたはずだ。それでも浜田省吾のロックライブに参加して楽しそうに演奏する姿は印象的だった。
なぜ、ロックのライブにストリングスを取り入れたのかというと、「なかなか生の弦楽器の音をコンサートで聴く機会がない地方のファンに楽しんでもらいたくて」と浜田省吾は語っている。(日経エンタテイメント 2000年2月号より)
その目的はファンへのサービスということだろう。
既に自分たちで確立したロックライブのスタイルでも満員御礼となるわけだから、その手法を継続するのが無難な気はする。
だが、そこに気の緩みとかマンネリの危険性が潜む。安定的な評価はマンネリと紙一重と言えるかもしれない。
そこで、意外とも思える取り合わせで、より高いレベルでのファンサービスを図る意欲はさすがだ。
このようなマンネリとの格闘は、外食産業でも垣間見ることができる。定番商品だけで充分に人気店となっても、年に何度かは新メニューを登場させる努力をしているものだ。大抵はおいしさに納得がいくメニューだが、時には外すこともあろう。湯豆腐にイチゴジャムをトッピングするようなインパクト勝負に出て、失敗するのも愛嬌かもしれない。
もちろん、新メニューの追加など一切無しに繁盛している専門店もある。伊勢の赤福もちのように、それ一本で営業を続ける老舗は存在する。だが、それは長い歴史で培った信用であり、一朝一夕で築き上げられるものではない。
やはり、大多数のビジネスマンにとって、新しいサービスや新企画には絶えず挑まなくてはならないものだろう。
そんな新しいものへのチャレンジは、疲弊しきった組織にはハードルが高い。組織の内部で風通しが悪く、不信感がうごめくような人間関係では、冒険は許されない。
浜田省吾のライブで、ストリングスがヒップポップやロックに参加するようになったのも、ストリングスのメンバーと従来からのミュージシャンが深く熱いディスカッションを交わしたからだ。
その際に、浜田省吾が独善的であったら、ロックにまでストリングスが加わるコラボレーションは生まれなかっただろう。
それはミーティングで本音を語り合える環境作りに成功したということだ。ただ、そのような意見交流が出来るようになるまで、数ヶ月は要したようだ。真に深いディスカッションができるようになるには、ある程度の時間は必要だ。
何か新しいことに挑みたくても、組織の中で自由に物が言えない雰囲気があれば、どうしてもその組織の活動は停滞してしまう。
そんな組織が嫌だと思いつつも、そこからは離れられないのがサラリーマンの辛いところだ。
ただ、諦めてしまえばそこで終わりである。その組織に所属している間は、人事異動でもない限り停滞した雰囲気に身を委ねる事になってしまう。
それを変えるには、誰かが一歩踏み出さなければ始まらない。
強い組織というのは、新しい企画について冒険ができるものだ。その前提条件として、事業の見通しなどを本音で語れる人間関係が必要だ。各自が方向性について意見を戦わせても、互いの信頼感を見失うようなことがなければ本物と言えよう。
投稿者 : 03:08 AM
80年代半ば以降のバブル経済では、土地や芸術作品などが投機の対象となり、三菱地所のロックフェラーセンター買収やソニーのコロンビア映画買収等の象徴的出来事があった。
当時、東京の不動産価格は青天井と言われ、貸しビルやマンションは、その実質的価値以上の評価額で売買されていた。
不動産オーナーは、物件を利用したいという本来の顧客の要望には応えようとはせず、より高値で売却できる相場師(ブローカー)との取引を熱望した。堅い職業と思われていた銀行も、このブームに便乗して怪しげな相場師に資金の供給を続け、バブル経済過熱に加担した。
不動産は投機目的の相場師の手を経た後では、その価格は適正水準から乖離し、もはや誰もが手を出すことができない金額まで膨れ上がった。こうした現象は、土地転がしやマネーゲームと呼ばれ、海外からウサギ小屋と揶揄される狭いマンションを、ビジネスマンの高嶺の花としてしまった。
その異常さに誰もが気づく頃になると、土地神話は崩壊し、バブル経済は一気にはじけた。バブル経済の後遺症を治すため、銀行は不良債権処理に躍起となり、企業は適正規模への回帰を図るため血の滲むようなリストラを敢行した。バブル崩壊後に、生活に窮したり、人生計画の軌道修正を余儀なくされたりして、辛酸を嘗めた読者の方も多いだろう。
浜田省吾は1990年に発売したアルバム「誰がために鐘は鳴る」に収録された「詩人の鐘」の中で、「銀行と土地ブローカーに 生涯を捧げるような 悪夢のようなこの国」とバブルに溺れる日本経済を糾弾した。
これは無理をして購入したマンションが、バブル崩壊後には評価額が暴落し、生涯をかけて支払うローンだけが残った多くの人達の心情を代弁している。
そこには、マネーゲームを放置した国への怒り、重い負債だけを背負わされた人達への思いが込められている。
「詩人の鐘」の発表から15年後の2005年には、マンションの耐震強度偽装問題が発覚し、翌年の2006年初めにはライブドア粉飾決算問題による東京証券市場の混乱が生じた。
マンションの耐震強度偽装問題は、マンションの安全性よりも建設コストを下げることを優先し、利益を上げるためなら法律を侵し、住民の生命を脅かしても構わないという企業エゴを白日の下に晒した。
ライブドアの粉飾決算や脱税問題は、球団買収や国政選挙に乗り出した時代の寵児ですら、赤字決算を黒字に粉飾して投資家を欺き、自社の利益をひたすら追求する現実を見せ付けた。
これらの出来事は、事業の本質で利益を出すのではなく、違法な原価低減や投機で暴利を得て、そのしわ寄せを弱者に押し付けるという構図であり、15年前のバブル期と何ら変わらない。
バブル経済と現在の耐震強度偽装や粉飾決算・偽計取引問題は、他人を泣かせてでも暴利を貪るという点が共通している。
しかし、そのような政策や事業は長続きするものではない。人々の支持を得られなければ、短期的に利益を上げることには成功しても、その成功を継続し続けることはできない。
実際に、バブル経済は崩壊し、耐震強度偽装をした建築会社は倒産し、粉飾決算で投資家を欺いた会社の経営者は退陣した。
それでは、事業の本質とは一体何かと言えば、それは「顧客満足」に尽きる。どんな事業であっても、顧客の支持が得られなければ、長期間の安定経営は成立しない。顧客の支持を受けるためには、当然ながら事業者が提供するサービスについて、顧客の満足を得る必要がある。
つまり、事業の本質とは顧客満足を得るために、継続的に努力をしていくことだ。これは会社経営全体でも、各自に与えられた部署や担当という現場でも共通してあてはまる。
浜田省吾は、自らの最大のファン・サービスはライブであると位置づけている。この方針は決してブレていない。
ライブ・ツアーを敢行するには、バンドや舞台装置等の裏方を引き連れて全国を移動する必要がある。大勢のスタッフを動員するからには、当然ながら経費も掛かる。実はミュージシャンにとって、ライブの経費は負担であり、利益性は良いとは言えない。
単に利益を追求するなら、ライブは行わず、CDのみを多量にセールスする事を考えた方が効率は良い。ライブは極力行わず、テレビ出演でCDの宣伝を繰り返し、CDセールスを重視するミュージシャンも存在する。
だが、浜田省吾は音楽業界では異色とも言えるスタイルを貫いている。それは、テレビ出演やコマーシャルやドラマとのタイアップはほとんど行わず、CDのセールス・プロモーションは控え目だ。
一方で、採算性が良いとは言えないライブは、精力的に行っている。浜田省吾のライブは「ON THE ROAD」と呼ばれ、そのON THE ROADツアーのチケットは発売即日に完売となってしまう。
ファンの間でも、浜田省吾のライブは年々進化しているとの評価が高い。デビューから30年を経過しても、更にライブの質は向上しているのだ。
この質の高いライブを提供し続けることで、CDアルバムも安定数が売れている。つまり、浜田省吾はファンが喜ぶことを第一に考えて行動し、その上でプロモーターとして、採算性も両立させる手腕を発揮しているのだ。
ファンや顧客を無視した利益追求では、事業は長続きしない。事業を長期安定化させるのは、徹底した顧客満足への取り組みに尽きる。
事業者が提供するサービスに、猛烈なファンがつけば、経営は安定する。その基本を浜田省吾から学ぶべきである。
投稿者 : 03:05 AM
理想と現実。浜田省吾の曲の中に度々登場するフレーズだ。理想は夢、現実は日常とか暮らしという言葉に置き換えられることもある。
「J.BOY」-“掲げてた理想も今は遠く”“打ち砕け日常ってヤツを”
「Midnight Blue Train」-“描いた夢と叶った夢がまるで違うのにやり直せもしない”
「星の指輪」-“若い頃の計画(ゆめ)なんて もう思い出せない 忙しいだけの仕事に追われているうちに”
このように若き日の理想や夢と、それに立ち塞がる現実について、葛藤する様子が描写されている。
そんな理想について、少年期と大人になってからのとらえ方の違いを、浜田省吾は次のように語っている。
「 (子供の頃は)理想と違ったからといってゲンメツしても、それをつくったのは自分だからね。子供のころは家庭にしても学校にしても自分がイヤだと思うものは、みんな人から与えられたものでしょ。そこから飛び出すことがひとつの目標だし、それを拒否することが、ひとつのストレスのはけ口でもあるしね。ティーンエイジロックと呼ばれるものの詞の、唯一のポイントがそれでしょ。だけど、そこを過ぎた人は、自分のつくったものを捨てて出るか、それを壊してつくり直すしかない。それは、たいへんなことだよね。だれの責任でもないから、人のせいにもできないし。」(ef 1986年11月号より)
つまり、少年期は理想どおりに現実が運ばないとき、それを人のせいにできる。実際、学校にしても企業の新人教育にしても、その枠組みを用意したのは大人の世代だし、それに不満をぶつけるのは少年の特権ともいえよう。
かくいう遠山も、集団行動や規律を嫌う小生意気なガキだった。そのくせ、ひとりじゃ何もできずどこへ行くのかもわからない中途半端な反抗ぶりだった。
授業を抜け出すことはあっても、タバコをふかしたりゲーセンでたむろすることは無かった。数学の授業をサボって、世界史の自習をするような意味不明の行動をしていたような気がする。
このように特に明確な目的も無く、ただ大人が作った軌道に乗るのを拒むのは、ズルい対応だったかもしれない。拒否する以上は、自分で道を切り開かねばならないのだが、そんな苦労を背負う覚悟は無かった。
それが大人になってからの批判の矛先は自分に向かうものだから、始末におえなくなってくる。何か不平不満を口にすると、その原因には少なからず自分の怠慢が含まれている。
すると高校生のように、自分が潔白であることに勝ち誇って、無邪気に社会を批判することに引け目を感じたりしてしまう。
それは動物愛護に目覚めた0Lが、ミンクのファーや皮のブランド・バックを買い込むことを止められない様なあざとさだ。
そこで日々の暮らしに何らかの妥協をして、こんなはずじゃなかったという思いを封印する生活を送ることも多いのではないだろうか。
そんな現実とは、疑問や不安、絶望や退屈などネガティブな感情を打ち消しきれないものだ。
誰しもが抱えるそんな問題について、浜田省吾は解決を請け負うというスタンスはとっていない。
ただ、ライブで良質の音楽を提供し、一時的な高揚感や慰安を感じ取ってもらうように務めているという。
そして、ライブが終わっても参加者が前を向いて頑張っていこうと思えるような気分になれたら、それがミュージシャン自身の救いにもなると語っている。
それでは、現在は30代~40代の働き盛りのビジネスマンたちが、若き高校生だったころ、どんな夢を描いていたのだろうか。
強烈な特定の職業への憧れから、必死の努力をしてその職業に就くことを成功した人もいるだろう。
ただ、多くは漠然と学歴のレールに乗り、深く考えることも無く進学をして、給与や処遇を比較しながら就職先を決めたというパターンでは無いだろうか。
そしてほとんどの場合は、かつて憧れていた職業とは全く違うことをしている。
だからと言って、就職希望の変節が悪いと言いたいわけではない。人は自分の適性について若いうちから把握できてはいない。また社会的環境によって、就業の選択肢が狭くなることもあろう。
だから、特に何がしたいという明確な目標がなくても、まずは何でもやってみるという行動力が大事なこともある。
そして岐路に立った時、その瞬間ごとに後悔の無いチャレンジができているかが大切だ。そんな時に迷いを断ち切るきっかけが、小説であったり音楽であったりするものだが、浜田省吾の曲が重大な決断の背中を押してくれたというケースも多いように思う。
何しろ現代の詩人でもあり哲学者でもある浜田省吾が、時流と対峙しながら練りに練った歌詞をつくっているのだから。そんな優れた曲は時が経過しても支持されていくだろう。
投稿者 : 03:02 AM
浜田省吾は自らの音楽活動について、ライブとCD制作を二本柱と位置づけている。いわゆる車の両輪ってことで、どちらか片方が欠けても音楽道を突っ走ることはできやしない。
そのライブとCD制作については、次のように語っている。
「 変なたとえですけど、コンサートは産業でいうと“実業”なんです。現場にたくさんの人が集まって成り立つ。利益は少ないけど、確実に仕事をしてみんなが生きている。それに対して、CD制作は投機。金融業に近い。あるとき当たって大儲けする、というね。
でも、バブル経済にしても、そういう方向ばかりになって弾けたわけでしょう。ちゃんと製造業があった上で、金融や不動産投資があるべきだと思うんですよ。だから、コンサートにこだわっている僕は、その一番の根幹をやっている。
ライブに向かう意識も、昔はまず自分が先だったのが、今はまずオーディエンスがいて、次に俺たちがいるっていう感じになってます。これだけ長く自分が音楽をやってこれたのは、やっぱり彼らが支えてくれたからです。」(日経エンタテイメント1999年6月号より)
何という冷静な見方をしているのだろうか。普通、ミュージシャンであればCD制作も立派な創作活動であり、充分に実業と言えるはずだ。
それを敢えて投機と言い切ってしまうあたり、芯の強さを感じる。
恐らくCD制作にはライブほどの人手と経費はかからず、メガヒットとなったときには、その分莫大な利益を生み出す可能性があるから投機という表現をしたのだと思う。
逆にライブは大勢のスタッフが関わることが前提となり、利益を出すには様々な工夫が必要となる。文字通り汗をかいて必死に稼ぐ仕事だ。
世の中の経済活動でも、モノ作りをする製造業がしっかりと機能した上で、投機に励む金融業が成立する。その投機でラクに稼ぐという感覚が染み付いてしまうと、地味で苦労も多い製造業が割に合わない仕事に思えてしまう。
その結果、製造業離れが進んで、モノ作りをしていた人たちが不動産や株式の投資に血眼になった時代があった。
そう、バブル経済と呼ばれた1980年代後半の現象だ。
そのバブル経済が崩壊することを、浜田省吾は独特の感性で予見していたと他の章で述べた。それなら、バブル経済の後始末にジタバタする世間に対し、「そらみたことか」と評論家気取りですましていることもできたはずだ。
しかし、浜田省吾はそんな態度は取らなかった。その導き出した答えは次のようなものだった。
「 特に90年代に入って、こんな不景気ですごく厳しい時代になって、その中をみんな頑張って過ごしているわけじゃないですか。僕自身の音楽人生や作品のことだけを考えるなら、時間をかけてアルバムをつくった方がいいかもしれない。でも、これまで僕を支えてくれた人たちがそれぞれの現場で一生懸命頑張っているのに、自分だけが隔離された別世界にいて、音楽をつくるのは恥ずかしいと思った。」(日経エンタテイメント1999年6月号より)
つまり、苦労も多く利益も少ないライブは止めてしまって、じっくりとCD制作に専念することもできた。でも、それだと必死で不況に耐えているファンの人たちに申し訳ない。だったら、ファンが本当に喜んでくれるライブを続けて楽しんでもらいたい。そう考えて、ON THE ROAD 2001という前代未聞の4年間に及ぶライブツアーを敢行したわけだ。
ライブが製造業という浜田省吾的解釈であるなら、どこまでもモノ作りにこだわっていることになる。まさに頑固一徹の職人気質と言えよう。
そこには「稼げれば良い」というお気楽な考え方は存在しない。ここまでファンのためを考えて行動するミュージシャンだから、そのファンも裏切るはずは無い。ライブはどの会場も満員御礼だ。
話を日本経済に戻すと、バブル後のリストラや企業破産地獄を経験して、製造業は本業回帰を目指した。その血の滲むような努力の甲斐があって、景気は落ち着いてきたと言えよう。
しかし、今またネットトレーダーがもてはやされ、空前の株式ブームが起きている。自宅に引き篭もって株の売買益で稼ぐことや、ネット広告などの不労所得によって生活することが若者の憧れのライフスタイルになっている。
そんな虚業が流行する時代の空気は、30代~40代のビジネスマンの皆さんならデジャビュ(既視感)の錯覚が起きないだろうか?
確か過去にもそんなムードで盛り上がった時期があったはずだ。
そう、1980年代後半のバブル期だ。あの時ほどの浮かれ気分では無いにしろ、今もモノ作りからかけ離れたところで稼ごうとする人々が増えている。それを煽るマスコミ情報も氾濫している。
例えば、「ネット株売買で1億稼ぐ」「アフェリエイト月収を100万円にする」「ダイエットで稼ぐ」こんなキャッチコピーがあちこちで目につかないだろうか。ちょっと考えれば胡散臭さ100%だと気づいても良さそうなものだ。
バブルの後には強烈なシッペ返しが待っている。その事は痛いほど学習したはずだ。その予防法は、浜田省吾が身を持って教えてくれた。
自分にとって何が本業であり、どうすれば顧客は喜んでくれるのか。その原点を見失うことなく事業を継続することに尽きる。欲におぼれて、投機に走ることなかれ。
投稿者 : 02:59 AM
ショービジネスに関わる人々の心意気を表すスローガンとして「SHOW MUST GO ON」というものがある。
直訳すれば、「ショーは止められない」ということだ。雨が降ろうが、槍が降ろうが、戦争になっても、病気になろうが、破産しようが、親の死に目に会えぬとも、それでもショーを中止することは無いという壮絶な決意表明でもある。
浜田省吾は足かけ5年にもおよぶロングランツアーのON THE ROAD 2001で、2001年のアリーナツアーのテーマを「THE SHOGO MUST GO ON」と決めた。
これは浜田省吾の“ショーゴ”と「SHOW MUST GO ON」をもじったものだ。
このスローガンをプロ意識と理解すれば、一般社会で働く人々も共感できる部分はあるのではないだろうか。
例えば、鉄道マンであれば台風や大雪であっても、何とか列車の運行を継続しようと努力している。その関係会社の社員も含めて、運行を支えようと必死の努力をしている。
だが、そうした努力は乗客は認識していなかったりする。ダイヤが狂えば心ない誹謗を受けることもあるだろう。それでも職業意識に燃えて列車の運行を地道に継続している。
商社マン・銀行マン・スーパー店員に公務員など。誰もがプロ意識に燃えて仕事を継続しているから、日本経済は今日も回っている
実は「THE SHOGO MUST GO ON」というテーマは、戦時下に近い環境でもその真価を発揮した。
2001年9月11日。この日はアメリカで同時多発テロが起き、世界貿易センタービルと米国国防総省(ペンタゴン)が破壊された。この直後からアメリカは過度な警戒態勢を敷くようになり、日本国内でもアメリカ大使館や米軍基地の警備は厳しくなった。
また、旅客機をハイジャックしたテロであったため、航空機を利用した海外旅行等は自粛ムードが漂い、旅行業界は大きな損失を出していた。
そのような時期の10月13日に、浜田省吾は沖縄県の宜野湾で野外ライブを行っている。
沖縄といえば、ご存知の通り米軍基地が密集している地域だ。9・11同時多発テロから1ヶ月しか経っていない時期で、人が集まるライブは危険であるという察しはつく。
それは戦時下のピリピリとしたムードであっただろう。誰もがこの公演は中止した方が良いと忠告をしたそうだ。
それでもライブを敢行した浜田省吾は、次のように語っている。
「 日本全体で考えると、米国の基地を沖縄に押しつけてるわけですよね。戦後の歴史でそうなってしまったんですけど。なのに本土に住んでいる人間が、“あそこが危ないから行かない”というのはあり得ないだろうと。だから“絶対にやらなきゃいけない。特にこの時期にやらなきゃいけない”と思ったんですね。
ステージの上でも言いましたけど、“ジェット機の爆音で音がかき消されるようなことがあったとしても、それが沖縄の現実じゃないか”と思ってました。実際は、そんなことはなくて、のどかな雰囲気だったんですけど。」(日経エンタテイメント 2002年1月号より)
誰もが身の危険を感じて敬遠するような時に、敢えてショーの継続をやり通した心意気はサスガとしか言いようがない。
これが本当の“歌バカ”なのかもしれない。
沖縄のファンも、このライブには特別の印象があっただろう。当然に中止になると思われていたライブを、危険を承知でやってくれた。
米軍の厳戒態勢の影響で観光業はダメージが大きくなり、日常生活も不便な局面もあっただろう。そんな中で、普段と変わらず浜省がライブをやって元気付けてくれた。その行動力に胸を熱くしたファンは多かっただろう。
そこまでやれば、ファンは絶対に離れない。
日常のビジネスは、実は単調な仕事の繰り返しなのかもしれない。その仕事の一つだけを取り出してみれば、大したことはやっていないと思えてしまうものだ。
しかし、それを毎日毎日繰り返し、風邪をひいても、身内に不幸があったとしても継続し、何十年もやり抜けばそれは周囲から絶大な信頼をされるものだ。
何か事業を行う場合に、顧客から無条件の信頼を得ることができれば、それは大成功したと言えるだろう。
その信頼は簡単には得られない。短期的に莫大な収益を上げることができても、事業としての信頼感は醸成されない。
地味であっても、長期間安定して継続している事業こそ、真の評価に値すると言えないだろうか。
その継続性というものが、例え戦時下となろうとも中断することが無いというのは、これ以上は無いアピールだ。
つまり、何があってもやり通すという気迫がお客を安心させる。そこまでビジネスを徹底して継続すれば、お客は逃げない。
私達の日常生活には小さなつまづきから、大きな壁までいろいろな障壁があるものだ。ビジネスでも同様だ。そんないろいろな困難から逃げず、地道に障害物を取り除いて仕事を継続していくことが成功への正攻法と言えよう。
投稿者 : 02:58 AM
親子の相克というのは、小説や映画では普遍的なテーマとなっている。もちろん、音楽でも同じだろう。
子にとって親は最初の社会との接点であり、成長するにつれて親を超えようとする。その際に生じる心理的葛藤は、文芸のネタには最適だ。
浜田省吾にも当然ながら親子間の葛藤はあり、特に父親との衝突は凄まじいものだったようだ。
浜田省吾の父親は警察官であり、今でいう転勤族だった。そのため、浜田一家は頻繁に引越しを経験した。
父親は子煩悩で、浜田省吾も父を慕っていた。浜田省吾は父親の強い勧めもあって、まじめに勉強をして広島県内でも有数の進学校へ進んだ。
それまでは平穏な家庭環境であったが、浜田省吾が高校へ入学した頃から、父親との関係がギクシャクする出来事が続いた。
まず、浜田省吾はまじめに授業を受けなかったらしい。学園紛争や反戦デモの機運が高まっている時期に、利己的な進学のことしか話題に上らないクラスメートに辟易した。
そんな進学校独特の雰囲気に馴染めず、野球部に入って部活に熱中したり、生徒会活動に没頭したりした。
高校生活で溜まった鬱憤を、反戦デモへの参加や、職員室前でボブ・デュランの「時代は変わる」を独特の歌詞を付けて唄ったりして発散していた。
そうした所業を警察官の父親が聞き及ぶに至り、親子の対立は臨界地点に達した。
「お前を過激派にするために高校へ入れたのじゃない。ワシは恥ずかしくて明日から仕事へ行けん。学校を辞めい。」
こうして父親自慢の出来の良い息子は、その評価を暴落させた。社会的な反戦デモ隊と官憲の対立という関係を、家庭内にも持ち込んだのだから始末に終えない。
大好きだった父の期待に沿えない苛立ちと、矛盾した学校や社会の仕組みにフラストレーションは蓄積される一方だっただろう。
それでも高校を卒業し、浜田省吾は浪人生活を送ることになった。しかし、予備校に通うことはなく、遊びまわっていた。
そんな様子を父親が知り、大喧嘩となって浜田省吾は家出をした。
家を飛び出して転がり込んだ先は、京都に住む友人の下宿だった。その友人は彼女と同棲しており、一緒に暮らしていると何かと不都合が生じた。
男女の気配を感じると、浜田省吾は遠慮をして野宿に近い生活をした。そんな生活を数ヶ月間送ると、風邪をこじらせて深刻な体調不良となった。
そこで意地の張り合いを止めた浜田省吾は広島の実家に帰った。その時、父と母は何も言わず向かい入れ、それ以来浜田省吾は父親と喧嘩をすることは無かったという。
その後はまじめに勉強をして、神奈川大学に進学した。
これは有名なエピソードだが、遠山は大学生のときにその事実を知った。そして、成功する人物っていうのは家出の一つくらいしなくてはいけないのかと単純に思った。
しかし、家出をして半年間も生き抜くエネルギーは、自分には無いよなと自己認識をしたものだ。
現在でも親子の対立は社会にありふれている。しかし、親への反抗が家出や自立という方向に向かうのではなく、引き篭もってニートになるという形に姿を変えてきたようだ。
引き篭もりは、子の成長や自立とは反対の方向に作用する。これでは何の解決にもならない。子が家出をするようなパワーも無く、ひ弱になっているのかもしれない。
経済が成熟した今、社会のあらゆる場面で争いを回避する風潮にある。それが家庭の中にも浸透して、親子間でも本音を言わないという現象が生じていないだろうか。
浜田省吾は不満を口にして行動することで、深刻な親子の対立を招いた。反発心は家出をするほど凄まじく、両親はそれを受け入れた。
だが、これが現在の一般的家庭像であれば、恐らく互いに遠慮して本音をぶつけることなく心にシコリを残す方法を選択するのではないだろうか。
つまり、子の反発心のキバを抜くことが日常的に行われるのだ。去勢された子は反発することもなければ、自立することもできない。
大学に進学した後の浜田省吾は、学園紛争に明け暮れる大学に愛想を尽かし、半年で退学した。その後はミュージシャンとしてデビューして、売れない数年間を経た後でロック・スターの階段を登った。
このように浜田省吾の人生は、決して順風満帆ではなかったのだ。普通であれば社会からドロップ・アウトしてしまうような試練を幾度と無く経験している。
現在、受験失敗・ニート・自己破産・事業失敗・離婚など、さまざまな悩みを抱える人は多いだろう。それが原因で家庭も混乱してしまう局面もあるかもしれない。
しかし、諦めてしまえば道は続かない。今はどんなに低いところにいようと、必ず少しづつ階段を登る決意をすれば、過去の失敗が財産となることもあるだろう。
浜田省吾の歌に励まされるのは、彼自身が苦悩を昇華させてきた経験を有しているからだろう。
Never Giveup
言葉にするのは簡単だが、事業を継続させたいなら、決して諦めないことだ。
投稿者 : 02:56 AM
「ベストセラーよりロングセラー。」
これは著作物の作者であれば、誰もが憧れるものだろう。ベストセラーとは短期間に凄い売上げを記録することで、ロングセラーとは長期的に継続して売れ続ける現象だ。
一瞬で爆発的なセールス記録を作って、印税収入がガッポガッポ入るベストセラーも捨て難いが、それよりも長い間売れ続けて人々の記憶に定着するロングセラーの方が制作者冥利に尽きるだろう。
浜田省吾の楽曲は、もちろん1992年に200万枚近く売り上げた「悲しみは雪のように」のようなベストセラーも存在するが、その多くはロングセラーと言えるだろう。
アルバムやDVD等の売り上げもロングセラーの傾向はあるだろうが、カラオケで歌われる曲は古いものが多い。
「J.BOY」や「もう一つの土曜日」は1986年、「MONEY」は1984年にリリースされた曲だ。
30代から40代のビジネスマンが集うカラオケでは、誰かがこれらの曲を必ず歌うのではないだろうか。
このように多くのファンに愛され、口コミによる評価で売れ続ける曲はロングセラーの称号を得ても良いだろう。
その一方で、口コミでの支持とは対極の商業音楽も存在する。
何よりも売り手側の論理に基づく、えげつない程のマーケティング主導の音楽だ。別に音楽だけに限らないのだが、商品の品質やサービスレベルが低次元な状態なのに、広告だけは巨費を投じてガンガンに行うパターンだ。
あまりにも売り込み臭が強すぎると、いかがわしさを感じてしまう。
そのような迷惑な情報タレ流しは、今日の日本に溢れている。テレビで、週刊誌で、インターネットで。
「ブレイク間違いないのイチオシ新人」
「1ヶ月で100万円稼げる新規ビジネス」
「寝ているだけで痩せられる最終ダイエット術」
遠山はホームページによる営業活動だけで生業をしているわけだが、眉唾な情報や胡散臭い特ダネを発信しているホームページを見ると辟易する。特に一方的に送られてくる迷惑メールには、怒りを覚えてしまう。
そんなホームページで商売をするには、SEO(Search Engine Optimization)という技術の話題が避けて通れなくなってきている。
一般にホームページで商品を購買したり情報調査をしようとした場合、まずはYAHOOやGoogleという巨大検索エンジンを利用するのがセオリーと言えよう。
これはネット初心者でも知っている常識だ。
検索エンジンのフォーム欄に、調査したいキーワードを入力するだけで、有力な手がかりが掲載されたホームページがズラズラと並ぶのだから、実にお手軽だ。調査をするのに費用が取られるわけでもない。
商品を販売したい側は、その検索エンジンの表示結果に対して、自分のホームページがより目立つ位置に並ぶようにしたい事情がある。
実際に表示結果がより上位にある程、ホームページが閲覧して貰える確率は高くなる。表示結果が2ページ以降になった場合は、ほとんど人目に触れなくなってしまう。
商業立地に例えるなら、検索エンジンの1ページ目に表示されるホームページは、銀座や渋谷の繁華街、または国道沿いの一等地に店舗を構えているのと同様の効果が見込める。
しかし、表示結果が2ページ目以降の場合は、途端に人通りは途絶える。10ページ目以降となっては、もはや砂漠や月面に立地するに等しい。
このような事情はネットショップのオーナーは先刻承知しているので、検索エンジンの上位に食い込ませようと涙ぐましい努力が続けられているのだ。
SEOとは、特定キーワードに関して、検索エンジンの上位に表示させるための技術ということになるが、ここでもマーケティングのための過剰競争が繰り返されている。
大多数の情報を検索する側にとっては、自分が知りたい情報をより素早く把握したいのが本音だ。
目的の情報がわかりやすく解説され、そこで見つけた商品に魅力を感じるなら、検索ユーザーも満足するだろう。
しかし、検索をかけた結果、表示されたホームページは宣伝ばかりで有益な情報が何も無かったら、二度とそのホームページに訪問しない。
販売する側は、とにかく検索エンジンでの表示順位を上げることに腐心して、その対策にばかり精を出す。それが効を奏すると、情報量が不足していても上位に表示されることはある。
すると、そのホームページを踏んでしまった訪問客は、外れをつかんだ感覚に陥る。
検索エンジンは、現在のところは多くのホームページから紹介のリンクがされているホームページが、より価値の高いページだと解釈するシステムになっている。
この特性を逆手にとって、自分のホームページとは何の関係も脈絡もないホームページとリンクを結ぶ行為が一般化している。いわゆる相互リンクだ。
この相互リンクを乱発するサイトが、表示順位を上げるという神話が成立しており、このリンクをする作業のみに没頭する業者も存在している。
このように、“売りたい”“広告をしたい”という思惑を全面に出すことがマーケティングと勘違いすると、ユーザーの感情や要望を漏らしてしまう。すると、検索エンジンの上位表示には成功したが、売上は伸びないという現象に悩むことになる。
ロングセラーを志向するなら、拙速な大量広告は慎むべきだ。顧客から確実に評価して貰えるサービス体制を確立し、情報提供量も充分に用意するなど、足許を固めることが何より大切だろう。
投稿者 : 02:55 AM
ミュージシャンのファンであれば、そのミュージシャンのライブに参加して、ナマの音楽に触れてみたいのが人情だ。
しかし、当のミュージシャンにとって、ライブにかかる経費は頭痛のタネのようだ。というのも、ライブには照明や舞台美術、音響など多くのスタッフが必要で、会場の確保やチケットのセールスにも経費や人手はかかる。
これが全国にツアーに出るとなると、スタッフを丸抱えで移動するわけだから、そのコストは膨大となる。経営で一番コスト高となるのは人件費だが、ライブは多くのスタッフを必要とするため、どうしても経費は高くついてしまうらしい。
ファンはそんな事情にはお構いナシに、お目当てのミュージシャンの全国ツアーを渇望するのだが、その期待にこたえるのは相当にきついのが実情のようだ。
そんな予備知識を得て浜田省吾のライブを観察すると、いろいろと考えさせられる。
なぜかと言えば、浜田省吾のライブには、見るからに費用がかかっていることが明白だからだ。
まず舞台装置が大掛かりで、大型モニターには全国各地の風景が映し出されている。いわゆるご当地映像をふんだんに使う。
2001年の“ON THE ROAD 2001”ツア-からは、アリーナ席の中央部を潰してセンター・ステージを設けている。これはアリーナ席の後部であっても、ライブの臨場感が味わえるようにする配慮だと思うが、その狙いは見事に成功している。ライブ後半部のセンター・ステージでは、1万人規模のアリーナの観客が、小さなライブハウスで盛り上がるような雰囲気となる。
浜田省吾がセンター・ステージの真下にいるファンに対して「今日は夫婦で来たの?」等と語りかければ、本当にそこが100人規模のライブハウスであるような錯覚に陥る。
ファンにとっては嬉しい限りのサービスぶりだが、このセンター・ステージを設けることで座席を潰しているので、貴重な売上を削っていることになる。
更には、ツアーの企画自体にも驚かされる。
1998年から1999年にかけての“ON THE ROAD 2001”ツア-前半部では、主に全国の小ホールを回っている。座席数が2,000にも満たないような会場を回るので、収支はカツカツであったろう。
極めつけは、奄美大島でのライブだ。離島まで機材を船便で運び、スタッフは航空機の定期便をほぼ貸切状態で移動している。その様子はDVDの「ON THE ROAD 2001」に収録されていて映像で確認できるが、傍目に見てもこれは赤字だろうという印象だ。
また、同ツアーでは野外コンサートも行ったが、そのコンセプトは「雨天順延」だった。実際に昭和記念公園では雨に祟られ、翌日に延期をしてライブを実施した。これも経費はかかっている。
このように、浜田省吾のライブは尋常ではないファンへの配慮と、採算度外視ではないかと思わせるほどの思い切りの良さを感じさせる。
それでも、ライブ・ツアーについては赤字では無いようだ。浜田省吾は初期の頃はホリプロダクションに所属していたが、ライブをレコードのセールスのためのツールとしか位置づけず、ライブの採算性を軽視する方針に納得がいかなかったようだ。
それで1983年に現在のROAD&SKYという事務所を設立し、ライブ中心に音楽活動を継続するようにしたと語っている。そのためには、当然ながらライブで利益を出さなくてはならない。
ファンには窺い知れない部分だが、ファンに満足を提供しつつ、ライブで収益を得られるように賢明な経営努力がされているはずだ。
恐らく個々のライブ会場では赤字となった所もあるかもしれない。しかし、ツアー全体では収益を上げているはずだ。
このような収益を出す仕組みは、経済活動でも共通する部分がある。例えば、会社の決算で言えば、単独の企業では赤字であっても、グループ企業全体の連結決算では黒字になるケースもあろう。
もう少し小さな事例では、小売業のある売り場で、単品では人気商品を赤字販売しても、それが集客剤の役割を果たし、売り場全体では売上が伸びる。よって粗利益はミックスされて、黒字となるというケースもある。
つまり、時として赤字になるような冒険をしても、それが顧客に大きな感動を与えれば、後からその出血分を補って余りあるほどの収益をもたらす可能性があるのだ。
ただ、ビジネスマンが注意をしなくてはいけないのは、赤字の先行投資の見極めだ。いつかは利益が出ると予測して、延々と赤字事業を継続した結果、取り返しの付かない事態に陥っては元も子も無い。
先行投資については、一定期間の評価をして、採算に合う見込みが無ければ打ち切る覚悟も必要だ。
情熱的な冒険と、冷静なそろばん勘定と、その両方を天秤にかけながら事業を続けたいものだ。
投稿者 : 02:53 AM
最近の浜田省吾のライブでは、MC(演奏休止中に演奏者がトークをする)の時に恒例行事となっている儀式がある。
それは、浜田省吾自身が「オレがライブをやっていく内は、ずっと継続していく」と宣言しているものだ。
一体、何だろうか?
答えは「年齢チェック」である。浜田省吾も、ライブに参加するファンの年齢構成が気になるらしい。
観客に向かって、「10代の人、手を上げてー」と尋ねる様子は、微笑ましくもある。
実際の統計は無く、遠山の感覚的計測では、その年齢層別は以下のとおりだ。
10代 5%
20代 10%
30代 30%
40代 35%
50代 15%
60代 5%
ファンのメイン・ボリュームは30代から40代の年齢層ということだろう。しかしながら、10代から60代まで幅広いファンを集める魅力はさすがと言うべきだ。
このような幅広い世代に対して、遠山が参加したライブでは次のように声をかけていた。
どうだろう?
浜田省吾の言葉の一つ一つは、様々な年齢層のファンのことを考えて発せられていることが理解できるのではないだろうか。
これはファンに対する実に細やかな配慮だと思う。親子ほども離れた年齢層のファンの心を、的確に捉えるのは彼のキャリアのなせる技だろう。
ちなみに、1992年時点ではファンクラブ会員の平均年齢は26.2歳だった。(1992年会報「ALL ABOUT SHOGO HAMADA」より)。
全くの余談であるが、遠山は当時23歳でこの年に結婚をした。その頃のライブ参加者は、当然ながら皆若かった。
しかし、2005年のライブに参加した時には、ファンの中心層は前述のように30~40代となっており、親子連れも増えていた。何か同窓会に参加するような感慨深さがあった。
年を重ねていくのは、浜田省吾のファンばかりではなく、実は日本の人口動態にも大きな変化が起きている。
いわゆる少子高齢化社会の予兆である。
すごく単純な話だが、ある夫婦が子供を二人産めば、長期的に人口は維持される。一人しか産まなければ、夫婦が死亡した場合は人口は一人分減ることになる。
これを数値化したのが合計特殊出生率という指標だが、これが2.05以上であれば人口は維持される。しかし、2004年6月時点で合計特殊出生率は1.29となっている。間違いなく若年層は貴重となり、人口は減少していくことは明らかだ。
一方で戦後のベビーブーム世代(いわゆる団塊の世代)は、2007年から2010年の間に60歳に達し、多量の定年退職者が発生する。この期間の退職金総額は80兆円にも達すると言われ、その使途が大きなビジネス的関心を呼んでいる。
つまり、子供や若年層は減少し、定年退職者は激増するというのが、日本経済の目前の課題になっている。家計に例えれば、働き手がいなくなり、扶養家族ばかりが増えるという状況だ。
更に製造業を中心とした中規模以上の企業は、日本国内の賃金負担に耐えられず、工場をどんどん海外に移転している。今は中国やベトナムへの転出がブームだ。
国内に残った企業は、賃金コストを抑えるためにパート・アルバイトや派遣社員の雇用を増やし、逆に正社員を削減している。2002年の総務省調査によれば、全国のパート・アルバイト比率は30.5%にも達するという。
少子高齢化で働き手が少なくなることを嘆きながら、貴重な働き手の就労の場所は減少し、必死で見つけた仕事がアルバイトというのが、これからのありがちな問題となる。
そんな時代を生き抜いていくビジネスマン世代は、働き方とか生き方の発想を変えていかなくてはいけない時にきているのではないだろうか。
極論すれば、多数の日本人の頭の中は、未だに高度経済成長期の幻想をひきずっていると言える。
それは、大企業に勤めて、大量生産・大量販売に関わって良い収入を得て、郊外に一戸建てを買うというライフプランだ。それが悪いとは言わないが、実現し難い夢になっていくのは間違いが無い。
何故なら、大量生産モデルは海外へ移転し、日本国内で生き残る産業は、極めてニッチな需要に対応するものになっていくことが予測できるからだ。
顧客のわがままとも言える細かい注文に応えることが出来る事業しか、日本国内では生き残れないだろう。それは、大企業では苦手な(効率の悪い)手法であり、若き起業家達がニッチな市場を開拓していくスピリッツに期待したい。
音楽も工業製品も、同一規格品を大量に売りさばく時代は終わったのだ。各年代や地域ごとの事情に応じて、柔軟なサービスを提供できる機動力こそが必要だ。
浜田省吾もファンの年代や地域別の特性の把握には熱心だ。その真正直な姿勢を見習いたい。
投稿者 : 02:50 AM
浜田省吾はライブ会場の規模の違いに応じて、ライブの内容や趣向を変えている。大別すると1,000人規模のホール会場、10,000人規模のスポーツ・アリーナ会場、数万人規模の野外公園会場という位置付けだ。
アリーナクラス以上では、ライブの際の視覚的工夫が重要となる。なぜなら、会場は広く後部の座席からはステージ上のミュージシャンは数cm程度の大きさにしか見えない。座席位置の違いで、ライブの臨場感が変わってしまうという不公平が生じる。
そこで、浜田省吾はアリーナ会場では大型スクリーンを導入するようにスタッフへ求めた。大型スクリーンでライブ・パフォーマンスの様子を投影すれば、会場の隅の座席であってもファンは盛り上がることができる。
野外ライブでは、このような大型スクリーンを活用するのはスタンダードな流れとなっているが、室内アリーナではまだ希少だ。その理由としては、やはり大型スクリーンのレンタル費用の問題がある。
そこは費用対効果の検討と、運営スタッフの懸命の努力があったのだろう。
浜田省吾のアリーナ会場でのこだわりはもう一つある。それは前面のメインステージの他に、センターステージを設置することだ。
センターステージとは、アリーナ席の中央部にプロレスのリングのような特設ステージを設けて、ライブの後半部はその場所で演奏を行うスタイルだ。ステージを2つも作るのだから、経費は余計に増す。
また、センターステージを作ることで中央部の座席を潰すことになるので、その分の入場料収入は減る。
メインステージでは大型スクリーンを活用して映像をフルに流し、更にセンターステージまで追加するわけだから、その経費コントロールには頭が痛かっただろう。
そのようなコスト的デメリットを抱えてまで、どうしてセンターステージにこだわるのか?
その答えは浜田省吾が求めるライブのクオリティにある。
浜田省吾はライブの醍醐味は生の演奏と観客との親密性にあると考えているようだ。ステージ上のミュージシャンと観客の一体感が味わえるのは、1,000人規模のホール会場が限界だ。
遠山も過去のON THE ROADツアーにおいて、ホール会場とアリーナ会場
の両方を体験したが、ホール会場の親近感と比べて、やはりアリーナ会場ではどこかによそよそしさを感じたものだ。
ホール会場では自分が叫んだ歓声が浜田省吾に届いていることが実感できるが、アリーナ会場ではそうはいかない。周囲の観客も同様に感じているためか、どうも行儀良く曲を聞き入る形になってしまう。
浜田省吾はライブ会場の違いによる温度差についても、何とか改善したいという気持ちがあったのだと思う。
そこで、アリーナの中央部にセンターステージを設けることで、座席の不公平感を緩和し、ライブ後半部はアリーナをホール会場の雰囲気に変えるマジックを披露したのだ。
このマジックは大好評で、メインステージでの演奏とは異なった盛り上がり方を実現した。
また、会場へのこだわりとしては、ドームやスタジアムではライブをしないというポリシーもあるようだ。
これは過去に横浜スタジアムでライブを行った際に、アリーナでも野外でもない施設で演奏をする難しさを感じ取ったからと述懐している。
つまり、浜田省吾は会場の規模や施設を層別して、それぞれの適切なサービスの仕方を作り上げているのだ。一定のサービスレベルに達しない施設では、ライブをしないという主義も徹底している。
このように場所や客層に応じたサービスの層別や絞込みは、ビジネスの場面でも必須といえよう。
よく「お客様には平等に接する」という原則論を標榜する職場があるが、この鉄則も運用を誤るとサービスの画一化と酷評されてしまう。
例えば、家具の接客でも単品のテーブルだけを探しにくるお客と、婚礼家具一式を探しにくるお客とでは、販売員に求められる商品知識や接客レベルは大きく異なるだろう。
それなのに、単品の購買客と同じ程度の応酬話法しかできなければ、大型商談を逃すことになってしまう。
商機を確実にGETするためには、顧客層の違いを理解して、それぞれの客層の心理にジャストフィットする商材の提案や提供ができなくてはならない。
少し話題は変わるが、今は何でも低価格志向で、販売店はローコストオペレーションこそが万能だという哲学が浸透しつつある。
確かに消費者にとって、良いものがよりやすく買えればありがたいことだ。
しかし、「安ければ必ず売れる」ものではないという現状認識も必要だろう。外資系のスーパーで新学期用品としてランドセルを破格の値段で売り出しても、これはほとんど売れなかったという。
アングロサクソンの合理思考だと、安価で品質は通常のランドセルを売り出せば、過剰スペックで高い日本製のランドセルを駆逐できるというシュミレーションが成立する。
だが、実際には高級ランドセルばかりが売れて、それなりのランドセルは在庫の山を築くことになった。
これは日本人の父母や祖父母の「子供には良いものを贈りたい」という心情を理解しないマーケティングの失敗といえよう。
このようにサービスというものは均質であることが良いとばかりは言えない。浜田省吾がライブ会場の規模に合わせてコンサートの内容を工夫するように、ビジネスの現場でも顧客の要望に応じたサービスレベルの差別化は必要だ。
投稿者 : 02:48 AM
現在の音楽業界では、一部の大ヒット曲が生まれる一方で、圧倒的多数のミュージシャンの曲は注目されることもなく忘れ去られている。
大ヒット曲はドラマやCMとのタイアップにより作り出されていることは、他の章で何度も述べたとおりだ。
こうした傾向を浜田省吾は次のように分析している。
「リスナーがすごい保守化してきて、それは世の中全体的に言えることだけど、ものすごいビッグ・セールスのものとそうでないものの落差が大きい。売れるものと売れないものが段階的に散らばってるんじゃなくて、二極化してるでしょう。それは世の中の流れ同様、保守化してるんだろうとは思う。
ロック・ミュージックが若かった頃は、ミュージシャンもリスナーも、とても冒険してたよね。新しいサウンドに対して貪欲だったし、新しいサウンドをミュージシャンの方はつくろうとしてたし、リスナーは探そうとしてた。でも今はもう、たぶんそういうものってないんじゃないかな。やっぱりヒットしているものを聞くと、リスナーの欲しがるものを提供してるっていうつくりですよね。歌の内容もメロディもサウンドも。それがいいか悪いかは別にして、けっきょくビジネスに徹した音楽作りになってると思う。
僕なんかは、正直言うと少し反骨気分ってのがあるから“冗談じゃないよ”と思うところがあるんだけど。」(「ROAD&SKY ファンクラブ会報57号」より)
つまりヒット曲は極めて限定され、音楽のジャンルや売れ方に多様性が無いとも言えるだろう。
このように圧倒的に強いもの、注目を浴びるものに大衆の関心が集中するのは、日本人の国民性かもしれない。
野球で言うなら、かつての読売巨人軍。政治の分野では、幾度と無く窮地に立とうとも必ず盛り返す自民党。自動車は世界のトヨタ。今も昔も圧倒的強者に対して信頼をよせて、安心感を得ると言う図式は不変だ。
これは他人の評価(世論)が気になり、多数派に所属することが大好きで、何かと集団行動をしたがるという典型的な日本人の行動パターンだ。
終身雇用の終焉や地域社会の崩壊が話題となっても、このメジャーな存在が大好きという日本人の性質はDNAにまで染込んでいるのかもしれない。
通常の市場原理がダイナミックに働くなら、安価で良質な商品が揃えば、後は適切な広告さえ行えば、その商品は多量に売れるはずである。
しかし、日本市場は一筋縄ではいかない。他人の評価を第一とするDNAが作用するため、アングロサクソンには理解できない購買行動が起きるのである。
その一例として、かつて“国民機”と呼ばれたパソコンを取り上げよう。
それは、NECが生産していたPC-9801(通称キューハチ)シリーズと呼ばれるマシンの伝説だ。
1990年代初めの頃は、日本でパソコンといえばNECのキューハチのことを指していた。そのシェアは圧倒的で、他社の追従を許さないものだった。それゆえに、キューハチは“国民機”と称号を欲しいままにしていた。
当時のパソコンのCPUは非力で、海外製のパソコンでは漢字等の日本語表示が困難だった。そこでNECは日本語処理を専門に行う漢字ROMという機能を付加し、高速な文字入力を可能とした。
その時点ではキューハチにアドバンテージがあり、パソコンに精通した人は知人にキューハチを勧めるようになり、NECのパソコンのシェアは9割を超えていた。
ブランドに依存する日本人は、キューハチ以外のパソコンには全く関心を示さなかった。(もちろん、その頃からの熱烈なMacファンも存在したが少数派だった。)
しかし、1995年にWindows95が登場する頃になると状況は激変した。
この時期にはパソコンのCPUは飛躍的な性能向上を遂げ、漢字ROMに頼らなくてもWindowsで日本語処理は実用レベルに達するようになった。つまり、漢字ROMを搭載していても、その機能は使わない盲腸のような存在となってしまった。
すると、国際規格(AT互換機)は海外の安価な部品が調達可能となるため、価格面での優位性が明確となった。
実際に欧米ではAT互換機のWindowsマシンが飛ぶように売れ、キューハチは割高だという認識が浸透し始めた。
性能でも価格でも優位性を示せなくなったキューハチは、すぐに売れなくなると思われた。
だが、実際にはWindows95の登場以後も、順調にキューハチは売れ続けた。もちろんNECの価格対応や広告戦略が見事だったこともあるが、これは日本市場独特の現象ともいえよう。(その数年後、NECは緩やかに方針転換を行い、キューハチからAT互換機に切り替えることで見事な生き残りを果たしている。)
そこには、日本人が集団として盲信したブランドは、少々時代遅れになっても、その神通力を失わないという特徴が読取れる。
それほど日本市場は世論やオーソリティーの言動に盲従する傾向がある。
よって、市場に圧倒的勝者が存在する場合は、特に日本市場では同一分野での競合は勝ち目が無い。そのような状況ではサービスの差別化を図り、違う土俵で勝負をかけるべきであろう。その差別化への動機は、浜田省吾の言う“反骨心”であっても構わない。
それが購買行動の二極化に適応していく術だと言えよう。
投稿者 : 02:46 AM
浜田省吾をテレビで見かける機会は、本当に少ない。歌番組には出演しないし、ドラマやCMのタイアップで曲が流れることも無い。
しかし、1998年から2001年にかけて敢行したON THE ROAD 2001ツアーでは、全国127ヶ所で196の公演を行い60万人を動員した。2000年に発売したベストアルバム「The
History of Shogo Hamada"Since 1975"」は150万枚を売上げ、最近のアルバムもコンスタントに20~30万枚のセールスを記録している。
つまり、売れないからテレビで見かけないのではなく、テレビやラジオといったマス・メディアを、セールスの手段として活用していないのだ。
ミリオン・セールスを記録するようなヒット曲は、ほとんどの場合がドラマやCMのタイアップ曲というのが日本の音楽界の現状だ。こうしたタイアップやテレビの活用無しにアルバムを売ってヒット・チャート上位に入ったり、ライブで1万人収容のアリーナを満杯にするのは驚異的だ。
ここで単純な疑問が生じる。
歌番組やCM等で全く耳にしない曲なのに、どうして売れるのか。更にはライブのチケットは当然のごとく発売即日にSOLD OUTとなるわけだが、これも不思議だ。
一体、浜田省吾のアルバムを買ったり、ライブに参加する人は、どこで浜田省吾の存在を知ったのだろうか?
ライブ会場に行くと、そこに集うファンの年齢層は30代から40代が中心だが、10代や20代も見かける。(もちろん、50代以上のファンもいる。)
10代や20代の年齢層は、比較的最近に浜田省吾を知ったはずだ。しかも、テレビ以外の接点から。
恐らく、親や年の離れた兄弟が浜田省吾ファンであったり、会社の忘年会で上司がカラオケで歌う「J.BOY」や「MONEY」を聞いて興味を持ったとか、そういうきっかけでアルバムを聴くようになったのではないだろうか。
つまり、もの凄く身近な人から影響を受けて浜田省吾の曲を知り、競争率の高いチケットを取るために何度も電話をする苦労を経て、ライブに辿りついたわけだ。
このように親兄弟や友人、恋人からお気に入りの音楽を勧められ、それがお気に入りとなって、気が付けばロングセラーのヒット曲となっていくという様子は、まさに口コミの力であり、最も自然な音楽の波及の姿ではないだろうか。
浜田省吾のファンは、親しい人にアルバムを聴かせたり、ライブの感動を話したりということをマメにしているように思う。
そこには感動を人に伝えたいという単純な動機の他に、テレビでは絶対に知りえない浜田省吾の音楽の良さを、自分が伝播しなくてはという使命感もあるように思う。
「俺が浜省の歌を広めなければ、誰がやるんだ。」
このくらいの心意気のファンも多いだろう。ファンにそこまで支持されるようになれば、口コミ・マーケティングは大成功と言える。
まるでマッキントッシュの熱烈なユーザーが、Macの良さを延々と語りだしてエバンジェリスト(福音伝道者)と称されるように。
遠山の場合は、浜田省吾教のエバンジェリストでありたいと思っているわけだが。
ON THE ROAD 2001ツアーの頃からは、インターネットも普及し、ライブの様子をネット上に逐一報告しあうファンが増えた。
最近では、ブログやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のmixi(※注1)で、ライブの感想を公開するファンが急増している。
余談となるが、遠山がこの本を書くきっかけとなったのが、mixiに公開したライブ参加の感想だった。その日記を見てくれた企画者から、ビジネスや経済学的視点から浜田省吾について書いてみないかとお誘いを頂いたのだ。
(※注1)
ブログとは、簡単な手順で日記形式のホームページを公開するツールで、この普及によってホームページを公開する個人が急増している。
ソーシャル・ネットワーキング・サービスとは、ブログを会員制にしたようなツールで、同好の士によるコミュニティが盛り上がっている。
このように、ファンが勝手に新しいファンを呼んで来るようになれば、放っておいても商品は売れる。この段階に至れば、派手なプロモーションや費用のかかる宣伝・広告は控え目にしても良いわけだ。
通常、消費者が購買行動に至るまでには、様々な心理的障壁が存在する。例えば、ふと耳にした曲を良いと思っても、そのCDを即購入するわけではない。CDショップまで出掛けるのが億劫だったり、ネット予約すら面倒と感じるものである。
ましてや、ライブとなれば繋がらない電話を何回もかけて、予定を調整して会場まで出掛けなくてはならない。
そんなハードルを乗り越えても、「欲しい」と思わせる何かがなければ、結局販売機会を喪失してしまうのだ。
しかし、親しい知人からの口コミという後押しがあった場合、大抵の人は「それなら買ってみようか。アイツが言うなら間違い無いだろうし」と思うわけだ。
この場合は購買行動に結びつきやすい。
一般のビジネスであっても、いろいろと宣伝活動はしているのに、あと一歩のところで購買(契約)まで至らないという現象に悩むことは多いと思う。
売り手側が必死に宣伝すればするほど、皮肉なことにお客は離れていくこともある。これはお客側から見れば、見ず知らずの営業マンが強引に商品を押し付けようとしているという印象を抱いてしまうからだ。
そんな時には、商品やサービスの品質の良さを追求し、既存顧客がリピーターとなり、更には新しい顧客を連れてきてくれるという循環を作り出す努力をすべきだろう。
そのためには、サービスレベルを維持し続け、口コミの評判を上げるに尽きる。一朝一夕に信用は醸成されるものでは無いが、これが出来れば事業は安泰となるはずだ。
投稿者 : 02:44 AM
ライブの帝王である浜田省吾にとっても、野外ライブは特別なイベントだ。通常のライブ場合は「みんなの街へ行く」という言い方をするが、野外の場合は「遊びに来て欲しい」と語る。
それだけ野外ライブにはファンを接待するような気分が働くらしい。
そんな特別な野外ライブだが、近年では1999年夏に開催している。その時も8年ぶりとなる野外ライブであり、とにかく貴重な機会だった。
この1999年の野外ライブを企画するにあたり、浜田省吾はライブ会場に関していくつかの要望を挙げたという。
それは、まず公園が全面芝生であること。そして、面積のゆとりがあること。(5万人が収容可能な会場に対して、チケットは2~3万枚しか発行しなかった。)
更にはトイレ・売店・駐車場が充分に用意できること。
これらの条件を満たす会場は意外と見つからず、スタッフは懸命に全国の公園をリサーチしたそうだ。
そして、最終的には北海道のキロロリゾート、広島の備北丘陵公園、東京の昭和記念公園が選ばれた。
全面芝や面積的なゆとりについては、恋人や家族と一緒に来て、ゆったりと座ったり寝転がったりできるようにしたいとの思いだったそうだ。
トイレについては、とにかく数を充実して、トイレ待ちの間に演奏が数曲終わってしまうような事態にならないような配慮だ。売店はアルコールを買ったり、子供が退屈しないように。駐車場に関しては、家族連れが余裕を持って行動できるようにとの狙いだ。
これらは屋外でイベントをする際には常識だと思えるが、このように行き届いたライブは少ないのが実情だ。
何よりも、野外ライブは経費も莫大となるため、会場のキャパシティの限界までチケットを発行するのが常識化している。そのため、会場はスシ詰めとなり、トイレで30分待ちとなったり、迷子や行方不明の遭難者が溢れることも珍しくない。
にも関わらず、ファンがゆとりをもって参加できる条件整備を第一に考えるのはサスガだ。
ミュージシャン自身がこのような細かい配慮をするのは、本当に素晴らしい。だが、浜田省吾のこだわりは、もっとスゴイところにあった。
それは野外ライブについては「雨天順延」というコンセプトにしたことだ。
野外イベントで雨天順延というのは、ある意味当たり前のことかもしれない。しかし、順延というからには予備日を用意する必要がある。野外ライブには大型スクリーンや照明、動力装置そして大勢のスタッフの人件費など、とんでもないコストがかかる。
それを予備日の分まで確保すると、単純計算で経費は2倍となってしまう。
恐らく、最初に「雨天順延」というコンセプトを聞いたステージ責任者は、顔面蒼白になったに違いない。ひょっとしたら、卒倒してしまったかもしれない。とにかく、運営者にとってはそのくらい過酷な条件なのだ。
とにかくビジネスに徹して利益を追求するなら、会場はスシ詰めにして「雨天決行」にするべきなのだ。経費を1日分に抑えて、チケットを多量に売りさばけば、儲かって仕方が無いはずだ。
そうした野外ライブのあり方について、浜田省吾は次のように語っている。
「 音楽ビジネスという面から考えれば、雨天でもコンサートは決行すべきなんでしょうね。でも、それは、目先のビジネスで、その場で損をしないだけなんですよ。野外コンサートについての業界の常識に対して、アンチ・テーゼを示したかったんです。そして、口で言うだけでなく、実際にそれを実行し、こうしたやりかたでも成功を収めることができるということを証明したかった。ぼくは、これは小さな種にすぎないかもしれないけれど、必ず実を結ぶとおもっています。」(アサヒグラフ 1999年9月24日号より)
つまり、雨天決行のような目先のビジネスでは、観客に酷な思いをさせることになってしまう。土砂降りの中で風邪をこじらせて肺炎にでもなれば、そのファンにとってはマイナスの意味で伝説のライブになってしまうだろう。
すると、その観客は二度と野外ライブには行こうとは思わなくなる。そのようなファン無視のライブはできないというのが浜田省吾の配慮なわけだ。
それでも、ライブで赤字を出すわけにはいかない。このようなファンに優しい野外ライブを行いつつも利益は出す。その実績によって、他のミュージシャンもファン優先の野外ライブのモデル例として考えるようになる。
浜田省吾は、そこまでの大局的視点で行動したそうだ。そこにはライブの先駆者としての誇りと自覚が垣間見える。
世の中には経済効率ばかり追求して、顧客の立場を見失う事例はいろいろとある。例えば、2005年のJR福知山線の列車事故は、過密ダイヤで運転士を追い込むあまり起きてしまった可能性が取り沙汰されている。
他社との競争や効率に焦るあまり、最も大切な安全性が損なわれてしまった。
目先の利益や効率ばかり追っていると、人は近眼的行動しか取れなくなっていく。その結果、事故でも起こして顧客からソッポを向かれては元も子もない。
自分が関わる事業にとって、本質的な顧客サービスとは何か。その問いかけを忘れてはいけないだろう。
投稿者 : 02:38 AM
現在の日本経済市場は成熟して、なかなか新規参入のチャンスは無いように思える。ごく一部のIT関連企業が急成長をしているが、ライブドアの偽計取引や粉飾決算事件、光通信株の大暴落をなどの現象を見るにつけ、どことなく胡散臭く頼り気がない。
マスコミは高感度の高い女優を使って大企業のCMを垂れ流し、消費者はそうして刷り込まれたブランド・イメージを信奉して、ヒット商品に群がる。
結果として、大企業が提供するメガ・ヒット商品は誕生するが、新規起業者がそのようなサクセス・ストーリーにあやかる可能性はゼロに等しい。
音楽業界でもテレビを中心としたマスメディアの影響力は大きく、そこに利権が発生する。とにかくテレビに関わる人々の意向に従わないと、ミュージシャンが楽曲をリスナーに知ってもらうことができないのだ。
そんな現在の音楽業界事情を、浜田省吾は次のように語っている。
「 シングル(CD)を売るというシステムがどういうものであるかっていうのは-ユーザーの人は知る必要もないことなのかもしれないけど、いかに露出していくかと。そして、その中で最も力を持ってるものはダントツにテレビであると。テレビの中で最もたくさん露出するものはドラマの主題歌であったりCMであったりするわけですけど、当然そこからたくさんのヒット曲が出てそれがたくさんのお金を生んでるがために、ガッチリとしたシステムがもうでき上がってるんですよね。具体的にじゃあこの楽曲の何%、この楽曲が入ってるアルバムの何曲分の著作権をどういうふうに分配しろ、しなければ使わない-もうそういうところなんですよ。だから、ものすごくいい作品だからシングル盤として世の中に露出して、それがメガヒットになっていくというような時代ではもうないんですよね。」(BRIDGE 2001年10月号より)
何という世知辛さだろうか。ファンはCMやドラマでも、もっと浜田省吾の曲を聴きたいと願っても、それには多額の宣伝費用をテレビ関連の各所に上納しなくてはならず、巨大プロダクションに所属しているわけでもない浜田省吾にとっては、その負担を背負えないという状況なのだ。
世の中はカネと利権でよどんでいると嘆きたくもなるではないか。
これはテレビという既存マスコミを通した場合の話だ。そのテレビが創り出すメガ・ヒットには上位集中という特徴がある。それは売れる曲は爆発的に売れるのだが、そんなメガ・ヒット曲数は年間ではそれほど多くない。
一方、ほどほどに売れる曲というのは減少して、圧倒的多数の売れない曲の骸が荒野に転がっている惨状だ。
何か少し前の戦力集中を図った読売巨人軍とプロ野球の関係のようではないか。
実はこのような圧倒的な上位層とうだつの上がらない下位層に二極分化するのは珍しい現象ではない。
ビジネスの現場でQCサークル活動なんかに取り組まれる方ならご存知だろうが、諸々の売上をパレート図とかABC-Z分析という手法で解析すると、成熟した市場は少数の勝ち組とその他大勢の負け組みに分化してしまう。
飲食店で物を売るにも、人気メニューは集中していて、売れない商品は全く売れないものだ。
だからと言って、売れない商品が粗悪品かといえば、そんなことは無い。単に陽の目を見ないだけだ。
そんな売れない組のやるせなさに、かすかな光を与えるのがインターネットだ。インターネットの可能性を雄弁に示す事例として、アマゾンの書籍販売がある。
書籍も音楽業界と同様で、ベストセラーとその他大勢という売上構成が出来上がっている。そのため、取次を経由した一般書店では、ベストセラー本しか置かれないという現象が起きている。
マイナーな書籍であれば、ほとんど店頭で見かけることはなく、注文しなければ入手はできない。当然ながら、そんな本は売れない。
しかし、アマゾンはインターネット上で無店舗販売をしているため、在庫リスクを考える必要がない。そのため、マイナーな本でも取扱をする。
すると消費者は、店頭では見かけない本を検索で見つける喜びを知り、これを積極的に活用するようになった。結果として、アマゾンでは売上の三分の一を非ベストセラーで占めるという快挙を成し遂げた。
ここに成熟市場でも挑戦者が切り込んでいける道筋が示されたと言えよう。
浜田省吾も意識しているかどうかは不明だが、わりとインターネットの活用には積極的だ。ROAD&SKYやSONYミュージックの公式ホームページでは、ビデオクリップ視聴やファンに向けたメッセージを提供している。
携帯電話向けのコンテンツとして、着うた配信にも積極的だ。更にはsuicaによる日本初の電子ポスター予約や、ConnectedDを活用したCD購入者に対するファン・サービスも実施している。
2005年には新曲「I AM A FARTHER」の発売にちなんでYAHOOとタイアップしてブログを公開したりもした。
インターネットは現段階では既存マスコミの影響力が小さく、検索エンジンとの親和性が良ければ、不特定多数のエンドユーザーに直接働きかけることが可能となる。
テレビを利用しないで、そんな芸当ができるのは、インターネットくらいだろう。これを活用しない手は無い。
そんなわけで、テレビに振り向いて貰えない起業家達は、こぞってインターネットを利用する。僕自身もそんな一人だ。(浜田省吾はテレビに振り向いて貰えないのではなく、自らの意思でテレビ出演を拒否しているのだから、事情はことなることはお断りしておく。)
成熟市場の閉塞感を切り崩すツールとしてインターネットを活用すれば、まだまだ面白いことはできそうだ。
投稿者 : 02:37 AM
かつて浜田省吾は日本の音楽業界では非主流の存在だった。いわゆるニューミュージックというジャンルの音楽は、大量のCMやプロモーションを前提として、広告や宣伝活動の物量作戦によってセールスをするのが常識化していると言えよう。
ドラマ・アニメ・映画・CMとタイアップして作り込みをされた曲が、ヒット曲となるのが一般的現象となっている。
また、こうしたタイアップにはテレビというメディアの存在が不可分であり、それだけにミュージシャンは歌番組への出演には積極的となる。
つまり、テレビ抜きには日本の音楽セールスは始まらないというわけだ。
そのテレビに出ないということは、従来の音楽マーケティング活動では自殺行為に等しいとも言えよう。
無論、浜田省吾も初期の頃はテレビやラジオというメディアへの出演や、テレビCMとのタイアップをして、(当時は)EP・LPレコードの販売促進活動にチャレンジをしていた。
遠山はリアルタイムで観た記憶は無いが、「ヤング オー オー」に出演したり、日清のカップラーメンのCMに「風を感じて」が使用されたらしい。
また、浜田省吾は「デビューから5枚目のアルバムまでは廃盤にして欲しい」と冗談で語っている。その主な理由として、初期の頃は音楽の方向性が定まらず、周囲のアドバイスに従って“売るための”音楽であるポップス系を作っていたと述べている。混迷が深まって他人に作詞をしてもらったりもした。
しかし、思うように売れずに、「それなら、(本心に従って)もっとハード・ロックをやりたい」と思うようになったという。
その時点で大きな思い切りがあったのだろう。6枚目のアルバム「Home Bound」(1980年発売)では「終わりなき疾走」を始めとするロック基調の曲が増え、この年に初めて年間のライブ数が100を超えた。
現在の浜田省吾のモデル・パターンは、この時期に形成されたと言ってよいだろう。そして、この戦略は当たり浜田省吾は“ロック・スター”“ライブの帝王”の称号を得るようになっていった。
ちょと見方を変えれば、テレビではポップス系の曲がもてはやされていて、音楽業界の主戦場はポップスの過熱で消耗戦に突入していたとも分析ができる。
その主戦場を回避し、ハード・ロックをしかもライブ中心でPRするという戦略に切り替えたとも言えないだろうか。
つまり、経済的にも精神的にも消耗・疲弊が強いられるテレビ=ポップスを敬遠し、日本では未開拓だったライブ=ロックという分野に特化していったということだ。
このような競合を避け、専門分野に特化(セグメント化)していく手法を、経済理論では“ランチェスター戦略”という。
ランチェスター戦略とは、第一次世界大戦時にイギリスのエンジニアであったF.W.ランチャスターが考案した戦争の法則で、第二次世界大戦後は企業の経済戦略理論として応用され現在に至っている。
ランチェスター理論の要点について、挑戦者側から見た場合は以下の通りである。
「大局での競合(消耗戦)の回避」
「差別化(セグメント化)した局所で戦う」
「局所に経営資源を一点集中し圧倒的勝利をする(カテゴリー・キラー)」
大局での競合を回避するというのは、資本力や販売力で劣る立場にある挑戦者は、既にディファクト・スタンダート(事実上の標準)を確立している勝者が存在する市場には参入しないということだ。
トヨタやGMと真っ向勝負をして、大衆車の製造メーカーを起業すると言う人はいないだろう。もし、いたとしても銀行は1円も融資してくれまい。
しかし、大衆車ではなくニッチな分野の極めて趣味的な車を作るなら、ごく僅かな希望はあるかもしれない。
差別化した局所というのは、巨大な販売網を持った会社でも、苦手な分野は存在するものだ。その大手が扱わない市場に狙いをつけることだ。
イトーヨーカドーやイオンの隣地で物販の店舗を構えるのは厳しいが、これら巨大スーパーでは売り場面積の少ない商品に目をつけ、そのジャンルに特化した店作りをすれば勝算は生まれる。
例えば、隣接する巨大スーパーが100坪の衣料品の売り場面積を有していたなら、50坪の紳士服専門店を作る。店舗面積が20坪しかなければ、更に「大きいサイズ」に特化する。このような工夫が差別化といえよう。
局所に経営資源を一点集中とは、差別化した事業を片手間でやっていてはいけないということだ。片手間の仕事では、消費者の要求するクオリティーは満たせない。
差別化すると決めた事業(市場)に対して、経営資源や人材を全力投球することだ。そうしないと、新興市場に目をつけた大手が後から参入してきた時に太刀打ちできなくなってしまう。
かつて世界のパソコンメーカーといえば、それはIBMのことを指した。しかし、汎用コンピュータ(パソコン)に特化したコンパックの台頭を許し、その後は通販やインターネット直売に特化したDELLが販売台数を凌駕している。
そして、当のIBMはパソコン事業では利益を出せなくなり、その事業を中国企業に売却した。これも、DELLが販売店を通さない通販という事業に全力投球したからだ。DELLが既存販売網の圧力に屈してダイレクト販売を止めていたら、現在のシェアは無かっただろう。
浜田省吾もロックとライブという差別化を図り、その分野での先駆者となった。そして、商業的にも成功を収め、既存メディアからも一目置かれる存在=カリスマに昇華したといえよう。
新しく事業を始める場合は、ほとんど誰もが挑戦者という立場に置かれる。その際には、既存市場との差別化や一点集中という戦略が有効となるのだ。
投稿者 : 02:35 AM
モノ余りの時代では、どんな事業でもマーケティングが重要となる。物資の乏しい地域であれば、少々の粗悪品であっても、安価に大量供給できれば飛ぶように売れる。
しかし、成熟した経済環境下では、そんな商品やサービスは受け入れられない。
いかに現代のマーケティングが難しいかという好例に、1996年に大ブームとなった「たまごっち」がある。携帯玩具の先駆けとも言える商品で、子供だけでなくOLも夢中になってバーチャルなヒヨコを無機質な液晶の中で飼育していた。
これが発売から大ヒットなって、店頭では山のようなバック・オーダーを抱えた。製造元のバンダイも、そこまで売れることを予測していなかった。
そこで慌てて「たまごっち」の大増産をしたのだが、潤沢に商品が店頭に並ぶ頃にはブームは去ってしまった。バンダイは不良在庫を抱えることになってしまったのだ。
つまり、二重にマーケティングの判断を誤ったことになる。当時の担当者には同情するばかりである。(2005年から小学生にたまごっちのリバイバル・ブームが起きている事も補足しておこう。)
このように、マーケティングの予測や判断は、非常にシビアで難しいものと言えよう。そこには、いつも様々な資料やデータを検討した上でも、迷いや不安がつきまとう。
その点、浜田省吾は最大のファン・サービスはライブであると位置づけ、過去この方針は決してブレたことがない。
なにしろライブ・ツアーを敢行するには、バンドや舞台装置等の裏方を引き連れて全国を移動する必要があるのだ。大勢のスタッフを動員するからには、当然ながら経費も膨大。そのためミュージシャンにとって、ライブの経費は負担であり、利益性は決して良いとは言えたもんじゃない。
というか、単に利益を追求するなら、ライブは行わず、CDのみを多量にセールスすることを考えた方が効率はいい。言うまでもないが、ライブは極力行わず、テレビ出演でCDの宣伝を繰り返し、CDセールスを重視するミュージシャンも少なくない。
あえて名前は出さないが、そうやって多くのミュージャンは人気を獲得し、ファン層を開拓し、安定したところで、ツアーに出る。
ところが、浜田省吾はそんな音楽業界では異色とも思えるスタイルを貫いている。
ライブ優先だ。
しかもテレビ出演やコマーシャルやドラマとのタイアップはほとんど行わず、プロモーションもむしろ控え目。
売る気がないと思えるほどである。
にもかかわらず、採算性が低いライブを精力的に展開し、チケットは即日完売。しかもファンの間では、そのライブは年々進化していると評価も高い。つまり、驚くことにソロデビューから30年を経過しても、更にライブの質は向上しているのだ。
残念ながら、これはライブ経験者にしか分からないが、そのブレない姿勢は圧倒的なメッセージになっている。
結果として、この質の高いライブを提供し続けることで、CDアルバムも安定的にセールスを計上。つまり、浜田省吾はファンが喜ぶことを第一に考えて行動し、その上でプロモーターとして、採算性も両立させる手腕を発揮しているのである。
ちょっと考えれば、テレビ出演やコマーシャルやドラマとのタイアップも、重要なファン・サービスであり、それを期待する需要も大きいのではないか。そういう疑問もあると思う。
これに関して、浜田省吾は「青空のゆくえ」(ロッキングオン出版・渋谷陽一著)で次のように言っている。
「これは凄くいい音楽か?っていうよりも、これはブレイクするか?これは凄く売れるか?っていうところで音楽の話をしてる。(中略)例えば音楽がテレビの付属品のようになってしまったこととか、そこからしかメガヒットが生まれなくなってしまったこととか、もちろんそのビジネスの仕方ね、タイアップの仕方とか(中略)あまり僕には健全に映らないんですよね。」
これには音楽に対する浜田省吾のこだわりが垣間見える。
つまり、音楽の提供が自らの職業的使命だと認識し、何の制約も受けずに楽曲を作りたい。そのためには、制限の多いテレビとのタイアップは避け、ダイレクトにファンに楽曲の良さを感じて貰いたいと考えているのだろう。
だから、浜田省吾の歌を聴く事を楽しみにしているファンの目前で、力の限りアピールできるライブを重視しているように思う。
結果として、この姿勢はファンに支持され、熱烈なライブへのリピーターを生み出している。
マーケティングとは、とても繊細で予測が難しいものであることは前述した。多くのビジネスマンは、それを知っているからこそ、時としてマーケットに迎合したりする。
それは、顧客像を過剰に意識して、生産者のポリシーを曲げたりするという弊害となることもあるだろう。
生産側の意向と顧客需要のすり合わせが、マーケティング活動とも言えるが、企画者が自己のポリシーを押し通す勇気も必要と言えよう。
投稿者 : 02:33 AM
浜田省吾がソロデビューをした1976年の時点では、日本ではロックやR&Bというジャンルの音楽は産声をあげたばかりだった。そのため、この分野でのセールス手法は確立されておらず、何もかもが手探りだった。
前例やマニュアルの類が無いというのは、ホントに辛いものだ。突然にジャングルへ放り出され、「今日からここで生きてゆけ」と宣告されるに等しい。
浜田省吾自身も、好きな音楽をやっていける嬉しさはあっただろうが、不安の方が大きかったかもしれない。その心境を次のように語っている。
「 我々の時代は、ロックシーンというものがまだなかったですから、10年後を全く想像できなかったんですよ。自分はどうなっているんだか分からない。でも、とりあえず好きなことだし、これで食えているからハッピーだねという気持ちと、世の中はオイルショックで不況で就職口もあまりないし、これで成功しなかったらどうしようみたいなのと、両方あったと思いますね。ただ、何もなかったからこそ、自分で選んだ道だからという納得もありましたね。俺が選んだ道なんだという。そこは今の子たち(現在の若手ミュージシャン)と(置かれている環境が)違うかもしれない。今はシステムがしっかりと出来ていて、これとこれを組み合わせるとどうなるかとか、タイアップはしっかりとって、プロモーションはこの番組に出て、みたいなことをすでにアマチュアのミュージシャンも知っていますよね。それが良いことか悪いことかは分からないですね。」(J-POP MAGAZINE 2005年9月号より)
やはり、浜田省吾といえども、成功しなかったらどうやって食っていこうかという不安を抱いていたようだ。
1980年代以降は音楽市場が膨れ上がり、ミリオンセラーも狙えるビック・ビジネスとなった。しかし、それ以前はロックで生計が成り立つものかどうかというレベルの疑問もあったのだろう。
そんな状況の中で、現在では考えられないことだが、浜田省吾もCMソングを作ったりテレビの歌番組に出演したりと、必死のプロモーションをしていたわけだ。
しかし、ポップミュージックのセオリー通りにプロモーションをしても、結果として売れなかった。そこで、ある種の開き直りもあって、自分が大好きなバリバリのロックを作り、それをひたすらライブで披露するという形で活路を見出すことになっていった。
そこから過去と現在の対比として、フロンティア精神とシステムの確立という特徴が分析できるだろう。
過去においては、ほとんどの場合で前例はなく、何もかも自分達で切り開いていかなくてはならなかった。いわゆる開拓者精神(フロンティア・スピリッツ)だ。
とにかくルールと呼べるものすら未整備で、全てが自己責任だ。失敗することの方が多いだろう。
そのようなリスクは大きいが、逆に自由な気ままさもあったはずだ。何もかもが自分の裁量次第とも言える。そういう面では、失敗した場合も納得はできた。
一方、現在は何もかもが整備されて、いろいろな販売手法は確立している。目標やチェックポイントは明確で、マニュアル通りに行動をすれば大きく間違うことは無い。
マーケティング活動においても、事前に売上の予測はできてしまう。コンビニの弁当売上予測等は神業かと思ってしまう。とにかく作業に無駄をなくし、効率の向上が何よりも美徳とされる。このように販売システムは確立された。
だが、この効率を極限まで追求すると、何もかもがマニュアル化された画一的なサービスしか提供されなくなる。マンネリってやつだ。そこには個人の思い入れや新しいアイディアが排除されてしまい、不満を抱えて仕事を続けるケースも生じる。
浜田省吾も名曲J.BOYで「打ち砕け日常(マンネリ)ってやつを」と絶叫しているのだが・・・。
また、ある商品のマーケティング手法が確立されてくると、昔は全工程を少人数で行っていた作業が分業化する。
すると、細分化された作業を任された人は、その分野のスペシャリストとなる。このスペシャリストが自分の作業範囲内でしか物事を考えなくなると、そこには深刻な組織的弊害が生まれる。いわゆるセクショナリズム、お役所仕事だ。
いくら販売システムが優れていようとも、その内部でお役所仕事が蔓延すると、そのシステムは悪性の癌に侵されたような状態となってしまう。
このようなマンネリを打ち砕くため、浜田省吾はライブ・ツアーにこだわる。
「 シンガー&ソングライターというのは、自分が作った歌を自ら歌うわけで・・・。ステージで歌わなければその歌はオールディーズになって行くしかないんですよね。自分の作った歌をコンサートで、自分で歌うことで今の歌になるんですよ。そして、聴いてくれた人がそれを良い歌だと思ってくれれば、それは生き残った歌であり、生き残って行く歌なんですよね。」(J-POP MAGAZINE 2005年9月号より)
つまり、ソングライター(作り手)としても、シンガー(表現者)としても、現役であることにこだわっていると言えよう。単に曲作りをしていくだけではなく、それをエンドユーザーであるファンの前で演奏しようと務めている。
そこには分業化が進んだ音楽業界の中にあっても、できるだけファンの顔を見ようとする真摯な姿勢が感じ取れないだろうか。
翻って自分の仕事を考えたとき、調査・開発から製造を経て販売に至るまで、全工程を把握してエンドユーザーの要望を知ろうとしているかが問われる。
分業された作業だけに埋没していると、仕事への意欲も減退するものだ。
既に確立されたシステムに乗っかっていたとしても、エンドユーザーの喜ぶ顔をイメージし、全工程を把握する気概は持つべきだろう。
投稿者 : 02:32 AM
浜田省吾のライブでは、休憩時間にもサービス心が旺盛だ。ライブの中間で10分程度の休憩があるのだが、この時間に観客が退屈しないようにステージ上のスクリーンにはオリジナル映像を流してくれる。
その映像はショートストーリーになっていて、浜田省吾が主演するというレアものだ。これを見逃すのはもったいないと思い、ついついトイレに行きそびれたファンも多いだろう。
ON THE ROAD 2001ツアーでは、「ミッドナイト・キャブ」と「マリア」というタイトルのショートストーリーを披露した。
「ミッドナイト・キャブ」は浜田省吾が扮するニューヨークのタクシー運転手に、様々な乗客がその人生模様を語りかける。無邪気な不良少年たちの武勇伝、娼婦風の女性が恋人に客の暴行を嘆く、東洋人(日本人?)が株の暴落に断末魔の悲鳴をあげる、寡黙な老紳士が大切な人の死を語る。このように乗客の人生観を、寡黙な運転手の浜田省吾がただ頷いて聞いている場面が印象的だった。
「マリア」は大農場でメキシコ人労働者が農作業をする様子が映されていたが、その中に浜田省吾が混ざって農夫役をしているのを見つけると、会場から笑いが起こった。やはり農作業中でもサングラスは外さないのだ。
そんな農作業後の歓談の際に、浜田農夫と地元の美少女のマリアが世界観や職業観を型ってしみじみと聞かせる。
この「ミッドナイト・キャブ」も「マリア」もテーマは「働く」ということだそうだ。そういえば浜田省吾の曲には「ビジネス」や「仕事」について触れる歌詞が多い。ロックにしろR&Bにしろ、流行歌のテーマはほとんどが「恋愛」というのが主流だが、そういう面でも異色といえるだろう。
もちろん、浜田省吾もラブソングはたくさん作っているし、その評価も高い。でも、人間は四六時中恋愛だけを考えて生きているわけではない。働き盛りのビジネスマンが音楽CDを買わない現象というのは、案外恋愛漬けの流行歌に食傷気味になっている事情もあるのではないか。もう学生ではないんだし、愛だ恋だと浮かれている気分じゃないっていうのも本音だろう。
遠山自身の感性が人と違っているところがあるのかもしれないが、はるか昔の高校生の頃からラブソングしか入っていないアルバムに違和感を持っていた。いいラブソングは確かに好きだが、歌の全てが恋愛一色だと「あんたの頭の中は恋愛しかないのか?」と毒づいていたものだ。何か無理に恋愛を強制する“恋愛押し売りソング”が氾濫しているようで、流行歌を聴きたいとは思えなくなっていった。
そんな偏屈な少年時代を過ごしていたが、大学に入学した年に浜田省吾のアルバム「J.BOY」を聴いて衝撃が走った。
何とアルバムの1曲目から「A NEWSTYLE WAR」なんていう反戦歌が入っている。「J.BOY」では過労死が社会問題になる中で、仕事におぼれるビジネスマンの心境を吐露している。その他にも父親の人生観やアルバイトで苦学する歌など、生活に密着して共感を得る曲が多かった。
ラブソングも「19のままさ」や「遠くへ」などは、将来の不安を抱えて吹けば飛ぶような存在の自分の境遇に一致した。
その時以来、浜田省吾が「通りのウィンドーに飾ってあったギターを見たとき」並みの稲妻が体を駆け抜けて、彼がリリースする曲は必ずチェックするようになった。
そんな浜田省吾が「仕事」について語った記事がある。
「 仕事っていうのは、ただ、お金をもらって生活するためだけのものだったら、どこか寂しい気がするんですね。人は社会的な生き物ですから、仕事をすることによって、社会の中のつながりとか誰か人のためになっているとか、そういう存在価値みたいなものを見出せたらすごく幸せだと思うんです。」(日経エンタテイメント 1999年12月号より)
納得である。現代社会は物の生産や流通が高度化して、仕事の内容が分業化・細分化されている。
例えば、工場の中で精密回路のハンダ付けの作業を任された場合、それ以外の仕事が見えないわけだから、自分のやっていることが社会のどこで役に立っているか認識できない。
そこで「お客様のために貢献しろ」とか「仕事に誇りを持て」と言われても、それは虚しいスローガンとして耳の左から右へ抜けていくだけだろう。
逆に消費の場面でも同様だ。今晩の夕食の刺身について、その生産や流通過程に携わる人々の苦労にどれだけ意識はいくのだろうか。
魚が切り身になるまでは、養殖業者の手で何ヶ月も世話をされた魚が水揚げされ、鮮度が落ちないうちにトラックで運ばれ、加工センターで切り身にされる。その後、店頭に並ぶわけだ。その間では熾烈な価格交渉があって、そこでストレスを抱える人もいるはずだ。
笑い話で、小学生に魚の絵を描かせると、切り身が泳いでいる絵を描いたという話がある。それほどまでに現代人は、かつては自らの手で行っていた工程の一部しか見ることができず近眼になっている。
そんな断片的な日常を繰り返していると、自分が社会の中でどのような役割を担っているかを感じ取るのが難しくなる。
浜田省吾も語るように、社会とのつながりを認識しないことには、人間は孤独や疎外感から開放されることはない。面倒に思える作業になるかもしれないが、自分のやっている仕事が何の役に立っているのかを調べ、その全工程や全体像を把握する努力を行い、それを家族と語って確認することが幸せにつながるのかもしれない。
投稿者 : 02:30 AM
ビジネスの現場では、何かと二者択一とか三者択一の選択を迫られる場面が多い。そんなときに、デジタル的にスパッと即決できることもあれば、双方の折衷案を模索することもあるだろう。
そんなギリギリまで方向性に悩む案件に対しては、浜田省吾はどのようなアプローチをしているのだろうか。
「 長く音楽をやってる人間の難しいところでもあるんですけど、ずっと僕の音楽を聴いてくれているファンと、ポップスを旬のものとして聴いている幅広いリスナーとの接点をどう持てるかかのバランスですよね。例えば、今だと宇多田ヒカルさんとかラルク・アン・シエルとかGLAY、椎名林檎さんとか-ポップスのリスナーって、そういう人たちの曲を聴いている人だと思ってますから。
もし僕が今、真っ白な新人としてデビューするとしたらどうするかということと、今までやってきたことにのっかって、これまでのリスナーだけを想定してつくること。僕は、そのどちらかに偏るのは嫌なんです。」(日経エンタテイメント 2000年5月号より)
やはり自らの音楽活動に関する重要な方向性に関しては、バランス感覚を大事にしたいということだろう。古くからのファンの要望にも応えたいし、流行を追うリスナーの感性にも合う曲もつくりたい。その両方のバランスをとりながら、アルバム制作やライブの選曲に工夫をしているはずだ。
このバランス感覚はビジネスのあらゆる局面でも求められるのではないだろうか。
例えば、究極的なテーマとしてサービスの質の向上とコスト削減の問題がある。このサービスとコストの関係は対立することも多い。
サービス向上とコスト削減、その片方のみを追求すると事業は傾いてしまう。
ありがちな話だが、脱サラをして喫茶店やペンションを経営したいという人も多いだろう。そして、いざ夢がかなって開業することになり、気合が入りすぎることになる。
とにかくお客様第一だからということで、出血サービスをしてしまう。減価償却も何も考えずに、夢の城に資金を投じて料金は良心価格に設定。その結果、赤字を垂れ流すことになり、「儲からない」と嘆くようになる。これでは経営とは言えない。
逆に、ローコストの過剰追求も悲劇を呼ぶ。品質や安全性を犠牲にしてまでコスト削減を極めた結果、マンションの耐震強度偽装問題を引き起こし破産した会社もある。この問題では、単に事業者が破産しただけでなく、多数のマンション住民を絶望の淵に追い込んでしまった。その責任は大きい。
やはり、物事には限度があるということだろう。サービス向上もコスト削減も、その片方だけを見て突き進むとロクなことにならない。
かといって、サービスも価格も中途半端な状態では、シビアな日本の消費者には見向きもされない。サービスはイマイチ、それで価格はどうかと言えばこれもイマイチ。そんな事業者の気の迷いが伝わるようなモノは売れるはずがない。
そこで顧客に支持されるには、高いレベルでサービスと価格のバランスをとることが求められる。サービスの質はできるだけ高く、コストは常識の範囲内で可能な限り抑える。それはとても苦労する作業だが、その過程を経て顧客の満足度は高くなる。
そんなバランス感覚を大事にする浜田省吾だが、今までに蓄積してきた楽曲とファンからの評価だけでは満足していないようだ。
常に新しいモノや時代の流行にも無関心ではない。
2000年4月に新曲「・・・to be “kissin you”」を発表した際には、ファンの間でもその斬新さが話題となった。
この曲のプロモーションビデオはアメリカで撮影され、ミュージシャンは現地で探したそうだ。その現地のベーシストは「日本の音楽はアメリカに比べて10年遅れていると思ってたけど、これはカッコいいじゃん。やらせてよ」と言ったという。(日経エンタテイメント 2000年5月号より)
本音で物を言い、自分が良いとは思えない音楽に関与するのは拒む職人肌のミュージシャンからも、曲の斬新性や独創性を認められている。
これは従来までの成功パターンに安住しない、創作に対して貪欲な姿勢を示している。
遠山が取り組んでいる商業ホームページの分野も、変化が激しい激戦区だ。何か目新しいホームページができると、その1ヵ月後には競合ジャンルのホームページがガンガンと出現する。
あまりに同一ジャンルのホームページが増殖していくので、数ヶ月でそのホームページが持っていた斬新性は損なわれるありさまだ。
何か新しいサービスを開発したとしても、それが目新しく思える賞味期間は短い。そんな過激な競合が起きる現場では、絶えず改良や新ネタの披露が求められる。新しいネタを探してあれこれ考える期間は、本当に苦しいものだ。
この改良や改善という発想は、何も音楽業界やIT業界だけに限った話ではない。製造業からサービス業まで、全ての業種で求められている。
過去の実績に満足してしまえば、事業の成長はそこで終わってしまう。そういった実績を大事にしながら、更に新しい工夫を積み重ねていくバランス感覚を持つことが必要だ。
投稿者 : 02:28 AM
インターネットや図書で情報検索をして、それをビジネスの資料として活用する場合に、著作権を理解しておかないと都合が悪いことが多い。
自分では知らないうちに他人の著作権を侵害し、後から損害賠償請求をされるような事態になったらたいへんだ。
音楽業界では特に著作権の権利関係がややこしい。著作権ビジネスとでも言うべき複雑な利権が絡むようだ。
これには浜田省吾も頭を抱えている。
「 シングル(CD)を売るというシステムがどういうものであるかっていうのは-ユーザーの人は知る必要もないことなのかもしれないけど、いかに露出していくかと。そして、その中で最も力を持ってるものはダントツにテレビであると。テレビの中で最もたくさん露出するものはドラマの主題歌であったりCMであったりするわけですけど、当然そこからたくさんのヒット曲が出てそれがたくさんのお金を生んでるがために、ガッチリとしたシステムがもうでき上がってるんですよね。具体的にじゃあこの楽曲の何%、この楽曲が入ってるアルバムの何曲分の著作権をどういうふうに分配しろ、しなければ使わない-もうそういうところなんですよ。だから、ものすごくいい作品だからシングル盤として世の中に露出して、それがメガヒットになっていくというような時代ではもうないんですよね。」(BRIDGE 2001年10月号より)
ドラマやCMのタイアップをとるためには、各方面に著作権により得られる収益を分配しなくてはならないという世知辛い話ではないか。
比較的最近でも、浜田省吾の曲に対してこうしたタイアップの打診はあったようだ。ある程度具体的な話になり、スポンサーも曲を気に入ってくれたようだが、あまりにもえげつなく収益を吸い上げられるので断ったそうだ。
ファンとしては単純に浜田省吾の曲をCMやドラマの名場面で聴きたいと願うわけだが、彼の事務所経営を考慮すると、得体の知れない金を宣伝費としてジャブジャブ使えない。そこにファンの想いに応えられないもどかしさはあろう。
ところで、音楽業界で著作権と言えば、日本音楽著作権協会(ジャスラック・JASRAC)の話題を避けて通ることができない。
JASRACとは、音楽の創作者の著作権を一括管理し、利用者から料金を回収して、手数料を差し引いて著作者に報酬を分配する団体だ。
テレビで流れるBGMや喫茶店の有線放送など、著作者自身が個別に利用状況をチェックするのは事実上不可能だ。テレビ局や有線放送事業者も、いちいち個別の著作権者に料金を支払うのでは作業量が膨大となってしまう。
そこで、JASRACが窓口となってテレビ局等と大口の契約を結び、著作権の細々とした作業を一手に引き受けているのだ。著作料の徴収を一括にしてプールし、独自の配分方式によって著作者に分配をすることで、個々の徴収・分配作業負担を軽減している。
だが、JASRACとの契約で問題が無いわけではない。カラオケでは使用料や権利者への分配方法が未決のままビジネスが先行するという弊害も生じた。
また、音楽のネット配信については著作権者が個別に管理が可能なのに、それも従来メディアと混同して一括管理されることの効率の悪さも指摘されている。
更には、消費者から見て著作者に著作料が正当に分配されているか確認する手段は無く、著作者にとっても適切に分配されているという根拠は持てない。
この音楽著作権の権利料は、消費者にとっても著作者にとっても不透明なままだ。あなたが浜田省吾のカラオケを唄った場合に、そのうちいくらが彼の事務所に支払われるか把握する術はない。
それから、JASRACは著作権侵害に対する法的対応も行っている。意図的な著作権の権利侵害は問題外だが、日常のビジネスで無意識のうちに著作権侵害をしてしまう可能性もある。
例えば、自分のブログに浜田省吾の曲の歌詞を書く場合、一定のルールを守らないと著作権法違反となってしまう。
ビジネスで公表する資料に、ホームページで見つけた資料を勝手に複写するのもご法度だ。
しかし、著作権者の権利を過剰に保護しすぎるのも問題がある。それでは他人の研究資料を活用して、更なる高度な創作をしていく可能性を摘み取ってしまう。
そこで、著作権法ではある程度の条件のもとで、ホームページや書籍の内容を紹介することを認めている。
具体的には、公表された著作物に関して、批評や研究の正当な範囲内で、出所を明示すること等が条件となる。
こうした条件を満たした紹介を「引用」と呼んでいる。
ビジネスの現場で公表を前提とする文書を作る機会は多いものだ。その際に、参考文献やホームページの出所を明示する引用は、最低限のルールとして押さえておかなくてはいけない。
何にしても、他人の著作物には敬意を払い、無断複写ではなく正当な引用を心掛ける配慮が求められるだろう。
投稿者 : 02:23 AM
日本で生活していく上で、お金は必要不可欠なものだ。これが無ければ、ぶっちゃけ生きていけない。
浜田省吾とお金と言えば、メジャーな曲がすぐに思いつく。
そう、「MONEY」だ。
初めて「MONEY」を聴いたときは、それはもうブッたまげた。「いつか奴等の足もとにBIG MONEY 叩きつけてやる」とか「あのとき彼女はこう呻ぎ続ける 愛してる愛してる もっともっと」などと、いかにもキレまくった歌詞が続く。
挙句の果てに「俺は何も夢見ない 何もかもみんな爆破したい」と叫んで意味不明な絶叫をする。
浜田省吾に最初に接した曲がこの「MONEY」だったら、イカレたパンク野郎という印象を持ったかもしれない。
社会人になって、カラオケに行くと「MONEY」を唄うビジネスマンが多いことも驚いた。浜田省吾をほとんど知らない人が、「MONEY」だけは知っていて気持ちよさそうに絶叫している。
「マネーーーー!!」とシャウトするのが爽快なんだろう。
しかし、これを日本語に直訳すれば「カネーー金ーー」と叫んでいることになる。そういう姿を連想すると、ちょっと気恥ずかしくならないだろうか?
どうも日本人はお金に執着する様子を否定的にとらえるところがある。日本語で「カネ、ゼニ」と叫ぶのはカッコ悪いが、「マネー」なら許されるようだ。
この曲の歌詞をよく読めば、お金で何でも買えるわけでもないし、稼ぐことばかり追い求めていると人生が狂ってしまうという警鐘だと理解できる。
「欲しいものは全てブラウン管の中 まるで悪夢のように」という歌詞が、テレビで煽られる欲望は、決して尽きることがないと暗示している。(テレビも時代とともに変化して、“ブラウン管”は死語になりつつある。歌詞が“スクリーン”とかに置き換わる時も来そうだ。)
そして何より残酷な事実は、「純白のメルデウス プール付きのマンション」はいくら猛烈に働いても、ほとんどの人には手が届かないという現実だろう。
それゆえに、酔っ払ったビジネスマンは「マネー」と絶叫するのだ。
それでは下世話な話になるが、この歌を1984年に発表した浜田省吾自身の懐具合はどうなのであろうか?
長者番付の歌手部門をチェックすると、1988年に初めてベスト10入りし、1990年から1992年までは3年連続でベスト10入りしている。
どうやらBIG MONEYは手に出来たようだ。羨ましい限りだ。
そして、株式投資に失敗したとか会社をコケさせたという噂も聞かない。矢沢永吉のように詐欺・横領事件に巻き込まれて35億円の借金を背負うなんてこともない。(矢沢永吉はその借金を6年で完済したという。そのパワーは凄まじい。)
そんなマイナスの話題が上らないということは、堅実な運用をしているのだろう。
誰もが欲しがるお金ではあるが、交換価値が無ければ単なる紙切れになってしまう。その紙切れ自体には何の価値も無い。
貨幣は全国どこでも通用するという信頼感があって、初めてその威力を発揮する。
最近では、アタッシュケースに札束を詰め込んで商談をするのは現金問屋くらいだ。ほとんどの大口取引は銀行間のオンラインを通じて、無視質なデジタル符号を交信することで完結してしまう。
遠山のような零細事業でも、クライアントからはネットバンキングの振込だから、入金処理の際に札を手にすることは無い。
そんなあやふやな預金残高の数字を信用してモノが動いているわけだ。それでは、その信用というのは誰が保証しているかというと、国家ということになる。
この肝心要の日本国が、国際的に信用を失墜する失態を犯せば、何億と預金があろうとその数字には何の価値もなくなってしまう。
絶対に潰れることは無いと言われた都市銀行や4大証券の一角が破綻することもあるのだ。通貨の信用不安が起きないという確証は無い。
そう考えると、生き抜いていく上で本当に必要なのは“信用”ということになるのではないか。貨幣経済も通貨に対する絶対の信頼感を前提としている。
世の中はお金中心に回っているように見えて、実は本当のところ経済の根幹は信用に尽きるのだ。
日本経済への信用、会社の信用、個人の信用。これらは密接に絡んでいる。そして、より多くの人から信頼される事業や個人にお金は集まるようにできている。
逆にいうと「金儲けが第一」というオーラを発する人のところには、不思議と人は集まらない。人を集める集客力が無ければ、お金も集まらない。金儲けを自己目的化してはいけないということだ。
人のために役立ち、社会に貢献できる事業こそ、長く愛され支持されるものと言えよう。浜田省吾もファンの心をつかんだからこそ、相応の経済的対価を得ることができたのだ。
投稿者 : 02:21 AM
浜田省吾のCDについては、アルバムに関してはいくつかのミリオン・セールスを記録している。しかし、シングル売上に関しては全般的に低調だ。
そんな中で、唯一の大ヒットを記録したシングル曲が「悲しみは雪のように」だ。
この「悲しみは雪のように」は、1992年にシングルCDとしてリリースされ、200万枚近くを売り上げた。
記憶されている方も多いと思うが、この曲はドラマ「愛という名のもとに」の主題歌として使われ、そのタイアップが奏功した。浜田省吾にしては珍しい取り組みだった。
「愛という名のもとに」では、毎回浜田省吾の曲がBGMとして流れ、それを楽しみにドラマを視聴するファンも多かった。
ちなみに、このドラマでは唐沢寿明と江口洋介が大学時代の友人(と同時に恋敵)という役所で共演し、その11年後の2003年に名作「白い巨搭」でも二人は主人公として共演した。
その「愛という名のもとに」について、当時プレイボーイ誌でハウンドドッグの大友康平が疑問を投げかけていたことを記憶している。
それは、ドラマに登場する友情があまりに安っぽくて、「浜田省吾兄貴の曲が泣く」という指摘だった。
遠山も同様の印象を持っていたため、その意見に深く頷いていた。
セールス記録の上では、「悲しみは雪のように」がブッチギリの存在感を示しているが、この曲が浜田省吾の代表曲かと問われれば、それは違うという思いを持つファンは多いだろう。
一般的な浜田省吾の代表曲と言えば、「J.BOY」「MONEY」「もうひとつの土曜日」あたりをイメージするのではないだろうか。
「悲しみは雪のように」は、どちらかと言えば地味な曲と言う印象が強い。
それにもかかわらず、「悲しみは雪のように」のセールスが金字塔となっているのは、やはりドラマとのタイアップのマジックという結論になるのではないか。
テレビで広くプロモーションされれば、必然的に多くの人々がその曲を耳にする。そして、それがメガ・ヒット曲を生み出す。そんなシステムが出来上がって、テレビ抜きではCDセールスが考えられない状況となってしまった。
もちろん、インディーズから這い上がってくる逞しいミュージシャンもいる。だが、そんなミュージシャンもブレイクする段階では、やはりテレビの力を借りていることが多い。
つまり、ヒット曲とテレビは密接な関係にあるということだ。言葉を換えると、テレビの巨大な広告力に頼らないと、日本の音楽業界では生き残れないという構図が出来上がってしまった。
浜田省吾はテレビ経由で曲をセールスするのではなく、直にファンと接するライブで支持されてきたことは何度も述べた。
すると、テレビ・ドラマとのタイアップでセールスした「悲しみは雪のように」は、どうしても異色の存在となる。
昔からのファンにとっては、この曲がこれだけ売れるなら、もっと売れても良い曲はたくさんあるというのが偽らざる心境ではないだろうか。
以上のような理由もあって、遠山はこのミリオン・ヒット曲に対する思い入れは少ない。(もちろん、メロディーや歌詞が優れていることは確かだが、他にももっと脚光を浴びても良い曲があると思うと、感情的に判官贔屓になるのかもしれない。)
このように比較的に地味な曲であっても、テレビでプロモーションされることによって、そのミュージシャンの代表曲として世間的に認知される現象がある。
繰り返すまでも無いが、それだけテレビやマスコミの影響力は巨大ということだ。また、歌番組で取り上げられるランキング情報は、本来は極めて多岐に渡るはずの音楽的嗜好について、画一的な序列意識を植え付ける。
つまり、ランキングのトップ10に入らない音楽は、優れた音楽では無いと判決されるような状況だ。
これはあらゆる商売でも共通する現象だ。何か商品をPRしたいと思い、必死で商品の良さをうたった広告を出しても、なかなか良い反応を得るのは難しい。
しかし、何かのきっかけでテレビ番組でその商品が取り上げられると、瞬時に凄まじい問い合わせが殺到する。そして、ウソのように商品が売れてしまう。
今なら、みのもんたが健康番組でお墨付きを与えた商品の売れ行きをリサーチすれば、その影響力を実感できるだろう。
でも、テレビで報道されないが、目立たないけれどももっと良い商品はあったりするものだ。
そんなテレビやマスコミの神通力を期待して、事業をする人はマスコミに取り上げられようとプレス・リリースに躍起になる現実もある。
実際、遠山も少ない経験ながらマスコミに取り上げられた実績はあり、その反響や第三者に与える信用感について、恩恵を授かったこともある。
そんな時には内心、「自分なんかよりも、もっとその分野でのスペシャリストはいるから、その人にインタビューして貰った方がいいかもしれない。」と思うことはあった。
要はマスコミに取り上げられる情報だけが全てでは無いのだ。テレビの情報だけを頼りに音楽をチェックしていたら、ほぼ永遠に浜田省吾とは出会えない。
リスナーというお客様と対面するライブを最重要視するミュージシャンが存在するように、マスコミには登場しない優れた商品やサービスも多く存在する。
そうした商品を選ぶ目を失ったら、人生の中で損をすることもあるだろう。商品やサービスを優れているかどうか判断するのは、マスコミではなくあなた自身なのだから。
投稿者 : 02:20 AM
浜田省吾が主演するショートムービーを見たことがあるだろうか。
もちろん一般には公開されていない。というのも、浜田省吾のライブの休憩時間でこれが映し出されるのだ。(例外的に2001年にNHK-BS等で浜田省吾自身が企画編集した番組でショートムービーが披露されている。)
浜田省吾のライブでは、休憩時間もサービス精神旺盛。ライブの中間で10分程度の休憩があるのだが、この時間に観客が退屈しないようにステージ上の大スクリーンにオリジナル映像が流される。
しかも、これが浜田省吾主演のショートストーリーになっていて、まさにレアもの。
これを見逃すのはもったいないと思い、ついついトイレに行きそびれたファンも多いだろう。
例えば「ON THE ROAD 2001」ツアーでは、「ミッドナイト・キャブ」と「マリア」というタイトルのショートストーリーを披露されている。
ちなみに「ミッドナイト・キャブ」は、浜田省吾扮するニューヨークのタクシー運転手に、様々な乗客がその人生模様を語りかけるグランドホテル形式の逸品。無邪気な不良少年たちの武勇伝、娼婦風の女性が恋人に客の暴行を嘆く、東洋人(日本人?)が株の暴落に断末魔の悲鳴をあげる、寡黙な老紳士が大切な人の死を語るなど。
このように乗客の人生観を、寡黙な運転手の浜田省吾がただ頷いて聞いている場面が印象的だった。
さらに「マリア」では、大農場でメキシコ人労働者が農作業をする様子が映されていたが、その中に浜田省吾が混ざって農夫役をしているのを見つけると、会場から笑いが起こった。やはり農作業中でもサングラスは外さない。
さすが我らが浜田省吾だ。
そんな農作業後の歓談のとき、浜田農夫と地元の美少女のマリアがその世界観や職業観をしみじみと語るという印象的な場面もあった。
なんでも、この「ミッドナイト・キャブ」にしても「マリア」も、そのテーマは“働く”ということだそうだ。
そういえば、浜田省吾の曲には“ビジネス”や“仕事”について触れる歌詞が多い。ロックにしろR&Bにしろ、流行歌のテーマはほとんどは“恋愛”が主流だが、そういう点でも異色といえるだろう。
もちろん、浜田省吾もラブソングはたくさん作っているし、その評価も言うまでもなく高い。でも、人間は四六時中恋愛だけを考えて生きているわけではない。働き盛りのビジネスマンが音楽CDを買わない現象というのは、案外恋愛漬けの流行歌に食傷気味になっている事情もあるのではないか。もう学生ではないんだし、愛だ恋だと浮かれている気分じゃないっていうのも本音だろう。
遠山自身の感性が人と違っているところがあるのかもしれないが、はるか昔の高校生の頃からラブソングしか入っていないアルバムに違和感を持っていた。いいラブソングは確かに好きだが、歌の全てが恋愛一色だと「あんたの頭の中は恋愛しかないのか?」と当時毒づいていたものである。何か無理に恋愛を強制する“恋愛押し売りソング”が氾濫しているようで、流行歌を聴きたいとは思えなくなっていったこともあった。
しかし、そんな偏屈な少年時代を過ごしていた遠山が大学に入学した年に、浜田省吾のアルバム「J.BOY」を聴いて衝撃が走った。
出逢ってしまった…。
なんとアルバムの1曲目から「A NEWSTYLE WAR」なんていう反戦歌が入っている。
「J.BOY」では過労死が社会問題になるなかで、仕事におぼれるビジネスマンの心境を吐露している。その他にも父親の人生観やアルバイトで苦学する歌など、生活に密着して共感を得る曲が多かった。
ラブソングも「19のままさ」や「遠くへ」などは、将来の不安を抱えて吹けば飛ぶような存在の自分の境遇にまさに一致した。
その時以来、浜田省吾が「通りのウィンドーに飾ってあったギターを見たとき」並みの稲妻が体を駆け抜けて、彼がリリースする曲は必ずチェックするようになった。
浜田省吾と仕事(職業観)については改めて語りたいと思うが、ここで注目するべきは、ショートムービーである。
浜田省吾が、ファンを第一に考えていることはすでに何度も述べたが、このサービス精神は見習うべきことが多いのではないか。
なにしろ休憩時間という、ある意味で消費されるだけの時間のために、わざわざショートムービーを作ってしまう。そんなアーティストが他にいるだろうか。
休憩時間(=プライベートな時間かもしれないし、接待ゴルフかもしれない)の有効活用は誰でも考えることである。
が、そんな時間も全力投球するのが、浜田省吾だ。
そもそもエンタテイメントという言葉の語源は、人をもてなすという意味である。
ステージで唄うのは当たり前、いい音楽を届けるのも当たり前。それが、浜田省吾だ。
では、休憩時間をどう使うのか?
そこに、浜田省吾はショートムービーを持ってきた。すごいと思った。手抜きはない。すべての時間を意味あるものにする。そこに集ったファンに、一時たりとも退屈をさせまいと尽力している。
文字通り、もてなす心。
そこに、エンターティナーとして仕事に取り組む姿勢を学ぶことが出来る。日常の仕事の中にも、探せばまだいくらでも、改良することはあるのではないだろうか。相手をもてなすという気持ちになれば、もっとやるべきことは見つかるはずだ。
投稿者 : 02:18 AM
浜田省吾がテレビに出ないことは何度も取り上げてきた。
しかし、全く出演していないわけではない。レア・ケースだが何度かはテレビ出演もしている。
それには二つの傾向がある。
一つは、デビューしてから日の浅い黎明期だ。偉大な“ロックスター”浜田省吾であっても、初期の頃は無名の新人であった。まずは多くの人に自分の曲と名前を知ってもらう必要に迫られていた。
そのためには、テレビに出て演奏を披露する機会を自ら求めていた。また、テレビCMとタイアップした曲作りにも挑戦して、日清のカップラーメンに「風を感じて」が採用された。
歌番組も「夜のヒットスタジオ」等に出演し、どの新人ミュージシャンもが願うように、そこからブレイクする曲を期待した。
しかし、小さなヒットは記録するものの、それまでのやり方ではメガ・ヒットというものは実現しなかった。
そして、彼のロックやバラードについては、テレビ出演によってはヒットさせることが難しいと感じたのであろう。1980年のテレビ神奈川「ファイティング80‘s」を最期に、長らく歌番組との関係は断絶することになった。
そして、この頃から“浜田省吾のライブのライブは熱い”という評判が高まり、年間100回以上の公演をこなすようになっていった。
もう一つのテレビ出演は、2001年までスキップする。この年に何と21年ぶりとなるテレビ出演を果たした。バリバリに売れているミュージシャンが、21年間もテレビに出なかったとは信じがたいものだ。
この2001年の8月にはNHK-BS(90分)、10月にはNHK総合(60分)、12月にはNHK-Hi(120分)に出演し、関係者は“NHK三部作”と呼んだ。
この一連の番組では、全て浜田省吾側が責任編集を行い彼専用の特別番組となった。選曲からコメントまで浜田省吾自身が編集に関与し、タイアップ狙いのプロモーションとは一線を画していた。
この企画が実現するまでには、NHKプロデューサーの熱意があったという。NHK側は1999年から出演交渉を続けたが、浜田省吾の回答は“興味は無い”という素っ気ないものだった。もちろん、礼儀正しい浜田省吾のことだから、ソファーで足組みしながら尊大に振舞うようなことは無く、丁重にお断りしたのだろう。
だが、2000年に「THE HISTORY OF SHOGO HAMADA "SINCE 1975"」というベストアルバムを発売し、これが150万枚を超えるセールスを記録し、これまでの固定ファン以外のリスナーがアルバム購入してくれたことをありがたく思ったという。
そして、2001年がデビュー25周年ということもあり、初めて浜田省吾の曲を耳にする人たちにも、きちんと自己紹介をしたいという気持ちになったそうだ。
そこでNHK側の熱意と浜田省吾の感謝の気持ちが同調し、NHKは「絶対にテレビに出ないカリスマスター」をテレビに連れ出す偉業を達成した。
この特別番組に驚愕し歓喜したファンは多いだろう。遠山もキッチリとこの三部作は録画し、何度も観たクチだ。
少し余談となるが、10月8日のNHK総合での放映の際には、9.11テロの報復としてアフガニスタンへの空爆開始を報じる字幕テロップが流れ、番組は中断した。
その時は浜田省吾がビルの屋上で「愛の世代の前に」を唄っているシーンで、「憎しみは憎しみで 怒りは怒りで 裁かれることになぜ気づかないのか」と熱唱していた。
その途中で放送が中断されたのは、反戦歌がアメリカ軍の横暴により打ち消される様を見たようで後味が悪かった。(こうした番組中断があったので、後日再放送された。)
そんな偶然からも、浜田省吾の平和を求める姿には、何か因縁めいたものも感じてしまう。
これらNHK三部作では、貴重なライブ映像やプロモーションビデオの映像を堪能できた。その他にも、浜田省吾のヒーロー像やラブソングについてなど、様々なインタビューもたくさん聞くことができた。
特に異色だったのが、陣内孝則とのショートコントで、陣内扮するプロデューサーが浜田省吾に説教をするものだった。
「曲が暗い。明るくしようよ。」「もっとドラマとタイアップしてガッポガッポ儲けよう。」等とキワどい台詞を連発し、その皮肉さに笑ってしまった。
全体としては、コアなファンとしても満足がいく内容だった。はじめて浜田省吾を目にする人たちは、彼の人柄に触れてもっと他の曲も聴いてみたいと思ったかもしれない。
ショートコント等で浜田省吾の新境地を見た気がしたが、残念ながら今後のテレビ出演の可能性は無いという。(ひねくれたコアなファンは、その方向性に安堵していることだろう。)
このように、浜田省吾もテレビを100%否定しているわけではない。テレビにまつわる様々な制約の存在が、その利用を躊躇わせてきたと言えよう。
例外的にデビュー25周年の時に、より多くの人に知ってもらうためテレビ出演をした実績はあるのだ。
これは商業主義の象徴であるテレビとの微妙な距離感を示している。
それだけにテレビは魔物といえる。うまく付き合わないと、その過剰なまでのコマーシャリズムに染められてしまう。
そんな危機感を持つ浜田省吾の良識を感じ取り、テレビに溢れる情報との接し方も再考したいものだ。
投稿者 : 02:16 AM